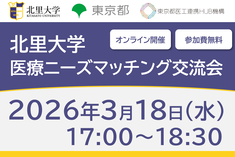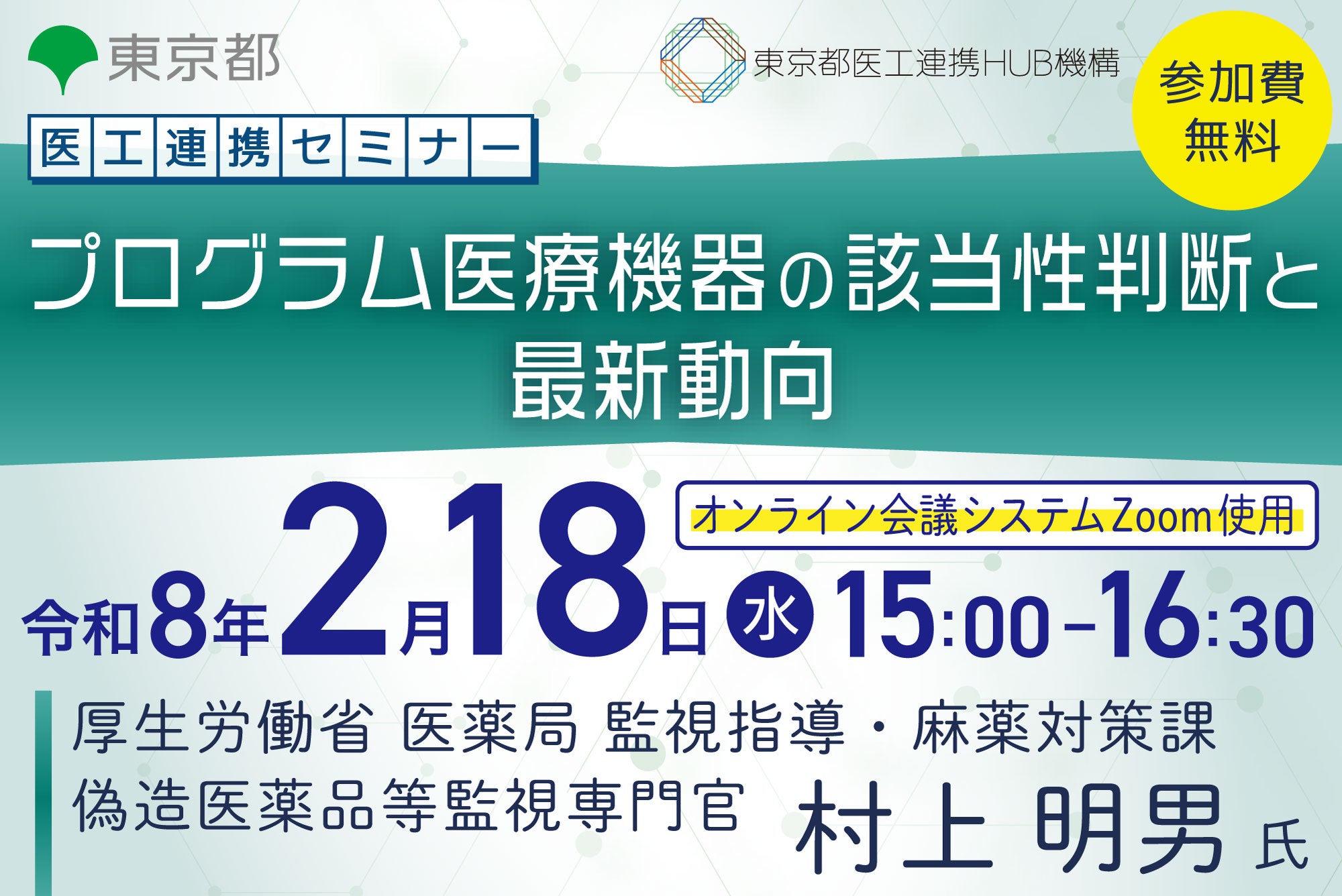ライフサイエンス研究のオピニオン・リーダーに話を聞く「スペシャルインタビュー」。第1回目となる今回は、LINK-J運営諮問委員会・特別諮問委員であり、「超音波による腎結石破砕技術の開発」など、東京大学で早期から「医工連携」に取り組んできた松本洋一郎氏にお話をうかがいました。前編となる今回は、アーヘン工科大学(ドイツ)留学、東京大学での「医工連携」の歩み、サイロ・エフェクト(縦割り組織における部分最適化)とイノベーションなどについて、お聞きしました。
――専門領域についてお教え下さい。
専門領域は「流体力学」です。東京大学では工学部に在籍し、1981年にはアーヘン工科大学・衝撃波研究所に、客員研究員として1年間留学しました。当時のテーマは「気泡力学とキャビテーション」。気泡流内における衝撃波や超音波の伝播などを研究していました。
ちょうどその頃、衝撃波を用いて腎臓結石を破砕する技術が登場しました。その研究を横目で見ながら、漠然と「流体力学は医療技術にも応用できるかもしれない」と考えるようになりました。もっとも、当時はまだ私がその開発に従事するとは思っていませんでした。
――その他にはどのような研究をされていたのですか?
帰国後は、東京大学で「衝撃波を分子スケールから連続体スケールまで統合して計算する」マルチスケール解析手法の開発に取り組みました。分子スケールの実験が可能な装置はアーヘン工科大学にあったので、計算の正しさを確認するため、東京大学から博士課程の学生を現地に派遣し、共同研究を行いました。計算による予測結果と現地での実験結果がピタリと一致し、喜んだものです。
また、留学時にイメージしていた「流体力学の医療応用」にも挑戦しました。きっかけは、研究者同士のディスカッションで「集束超音波による前立腺がんや乳がんの治療」を知ったことでした。話を聞くと、超音波でがんを加熱・凝固し、老廃物として排出させる治療法だという。免疫を強化する物質が放出されるため、治療部位とは異なるがんにも効果が波及する上、放射線療法と比べて身体的負担も小さいと聞いて、興味深いと思いました。
――それが後の「超音波による腎結石の破砕技術」につながるわけですね。
当時の東京大学では、桐野高明先生(元医学部長、当時副学長)と小宮山宏先生(元工学部長、当時副学長)の2人が医工連携の重要性について話をし、大学病院内に医工連携の研究室が設置されました。「超音波による腎結石の破砕技術」も医工連携の対象となり、私たちが技術・装置を開発し、医学部の先生方が非臨床研究を担当しました。私自身も当時から、異なる分野の先生方と一緒に研究をすることが、イノベーションを起こす上で極めて重要であると考えていました。
その後、完成した装置を小宮山先生に見せたところ「これは面白い」と評価いただけたのをおぼえています。他にも、経頭蓋に超音波を照射することで深部脳腫瘍を攻撃する治療法、マイクロバブルと超音波を組み合わせた毛細血管の可視化技術、がん細胞の血管新生を標的とした超音波治療、超音波を用いた細胞膜穿孔などを研究していました。

――東京大学では総長補佐、副学長、理事と要職を歴任されました。
総長補佐を務めた当時、小宮山先生(後に総長)が「知識の構造化(自律分散的に創造された知識同士の関係性を明らかにするために構造化・可視化し、分散する膨大な知識を有効に活用する手法)」を提唱していました。そこで私も、同じく総長補佐だった医学部の永井良三先生と「知識の構造化を用いて、駆け出しの医師を名医にする方法」の開発などを検討していました。
その頃、東京大学で自然言語処理を研究していた辻井潤一先生と、MEDLINE(生命科学に関する文献情報を網羅するデータベース)の解析にも挑戦しました。独自のテキストマイニングを開発し、MEDLINEが保有する膨大な量のテキストから「生命現象の解析の鍵となるたんぱく質」などに関する情報を抽出するのです。現在の機械学習のはしりですね。
理事に就任した後は、工学部教授のポストは後任に引き継ぎましたが、研究室は継続しました。大学の運営という観点では、研究現場と常に接点を持つことは、とても大切です。現場から離れてしまうと、「現場の研究者が何を考えているか?」といった現場の感覚を失いがちだからです。大学側もそのように考えており、研究室を閉鎖しませんでした。
――大学の経営に携わるのと並行して政府の医療イノベーション推進室の室長に就任しています。
初代室長の中村祐輔先生の頃から、オブザーバーとして関与していました。その後、中村先生が渡米を理由に辞任することになり、私が次の室長に就任することになりました。当初は多忙を理由にお断りしていたのですが、紆余曲折あって、引き受けることになりました。
室長に就任して、大学内部からは見えない多くのことに気づきました。たとえば、霞ヶ関には様々な組織や役職があって、それぞれの縦割りが非常に厳しいのです。中村先生は、それを「霞ヶ関の谷間」と表現しました。いわゆる「サイロ・エフェクト」ですね。それぞれが自分のフィールドの中で仕事をしている状況です。この壁を乗り越えなければ、新しい発想は生まれません。
――背景が異なる人たちが共同することで新しい発想が生まれる?
私の研究室での話です。一旦就職していた学生が、方向性の相違で再び研究室に戻ってきたことがありました。短期間とはいえ企業のマインドが植え込まれた彼は、「同じフィールドの研究者なのに自分たちと異なる言葉で話す」新鮮な存在でした。特許に詳しく、申請のコツも心得ていました。結果として、彼の存在は研究室に広がりをもたらしたと思います。
大学も同じことです。「医工連携」では、工学者である私がいくら「これは素晴らしい技術だ」と自画自賛しても、医療者にとっては「使いものにならない」技術かもしれません。相手が求めるものを知り、それをこちら側の知識で咀嚼し、「こういう解があります」と提案する。互いが持つ知識を組み合わせれば、それだけ解はたくさん生まれるのです。
後編では、アカデミアの弱点である治験体制の整備や、大学の枠組みを超えた「八ヶ岳連峰型」モデルの重要性。また、ライフサイエンス業界における起業家社会の育成や、今後のLINK-Jに対する期待についてお話いただきます。
 松本洋一郎 氏
松本洋一郎 氏東京大学工学部を卒業後、東京大学大学院で博士課程を修了。東京大学講師、助教授、教授を経て工学部長に就任。評議員、副学長、理事など要職を歴任(現在は名誉教授)。助教授になりたての頃、アーヘン工科大学(ドイツ)に客員研究員として留学。また、内閣官房医療イノベーション推進室長を務めた。現在は理化学研究所理事、国立がん研究センター理事を務める。専門領域は機械工学、流体工学、計算力学、分子動力学、医療支援工学など。