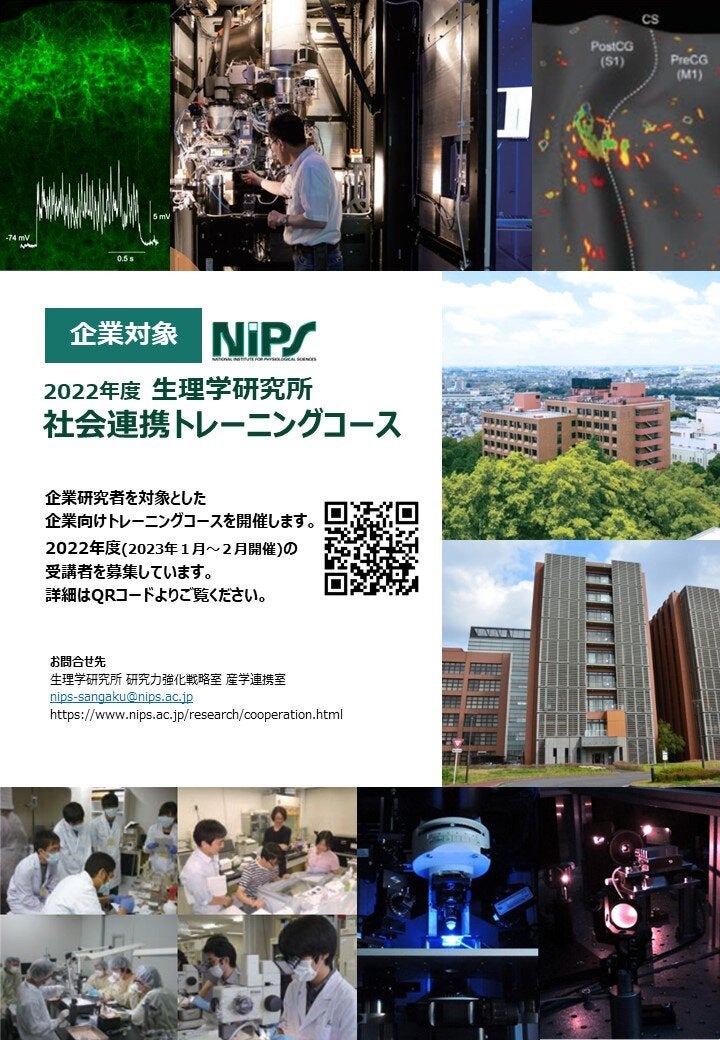水など物質は、温度の上昇によって固体から液体、気体へと状態を変化させていきます。そして、気体の温度をさらに上昇させたり、高電圧を加えたりすると電離が起き、物質は陽イオン、電子、中性分子が混在し、化学反応性に富んだ状態へと変化します。この状態が「プラズマ」と呼ばれるものです。プラズマという現象は自然界でもよく見られ、皆さんが知っているところではオーロラや雷などが代表的なものです。また、蛍光灯やプラズマテレビなども、プラズマを技術応用したものです。
プラズマには、粒子の温度が高く太陽と同等のエネルギーを作り出すことを目的とした核融合技術に代表される高温プラズマと、電子温度は高いが全体としては手で触れることができるほどに低温のプラズマがあります。この低温プラズマは、その汎用性の高さと扱いやすさから近年世界的に研究・応用が進められている、現在最も注目されている技術のひとつです。特に産業界や医学界からの期待は大きく、既に半導体技術への応用をはじめ、医療においては殺菌、消毒などで実用化されています。
日本政府の期待も大きく、2012年から2016年にかけて文部科学省 科学研究費助成事業にて「プラズマ医療科学の創成」と題した新学術領域が設けられ、活発な研究が行われてきました。そしてさまざまな分野にわたるプラズマバイオ研究分野同士の連携の輪を積極的に繋ぐことでプラズマバイオ研究の可能性をさらに拡げるべく、我々自然科学研究機構は新分野創成センターにプラズマバイオ研究部門を設置(2018年度)するとともに、名古屋大学と九州大学との間でプラズマバイオコンソーシアムを結成しました。その後2020年度にはコンソーシアムに東北大学が加わり、結成から4年目を迎える現在、さらに大きな規模で分野間融合型研究が進められています。
生命科学分野でのプラズマは、これまでとは異なったタイプの動植物への刺激方法であり、新たなストレス対応メカニズムを見出すと共に、それに基づく応用が期待されています。今回のシンポジウムでは、プラズマバイオ研究がこれまで辿ってきた進歩の過程を簡潔に紹介するとともに、医学、農学、工学など、さまざまな分野で徐々にあがりつつある最新の研究成果の数々を紹介します。さらに講演後にはパネルディスカッションを行い、プラズマバイオ研究分野がもたらす未来について視聴者の皆様とともに考えてみたいと思います。
・LINK-J会員は先着30名の方にてライブ配信会場での直接の視聴が可能です。
応募方法はイベントの配信メールにて(8月3日配信予定)お知らせいたします。
・新型コロナウイルス感染拡大状況を考慮し、講演者4名(佐々木様、大坪様、中村様、石橋様)は東京会場でのご登壇を予定しておりましたが、オンラインでのご登壇へと変更となりました。(8/18追記)
参加方法
お時間になりましたら、下記視聴URLにてご視聴ください。視聴URLこちらにてご視聴ください。
・Youtubeなどの操作方法等はご自身で事前にご確認をお願いいたします。
LINK-J会員の方のみ、先着30名様に限り会場にて参加が可能です。応募方法はイベントの配信メールにて(8月3日配信予定)お知らせいたします。
*国からの要請あるいは新型コロナウイルス感染拡大状況等の理由から、リアル会場での開催を中止する場合があります。
プログラム
| 時間 | 内容 |
| 13:00- | 機構長挨拶 小森 彰夫 氏(自然科学研究機構 機構長) |
| 13:05- | 「プラズマバイオ概要説明」 井本 敬二 氏(自然科学研究機構理事/新分野創成センター長) |
| 13:20- | 「大気圧空気プラズマを用いた五酸化二窒素の選択合成とその応用展望」 佐々木 渉太 氏(東北大学大学院工学研究科 助教) |
| 14:00- | 「酵母で迫るプラズマの謎」 大坪 瑶子 氏(自然科学研究機構核融合科学研究所/基礎生物学研究所/新分野創成センター 特任助教) |
| 14:30- | 「プラズマによるがん克服への挑戦」 中村 香江 氏(名古屋大学低温プラズマ科学研究センターバイオシステム科学部門 特任講師) |
| 15:00- | 「農作物の種子に対するプラズマ照射効果の謎に迫る」 石橋 勇志 氏(九州大学大学院農学研究院 准教授) |
| 15:35- | パネルディスカッション 司会 坂本 貴和子 氏(自然科学研究機構研究力強化推進本部 特任准教授) パネリスト 井本 敬二 氏・佐々木 渉太 氏・大坪 瑶子 氏・中村 香江 氏・石橋 勇志 氏 |
| 16:05- | 挨拶 吉田 善章 氏(自然科学研究機構 副機構長) |
※講演題目は変更になる場合がございます。
登壇者
| 登壇者プロフィール | |
 |
井本 敬二氏 自然科学研究機構 理事、新分野創成センター長、プラズマバイオコンソーシアム 世話人 1976年 京都大学医学部医学科卒業 1990年 京都大学助教授 1995年 岡崎国立共同研究機構生理学研究所教授 1999年 岡崎国立共同研究機構生理学研究所研究主幹 2004年 自然科学研究機構生理学研究所研究連携担当主幹 2007年 自然科学研究機構生理学研究所研究総主幹 2011年 自然科学研究機構生理学研究所副所長 2013年 自然科学研究機構生理学研究所長 2016年 自然科学研究機構理事 2019年自然科学研究機構理事(非常勤) |
 |
佐々木 渉太 氏 東北大学大学院工学研究科 助教 2017年 東北大学 大学院工学研究科 電子工学専攻 博士後期課程修了 2017年 University of Minnesota, Department of Mechanical Engineering, Researcher (日本学術振興会 特別研究員PD) 2018年~ 東北大学大学院工学研究科 助教 |
 |
大坪 瑶子 氏 自然科学研究機構核融合科学研究所、基礎生物学研究所、新分野創成センター 特任助教 2009年 東京大学大学院 理学系研究科 生物化学専攻 博士課程修了 博士(理学) 2012年 かずさDNA研究所 特任研究員 2015年 基礎生物学研究所 日本学術振興会特別研究員(RPD) 2018年 核融合科学研究所 ( 基礎生物学研究所 併任) 特任助教 |
 |
中村 香江 氏 名古屋大学低温プラズマ科学研究センターバイオシステム科学部門 特任講師 2009年 名古屋大学大学院医学系研究科博士課程修了 2009年 Department of Internal Medicine Division of Cardiovascular Medicine,University of Michigan Medical School / Visiting researcher 2011年 医療法人葵鐘会 / 研究員名古屋大学大学院医学系研究科産婦人科学 / 客員研究者 2019年 名古屋大学低温プラズマ科学研究センター バイオシステム科学部門 / 特任講師 |
 |
石橋 勇志 氏 九州大学大学院農学研究院 准教授 2008年 九州大学大学院 生物資源環境科学府 博士後期課程 修了 博士(農学) 2008年 日本学術振興会特別研究員(PD) 2011年 九州大学大学院 農学研究院 特任助教 2014年 九州大学大学院 農学研究院 准教授 |
| 登壇者要旨集はこちらより御覧ください。 | |
対象者
生命科学・プラズマ工学に興味を持っている一般の方
参加費
無料
主催
主催:大学共同利用機関法人自然科学研究機構(NINS)、プラズマバイオコンソーシアム
共催:一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン(LINK-J)
お問い合わせ先
第32回自然科学研究機構シンポジウム 事務局
Tel:03-5425-1898 Fax:03-5425-2049 E-mail:sympo32@nins.jp