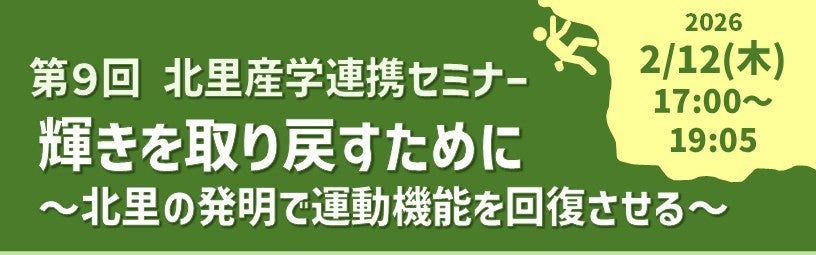中央研究所が研究開発のイノベーションエンジンと考えられていた時代、自らも日立製作所の電子顕微鏡の研究者として20年余を過ごし、世界を牽引。その後、基礎研究所長、中央研究所長を経て、ヘルスケアビジネスユニット、ライフ事業統括本部のCSOを務めてきた長我部信行氏に、産学連携の状況や課題、大学発ベンチャー、人材開発など、多岐にわたるお話をお伺いしました。
中央研究所モデルから脱却し、新たなイノベーションを
――1980年代から中央研究所が研究開発における競争力の源泉になった時代が続きましたが、現在ではオープンイノベーションへと変化しています。こうした時代を経てこられたご経歴、いまの状況について教えてください。
長我部 私が日立の中央研究所に入社したのは、バブル崩壊の約10年前の1980年で、まさに中央研究所の時代でした。半導体メモリの基本特許を取る人が数多くいて、大学よりレベルが高い基礎研究も中央研究所で手がけていました。実は、1980年以前にもオープンイノベーションはありました。企業より大学に人材が揃っていたので、中央研究所長を東京大学から招き、私が長年携わってきた電子顕微鏡の研究開発や事業も、スタートは産学連携によるものでした。
電子顕微鏡の発明はドイツだったものの、戦前にいち早く東京大学生産技術研究所の瀬藤象二先生が、東芝や島津製作所、弊社のエンジニア、電子顕微鏡のユーザーとなる医学部の教官などを集めてオープンイノベーションの場を作り、各社が輸出産業に育てました。企業が大学の人材のリードで研究してきた時代から、何でも自分たちでやる時代を経て、やがて1989年にバブルが弾けて転換期を迎えます。
私は入社以来20年間研究者でしたが、2001年に、基礎研究所所長、2011年には中央研究所所長を命じられました。その間の7年半は基礎研究、次の2年半は半導体とライフサイエンス、さらに3年半は中央研究所長と、研究マネジメントに関わったのは10年超です。イノベーションモデルが変化する中で、自分たちのイノベーションをどう起こすのかを模索していました。当時日立では半導体、ディスプレイ、ハードディスクドライブなど様々なデバイス事業のポートフォリオ変革をしており、研究所の構成も変化していく、そんな時代に私は研究所マネジメントに携わっていました。
その後、2014年に事業規模約2,000億円のヘルスケア事業部に異動し、3年半は事業戦略と技術戦略を兼任しました。その後、自動車、家電とヘルスケア事業から構成されるライフセクターで約2年、CSOとして事業戦略に携わってきました。
――産学連携のあり方はどのように変化していったのでしょうか。
長我部 アカデミア主導での産学連携は、前述した電子顕微鏡がその好例です。また、イノベーションの方法論を試行錯誤していた70年代から80年代の成功例は、超LSI技術研究組合で半導体の製造装置や検査装置といった周辺産業がつくれたことです。しかし、その後の産学連携は苦戦をしてきたように思います。以前の産学連携は、例えば瀬藤先生の強い指揮の下、東芝も島津も日立もデータを共有してオープンイノベーションを実現させました。その後はアンダーワンルーフというコンセプトであっても企業間には壁があり、他社の情報には触れる事ができないよう大学に要求した上で進められる事が多かったように思います。大学対企業の関係は構築できても、企業間ではできなかった時代が続きました。
一方、企業が外の力を入れるという意味では、弊社は2000年にCVC(Corporate Venture Capital)をスタートさせ、また社外の人材も獲得して研究所中心にライフサイエンス推進事業部を設立しました。これらは軌道にのるまでには至らなったのですが、新しいイノベーションモデルへのチャレンジであり、こうしたチャレンジの上にたって、色々なパートナリングによるイノベーションの創出が定着し始めたと思います。例えばイノベーションの中にデザインシンキングを導入し、エスノグラフィ(行動観察調査)やビジョンデザイン「25のきざし」といったツールを作り、顧客とのコラボでイノベーションを起こす仕掛けもつくりました。
また、最近になって再度ミュンヘンに本拠地を置くCVCもスタートさせています。投資回収性と自社の戦略との整合性を両立するスタートアップを目利きして探し出し、投資をする事によって連携を深め事業モデルや技術の可能性を検証しています。また、他社連携としてはJVをつくるなど、企業間コラボは増えてきました。
サイエンティフィックな発見を掴んで新たな市場を拓く
――ライフサイエンスの世界でいうと、例えばアストラゼネカのコロナワクチンは大学と企業の1対1の関係の中であっという間にできたものです。いま、大学との1対1の関係はどのようになっていますか。
長我部 1980年代までは、基本的に企業と大学の研究室と1対1で技術開発が進められました。そこから包括連携の動きが始まって、私たちは北海道大学を皮切りに10以上の大学と包括連携を進めました。最近はさらにR&Dが進化して、東京大学、京都大学、北海道大学とは自社のラボを大学において、それぞれ大きなテーマを決めて共同研究を進めています。
ライフサイエンスはアカデミアのポジションが他領域と比べて独自です。アカデミアが持つ病院がマーケットそのもので、企業より大学の方がニーズを把握しています。新発見が生まれる可能性が高く、サイエンス発展の成長率が高いことなどから、発明がそのまま商品に結びつく事も多いです。例えば抗体医薬も組み替えタンパク製剤も約10年でサイエンティフィックな発見から市場へと展開されており、例えばデバイスの世界と比べるとラボ・トゥ・マーケットが早いと思います。
――医工連携で臨床現場の声からイノベーションを起こそうとしていますが、出てくるアンメットニーズは医師と患者にとっての2種類あります。また、マーケットも大小ありますが、それをどうやって事業に展開していけばいいでしょうか。
長我部 医工連携の成功例として、LINK-Jのシンポジウムにも登壇した朝日インテックのカテーテルガイドワイヤーが挙げられます。カテーテル治療の第一人者の医師から、「CTO(慢性完全閉塞)を治療できるガイドワイヤーを作れないか」と、金属材料の得意な朝日インテックに声がかかり、その要求に応える事によって医療機器を手がけたことがない素材系の企業から画期的な医療機器が創出されました。臨床現場の医師のもつニーズには、初期に推定できる市場規模の小さいものから大きいものまで多々あります。大企業はそれなりの市場規模が期待できる事業でなければ開発に踏み出しにくいものです。スタートアップやライフサイエンス分野に進出したいと考えている特長のある技術をもつ企業に、こうしたニーズが伝われば、事業化され大きく育つ可能性があると思います。アカデミアからのニーズをもっとオープンにしたら、医師のアンメットニーズが充足されるのではないかと考えています。
ライフサイエンスの世界で勝つためのポイントは、サイエンスの最前線とどう向き合うかは大きいと思います。島津製作所は、国立がん研究センターをはじめサイエンスや臨床現場にラボを置いています。また、ジョンソン・エンド・ジョンソンは自社にインキュベーションラボを構築してスタートアップを呼び込んでいます。武田薬品工業の湘南アイパークも同様です。こうしたライフサイエンスの現場に拠点をもつ、或いは最先端の試みを自社に引き込むといった行動をしていかないと、ライフサイエンスの先端をキャッチアップできないと感じています。
世界で始まっているデータ活用ビジネス
――ゲノムやオミックスなどの大きなデータを解析してサイエンスの発見につなげ、プレシジョンメディシンを叶えるという仮説の下、様々なプレーヤーが取り組んでいます。さらにデータを中心とした新たな産業の創出など、御社で培った総合力が活かされると思いますが、いかがでしょうか。
長我部 そこはまさに日立の一丁目一番地で、「デジタル×OT(Operational Technology)×プロダクト」、各業種の現場の知識にプロダクトとデジタルを掛け合わせ、お客様や社会に価値をご提供することは大きな目的です。
データ蓄積とその解析については、病院や検査センター、製薬会社のデータが使えれば、過去の類似症例や疾患状況、個人の病歴などのデータから、最適な治療計画を導き出す事が期待されます。ゲノムやオミックスの情報に加え、金融機関も一緒に入っていれば、患者にとって最適な保険設計までできる可能性があります。期待はふくらみますが、問題は個人情報保護の観点で、社会的なコンセンサスやデータ・セキュリティの担保など条件が整う事が必要です。日本でもデータ利活用の様々な取り組みが始まっていますが、米国ではすでに企業が病院からデータを取得して分析し、保険者や病院に最適治療パスを推奨するビジネスが成立しています。また、北欧ではデータを活用し、デジタル技術を使って先端的な医療システムを実現しようとしている国もあります。
また、創薬のプロセスでも、これまで蓄積されたデータ、今後生み出されるデータを活用する事により圧倒的な開発期間短縮やコストの削減が図れるという期待があります。材料の開発においてもシミュレーションや過去の実験データから必要とされる特性をもつ材料の探索がなされるようになってきました。こうした技術はリード化合物の最適化にも適用が可能だと思います。各企業が持っているが使っていないデータを集約できるような仕組みを工夫して、機械学習などにより効率的な創薬ができるようになるかもしれません。
画像診断でもAIによる読影の自動化は盛んにチャレンジされています。米国企業のEnvoyはマーケットプレイスをつくり、様々なAIツールを扱う会社がアプリケーションを供出して、ユーザーが選択して使える、そんなモデルができつつあります。こうしたマーケットプレイスは、地域を越えて一気に広がっていく可能性を秘めています。

本質的な好奇心に基づく研究をどれだけ育てられるか
――産学連携では大学発のスタートアップが注目されています。大学は研究と教育に加え、ベンチャー創出が新たな使命となっています。このような動きをどう御覧になっていますか。
長我部 私は大学の基礎研究に注目しています。キュリオシティ・ドリブン(curiosity driven)と呼んで良いのか、真理を探究する研究があってこそ生まれるものがあります。例えばゲノム編集のCRISPR-Cas9も、細菌の免疫システムの研究から発見されたものです。物事の本質の解明をめざす基礎研究は、新たな可能性を産むものであり、大学はそれを行う機関だとは思います。ただ、大学運営交付金が減少する中で基礎研究を育てるには、基礎研究の成果を使って果敢に社会実装をめざすスタートアップを創出して資金を集めてチャレンジする事が必要です。それにはVCなど環境整備が大事です。
ただし、スタートアップの有効性は分野によって多少異なるのではないでしょうか。複合技術や融合によって構成される分野では難しいですが、ライフサイエンス分野であればスタートアップの存在は非常に重要だと思います。
――博士や研究職といった人たちの人材開発について、お考えをお聞かせください。
長我部 学位取得の過程で得たテクノロジーやサイエンスは陳腐化するものです。しかし自立して研究をできることが学位の定義であり、その人にとって最も重要な価値です。何が課題かを自ら捉え、仮説を立てて検証法を考え、その検証をみんなにわかる形で公表する。そして次の新たな課題、残された課題が何かを表明する能力です。これはマネジメントにも使えるし、研究力そのものがどんな仕事でもできる"よすが"となるでしょう。昔は企業が学位取得者を嫌うという話もあったようですが、いまは企業も学位取得者への見方は変わりました。それは方法論としての強みを持った人間だからです。
人材の流動化で新たなチャレンジを
――10年経つと、一度スタートアップを経験した人が二度目、三度目の周期に入り、起業の際にその人材が入ってくると言われていますが、いかがでしょうか。
長我部 実態は把握できていませんが、そうした拡大再生産の流れは感じます。企業でもスタートアップを近くで見る人が増え、ある程度、経営のリテラシーをもつ人材はいるので、スタートアップを経営した人の拡大生産と、その周りにいる人たちを合わせれば、結構起業に必要な経営人材を供給できるかもしれません。
今後は人材の流動化が進みます。弊社もメンバーシップ型からジョブ型に移行するために職務内容を明確にしています。これまでのような一律の初任給ではなく、対象者の技能、経験及び職務の内容などを考慮した、個別の処遇設定を行う事が可能になっています。そうなると企業間を動く人も増えてくると思います。ドクターコースの進学率が低いのは、採用する企業がインセンティブをつけないからだと大学から指摘されますが、ジョブ型になれば、これも変わってくるのではないでしょうか。

イノベーションを目指す人をエンカレッジする社会へ
――イノベーションを起こすために必要なこと、あるいはエコシステムを構築していく中で、何が重要でしょうか。
長我部 最も重要なのは人材です。そして人材が効果的に活躍するためには流動性が不可欠で、企業に所属していても、スタートアップの経営を助け、パートタイムなどで仕事をする仕組みが生まれてくるのではないでしょうか。流動化を含めた組織マネジメントと、その上でのインセンティブ設計が求められます。さらに重要なのは、イノベーションを目指す人をエンカレッジする社会の風潮です。
大学発ベンチャーも鍵となるイノベーション創出モデルですがCEOやCFOといったマネジメント人材が重要です。VCもマネジメントがきちんとしていないと投資できないので、ガバニングボードに入るなどして注視しています。今後は経営人材とスタートアップのアイデアを持った人をどうマッチングして、アカデミアのシーズやポテンシャルを活かすのかが課題だと思います。
投資の仕組みの整備も重要です。バブル以降、特に日本が遅れたのはスタートアップ投資の仕組みです。バブルが弾けた1989年頃、米国と日本のVCの総額はほぼ同じでした。ところが30年経って、日本のVCは大きく増える事がなく、米国は2桁以上も伸びて差が出ています。近年、ようやくVCが立ち上がってきましたが、イノベーションを起こす上で投資の仕掛けは最も重要です。
懸念は、基礎研究です。国の競争的資金もアウトカム志向になってきて、こうした社会的価値や経済的価値が生まれるから、このテーマをやるという形でなければ採択されません。アイデアの多様性やシーズを増やすための基礎研究への投資をどう確保するか、国か各大学の努力なのか、ここをどう守るかは重要なポイントです。
――最後にLINK-Jに期待することがありましたら、お聞かせください。
長我部 エコシステムの形成はある種組み合わせ問題なので、マッチングで可能性を広げられるかどうかが鍵です。最近のデジタル技術で最も事業が伸びているのは、需給マッチングビジネスモデルです。そこでLINK-Jに望むのは、日本橋の魅力を高めて組み合わせの接点を増やすと同時に、そこにデジタルを絡ませ、一定の地域からネットワークを広げて可能性を高めていただくことです。シーズを持ったアカデミアの人と経営能力を持った人、投資家とスタートアップ、人と人、組織と組織の交点を効果的に設計し、地域とネットワークにつくり込んでいくかに最も期待しています。また、ライフサイエンスのスタートアップを見ていると、金融から来た人が興している会社が多いことに気づきます。金融とテクノロジーと経営能力に対して共鳴や共感、パッションを生み、必要要素を集めていかに盛り上げてその気にさせるか。LINK-Jの仕掛けの中で、多少失敗しても構わないからチャレンジする人が増えることを望んでいます。
 長我部 信行 氏 株式会社日立製作所 ライフ事業統括本部CSO兼 企画本部長
長我部 信行 氏 株式会社日立製作所 ライフ事業統括本部CSO兼 企画本部長1955年生まれ。1980年 東京工業大学大学院理工学研究科物理学専攻修士課程修了後、日立製作所中央研究所入社。1997~1998年 東京工業大学総合理工学研究科客員助教授、1998年 ~2001年 同大学院理工学研究科物性物理学専攻最先端物性物理学講座客員教授を兼務。2000年 基礎研究所主管研究員、2001年 基礎研究所所長、20011年 中央研究所所長、2014年 ヘルスケア社CTOなどを経て、2016年より現職。博士(理学)。
一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム(FIRM)副会長、公益社団法人応用物理学会監事。経済産業省 日本工業標準調査会 知的基盤整備特別委員会、文部科学省第9期科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会、文部科学省第9期科学技術・学術審議会 基礎基盤研究部会などの各委員を務める。応用物理学会賞論文賞(日本応用物理学会)、論文賞(日本電子顕微鏡学会)、瀬藤賞(日本顕微鏡学会)受賞。日本工学アカデミー会員、日本物理学。