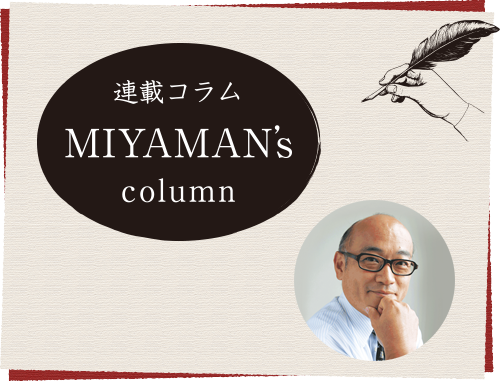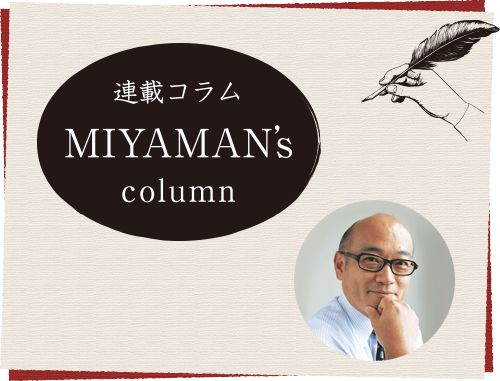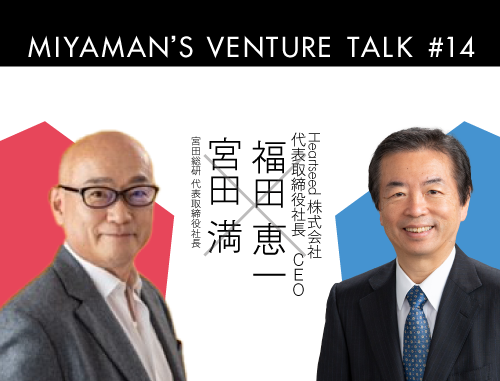上場維持基準の厳格化が招く“成長の逆風”
東京証券取引所が今年6月を目処に、ベンチャー企業の上場基準改正に動いています。2025年4月22日に市場改革に向けた有識者会議を開催し、「上場後5年で時価総額100億円」が可能である企業がグロースへの上場維持を許されるという新基準案が提示されました。今後、パブリックコメントを経て、正式な上場基準となる見込みです。
驚くべきことに現在上場しているバイオ・ベンチャー企業45社を新基準案で評価すると、6割以上のバイオ・ベンチャー企業は、本来なら上場維持を許されないという結果になりました。他業種では7割も新基準を満たさないので、バイオはまだましという意見もあります。しかし、バイオも含むベンチャー企業の上場維持のハードルが上がったことは間違いありません。今後、新上場維持基準が適用されるようになれば、上場後の成長に対する評価も厳しくなることは避けられないでしょう。
東証がグロース市場を改革したいという気持ちはよく分かります。本来、東証グロース市場は成長性の高い企業の資金調達の場でありました。しかし、現状は小粒株が多いため、デイトレーダーの遊び場と化してしまっています。少なくとも時価総額100億円から300億円の企業でなくては、潤沢な資金を長期に投入しうる機関投資家の対象にならないためです。流通株式数が少なく、まとまった株式を購入することも難しく、しかも大量購入しようとするとそれだけで株価が高騰してしまい、投資利益を損ないます。東京証券取引所の機関投資家を対象にしたアンケートでも、機関投資家から時価総額100億円以上の企業ではないと投資できないという悲鳴が聞こえてきます。できれば300億円から500億円というのが本音です。欧米では1000億円以上が機関投資家の投資対象となっています。ずいぶん昔ですが、米Genentech社の創始者であるBob Swanson社長(当時)が来日した時、「やっと時価総額10億ドルに達した。これで機関投資家の資金が入る」と喜んでいた記憶が蘇ってきました。
しかしそれでは、上場時見込み時価総額まで企業価値を膨らますために、バイオ・ベンチャーに出資される資金源は何処にあるのか?その手当も考え、上場維持基準を考えなくては、東京証券取引所グロースに上場する企業が減少、あるいは十分体力をつけたバイオ・ベンチャーが、東証より上場審査が面倒臭くない米国の新興市場NASDAQに流出する可能性もあるのです。証券市場の都合だけを優先すると、やがてバイオ・ベンチャー創出の井戸が枯れるリスクを考えなくてはなりません。ベンチャー振興のためには部分最適よりも我が国の金融市場の全体最適が必要です。これこそ政府の役割なのです。
 宮田 満 氏
宮田 満 氏 東京大学理学系大学院植物学修士課程修了後、1979年に 日本経済新聞社入社。日経メディカル編集部を経て、日経バ イオテク創刊に携わる。1985年に日経バイオテク編集長 に就任し、2015年に株式会社宮田総研を設立、新Mmの憂 鬱などメディア活動を開始。2017年、株式会社ヘルスケアイノベーションを設立、2020年6月よりバイオ・先端医療関 連のベンチャー企業に投資を開始した。厚生労働省厚生科 学審議会、文部科学省科学技術・学術審議会、生物系特定 産業技術研究支援センターなど、様々な公的活動に従事。