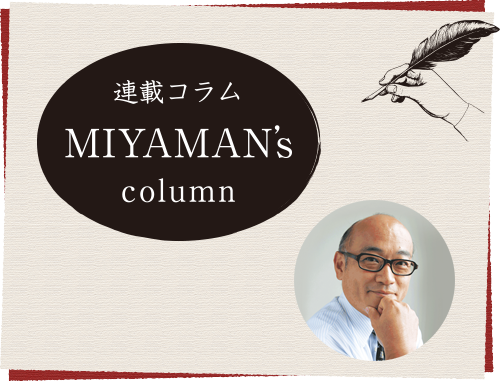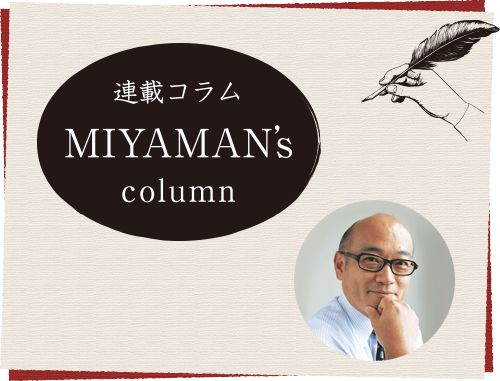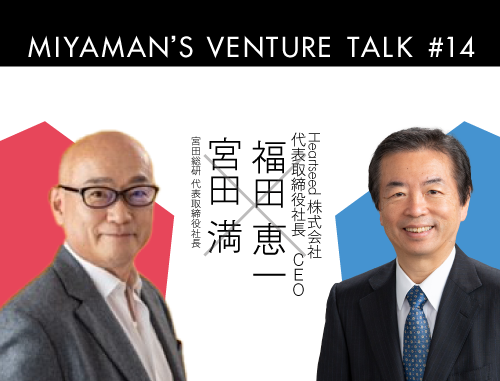政府は腹を据え支援を、中途半端な支援はありがた迷惑
今年は巨額な補正予算が計上されたため、政府のバイオや生命科学に対する補助金が期待できる状況だ。政府も創薬ベンチャーの支援にも力を入れることを政策として掲げている。
しかし、本当に来年度の予算にも期待できるのだろうか?従来の政治状況との最大の差は自民党・公明党が少数与党であるという点だ。野党の少なくとも一会派を味方につけなくては本予算が議会を通らない。そこで今起こっているのが、野党が政府の予算案に賛成するための条件闘争である。国民民主党の103万円の壁から始まった議論は、維新の会の公立・私立を問わない高校無償化に拡大しつつある。表現は悪いが、今年の夏の参議院選挙をにらみ、与野党は成果を上げるため目前の予算を奪い合いあっている。そこには一貫した政策というものが見えない。いつ前言が翻るかもわからない状況だ。実際、高額医療費の増額に関しても、厚労省の提示した案は患者団体などの動きによりたった2週間で、修正を迫られた。従来のように政府は自民党に根回しすれば、予算が確定するという安易な、しかし安定性のある予算策定はもうできなくなったと言えるだろう。暫くはあらゆる政策で右往左往が続きそうだ。民意が反映される良い面もあるが、票獲得のための人気取りによって、国が進むべき道が歪むリスクも高い。
こうした状況を解った上で、敢えてバイオや創薬支援の来年度予算に要求を突きつけるとすると、あまりに助成や補助額が中途半端であることである。AMEDの新薬開発の予算はバイオベンチャーにとってまことにありがたい予算であるが、国が積極的にリスクを取るというならば、非臨床試験やフェーズ2Aまでの治験をそれぞれ完了するに足る予算を出すべきだと思う。補助率や助成額が中途半端であるため、アカデミアもベンチャーもそれぞれ安心して新薬開発に取り組めない。常に不足分の資金調達を進める必要がある。
政府のリスクマネーが潤沢に供給されれば、その資金で進めた成果や知財を基に、ベンチャー・キャピタルや事業会社からの資金調達やライセンスが起こる好循環が起こる。八方美人の中途半端な資金のばら撒きではなく、選別集中投資こそが必要だ。
そのために、採択件数が絞られても良いと今腹を括るべきなのだ。当然、審査委員の能力も問われることになる。
 宮田 満 氏
宮田 満 氏 東京大学理学系大学院植物学修士課程修了後、1979年に 日本経済新聞社入社。日経メディカル編集部を経て、日経バ イオテク創刊に携わる。1985年に日経バイオテク編集長 に就任し、2015年に株式会社宮田総研を設立、新Mmの憂 鬱などメディア活動を開始。2017年、株式会社ヘルスケアイノベーションを設立、2020年6月よりバイオ・先端医療関 連のベンチャー企業に投資を開始した。厚生労働省厚生科 学審議会、文部科学省科学技術・学術審議会、生物系特定 産業技術研究支援センターなど、様々な公的活動に従事。