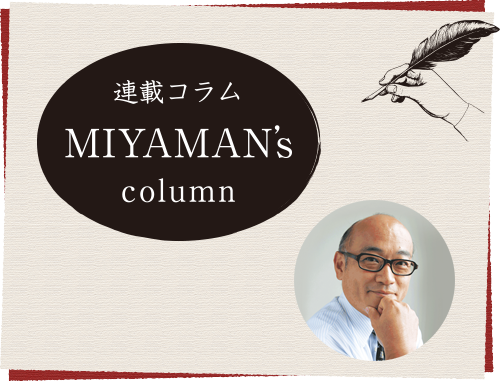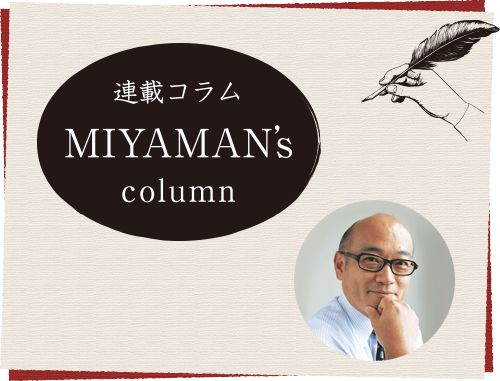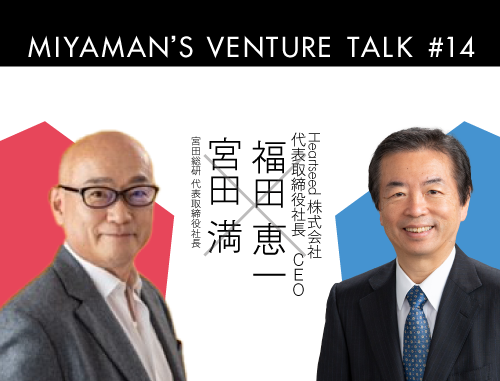起業はまず教授の言葉を疑うことから始めよ
最近、衝撃的なことがあった。
Nature誌など一流学術雑誌に論文を多数発表している某旧帝国大学の教授から「有望な新薬の標的を発見した。これに対する抗体や核酸医薬を開発できれば、今まで治療法の無い疾患の画期的新薬となる。ただし、特許を引き受ける会社が手を上げないと、大学が出願しない。出願費用もすべて負担する企業が無いと権利を確保できない」という相談を受けた。話を聞くと、確かに最新の免疫学の研究成果のようだ。大学の知財関係者も期待していると聞き、半分は義侠心、半分は患者さんのためという想い、収益機会への期待もあり、私は大学と共同出願する特許関連費用を負担することを決めた。ベンチャー・キャピタルの定款を変更してまで特許化に踏み切った。
導出先のバイオ・ベンチャー企業まで決めていたのだが、国際特許出願(PCT出願)に移行する際に問題が発生した。出願国などを決める際、権利侵害のリスクを確認するための特許調査を行ったところ、先行論文や特許が多数リストアップされた報告書を受け取った。対策や追加実験などを検討したものの、万策尽きて、共同出願の権利を放棄した。費用を削減できた大学は喜んで特許を引き取ったようだが、多分、あの内容では権利化することは難しいだろう。
さらに驚いたのは、教授が知財担当者に相談した際、先行発明や発表の調査を行っていなかったことだ。知財の専門家であれば、科学論文に載る新知見と権利化できる特許は次元が違うことを理解しているはずだ。
調べてみると、厚労省傘下のナショナルセンターでも、ほとんど調査せずに出願しているらしい。製薬企業は自前で特許調査をするが、教授頼みのベンチャーがこの事実を知らないことが多い。
バイオは「知財のゲーム」と言われる。知財に瑕疵があれば勝利は覚束ない。研究機関や大学に知財を精査する資金と人材が不足しているのが原因だ。アカデミア発のベンチャー起業を語るなら、知財力の強化が不可欠。私の反省としては、教授の「世界初」を疑い、費用を投入してでも、シーズ段階で徹底的に特許調査を行うことにした。投資家の皆さんにも、お勧めしたい。
 宮田 満 氏
宮田 満 氏 東京大学理学系大学院植物学修士課程修了後、1979年に 日本経済新聞社入社。日経メディカル編集部を経て、日経バ イオテク創刊に携わる。1985年に日経バイオテク編集長 に就任し、2015年に株式会社宮田総研を設立、新Mmの憂 鬱などメディア活動を開始。2017年、株式会社ヘルスケアイノベーションを設立、2020年6月よりバイオ・先端医療関 連のベンチャー企業に投資を開始した。厚生労働省厚生科 学審議会、文部科学省科学技術・学術審議会、生物系特定 産業技術研究支援センターなど、様々な公的活動に従事。