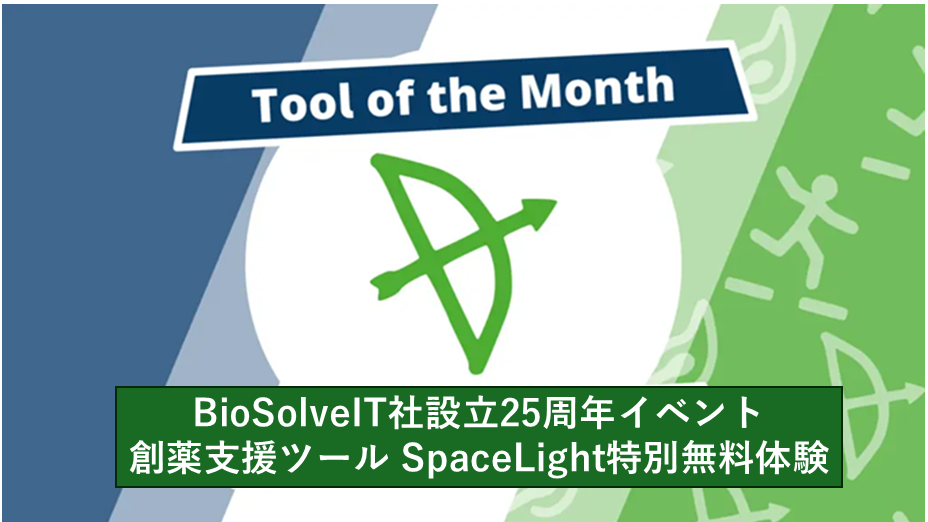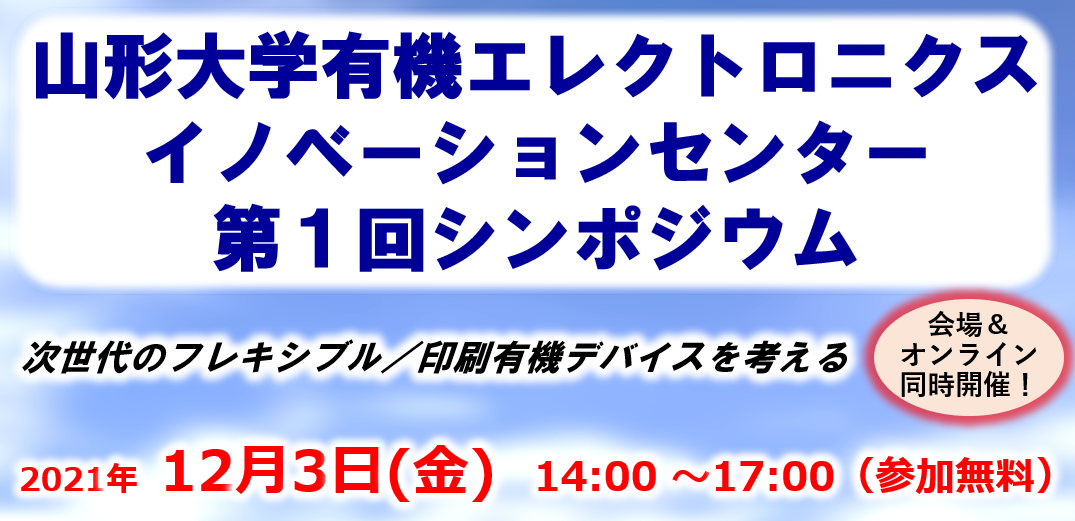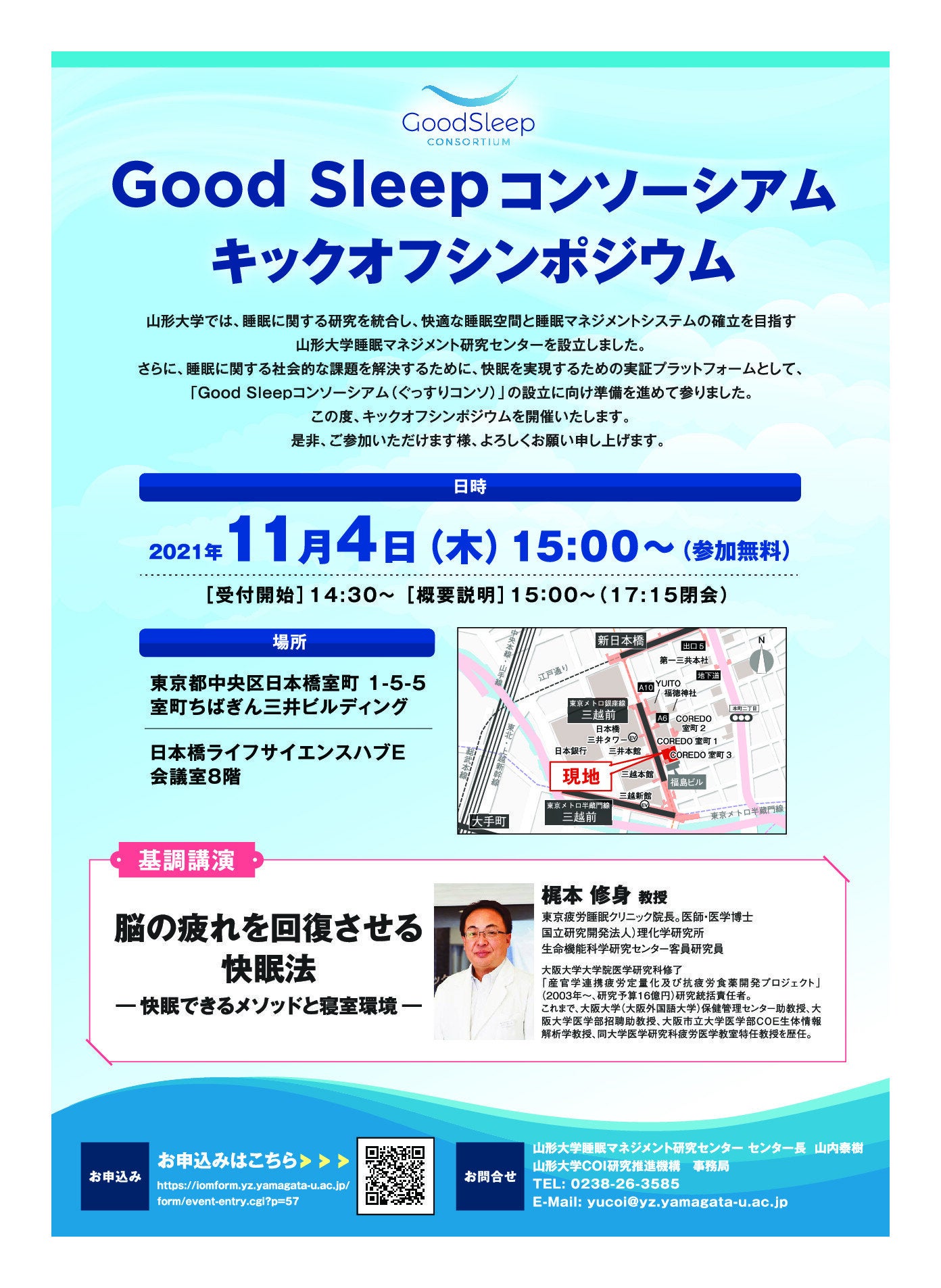2025年7月3日(木)、山梨大学とLINK-J共催で「大村イズムの継承と天然物由来創薬の挑戦 「フロウティラ創薬研究における天然資源の新展開」 山梨大学・北里大学連携研究の新形態」をハイブリッドにて開催しました。
当日は現地参加・オンライン合わせて、153名の方にご参加頂きました。
主催:一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン(LINK-J)、山梨大学
LINK-JのYouTubeチャンネルでアーカイブ動画を公開しています。(一部編集をおこなっております。)
【登壇者】
黒澤 尋 氏(山梨大学理事)
廣瀬 友靖 氏(北里大学 大村智記念研究所 教授)
山村 英樹 氏(山梨大学生命環境学部生命工学科 教授)
阿部 章夫 氏(北里大学 大村智記念研究所 所長 教授)
鈴木 堅太郎 氏(山梨大学 生命環境学部 教授)
中尾 篤人(山梨大学医学部免疫学講座 教授)
花木 秀明 氏(北里大学 大村智記念研究所 特任教授 / 山梨大学 大村記念微生物資源研究フロウティラ 特任教授)
Opening Remarks
本シンポジウムの位置づけ
曽山 明彦(LINK-J常務理事)
本シンポジウムの趣旨・フロウティラ紹介
黒澤 尋 氏(山梨大学理事)
第一部:天然物化合物ライブラリーの創薬研究への活用について
『AMED・BINDS事業における大村天然物ライブラリーの活用』
廣瀬 友靖 氏(北里大学 大村智記念研究所 教授)
【講演要旨】
北里大学大村智記念研究所では多種多様な微生物ライブラリーを基盤に、その培養液から低分子~中分子までカバーする非常に多様性に富んだ天然物を取得し、それらを「大村天然化合物ライブラリー」として管理している。そしてAMED BINDS事業ではそのライブラリーを外部研究機関が有する優れた評価系へ供給することで創薬シード探索を展開している。本シンポジウムではその取り組みについて紹介させていただきたい。
『希少放線菌ライブラリーの活用』
山村 英樹 氏(山梨大学生命環境学部生命工学科 教授)
【講演要旨】
希少放線菌は土壌中の放線菌の僅か数パーセントしか存在しないため、これまで創薬資源として十分にスクリーニングされてこなかった。そこで本研究室ではこの希少放線菌を創薬資源として活用すべく、土壌などの試料から希少放線菌の選択分離法の開発を行ってきた。今回、非常に高い割合かつ多数の新種相当の希少放線菌を選択的に分離する画期的な方法を開発することに成功した。その方法は希少放線菌の中でも特に希少性が高い運動性放線菌をターゲットとしており、ろ紙の細孔に運動性放線菌を誘い込ませる非常に簡便な方法である。この方法ではActinoplanes属が最も多く分離されており、これまでに500株以上を保全し、その数は日本最大級である。この他の選択分離法や希少サンプルから分離された希少放線菌と合わせて山梨大学では希少放線菌ライブラリーを構築し充実を図り、スクリーニングソースの整備を行っている。
第二部:天然物化合物の新たな創薬への取組み
『多剤耐性菌の解析最前線: 人類の存続をかけた挑戦』
阿部 章夫 氏(北里大学 大村智記念研究所 所長 教授)
【講演要旨】
病原細菌の多くは、生体内の環境変化に応じて多様な遺伝子を発現することで、宿主内での生存能力を獲得している。こうした遺伝子発現の多くは二成分制御系によって制御されており、大腸菌では、センサーキナーゼ30個、レスポンスレギュレーター32個の計62個の関連遺伝子が存在することが知られている。近年、二成分制御系が抗菌薬曝露時の細菌の恒常性維持において重要な役割を果たしていることが、数多くの研究により報告されている。しかしながら、薬剤耐性獲得において、どの二成分制御系が特に重要であるのかについては、未だ明確な知見が得られていない。そこで我々は、抗菌薬曝露に関与すると考えられる二成分制御系に注目し、その各種欠損株を用いて最小発育阻止濃度(MIC)の測定による評価を実施した。その結果、CpxA-CpxR系の欠損によってカルバペネム系抗菌薬に対する耐性が有意に低下することを見出した。現在、このシグナル伝達経路を標的とする阻害化合物の取得を目的としたスクリーニング系を構築している。
カルバペネムは「最後の切り札」とも称される抗菌薬であるが、すでに耐性菌の出現が深刻な問題となっている。とりわけ、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)は、薬剤耐性プラスミドを保有し、複数のプラスミドを取り込むことで多剤耐性化を進化させており、多くの抗菌薬が無効となる事態を招いている。さらに、抗菌薬による強い選択圧は、耐性菌の出現を促進する要因ともなっている。製薬企業が抗菌薬開発から相次いで撤退するなか、新たな創薬標的を見出し、困難な状況下でも挑戦を続けることは、アカデミアに課された重要な使命であると考えている。
『微生物由来天然化合物を基盤とした疼痛創薬研究』
鈴木 堅太郎 氏(山梨大学 生命環境学部 教授)
【講演要旨】
慢性疼痛はQOLを著しく低下させ、国内で年間約2兆円の経済的損失をもたらすと推計されており、深刻な社会課題である。加えて、女性に有病率が高いことから、性差疾患としての重要性も指摘されている。近年、脊髄ミクログリアの過剰な活性化が慢性疼痛の発症に深く関与することが明らかとなり、その制御は新たな治療戦略として期待されている。本研究では、北里大学及び山梨大学が保有する微生物由来天然化合物ライブラリーを基盤にスクリーニングを行い、組織・動物レベルでの評価を通じて、ミクログリア活性を制する天然化合物を同定する。我々は、本アプローチにより慢性疼痛の病態の理解を深め、新規疼痛治療薬の開発を目指す。
『アレルギー疾患の予防や治療における天然成分のポテンシャル』
中尾 篤人 氏(山梨大学医学部免疫学講座 教授)
Closing Remarks
花木 秀明 氏(北里大学 大村智記念研究所 特任教授/ 山梨大学 大村記念微生物資源研究フロウティラ 特任教授)
イベント後のネットワーキング・レセプション会場は非常に盛り上がりました。
皆様、登壇者をはじめとした多くの方とお話をされており、活発なネットワーキングが行われました。
参加頂いた皆様からは「フロウティラにおける創薬の展開がよく分かり非常に勉強になりました。」「山梨大学、北里大学の強みを存分に活かされていて天然物の力、それぞれの大学の力を感じた」「大村天然化合物ライブラリーや希少放線菌ライブラリーの構築・活用は、低分子・中分子創薬における新たなシーズ探索の可能性を強く感じさせる内容でした。」と多くの感想が寄せられました。
最後に、登壇の皆様と記念撮影を行いました。
ご参加頂いた皆様有難うございました。