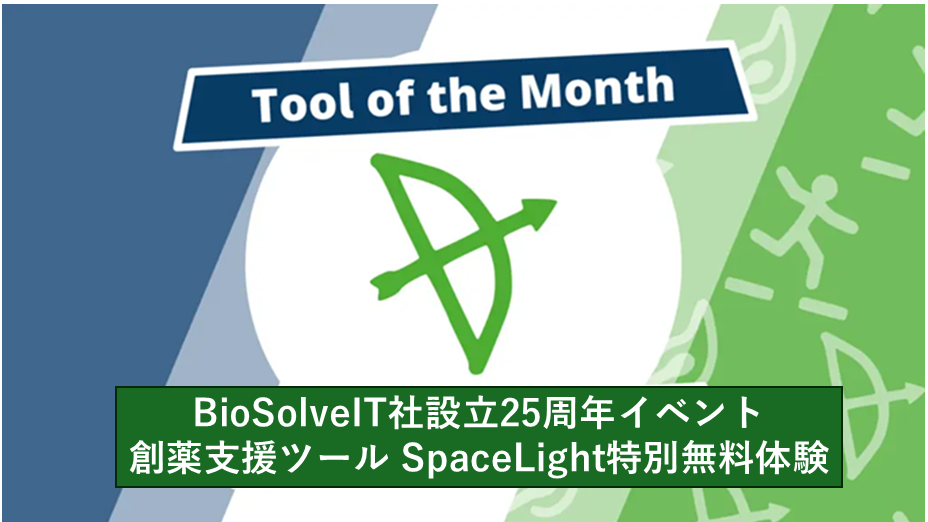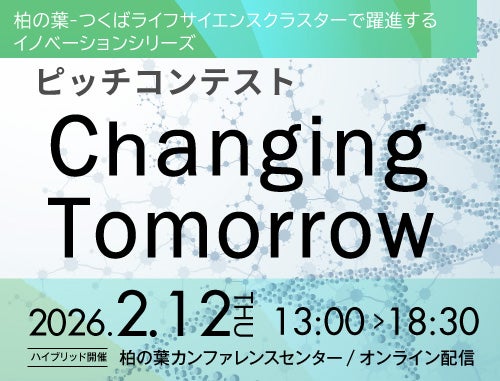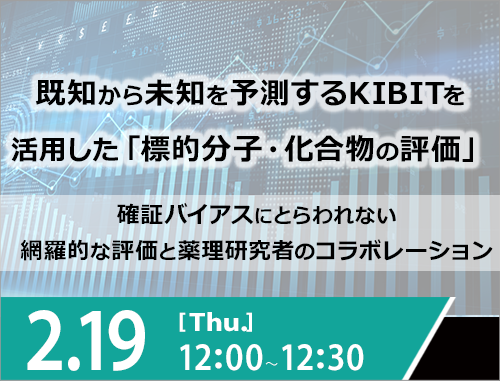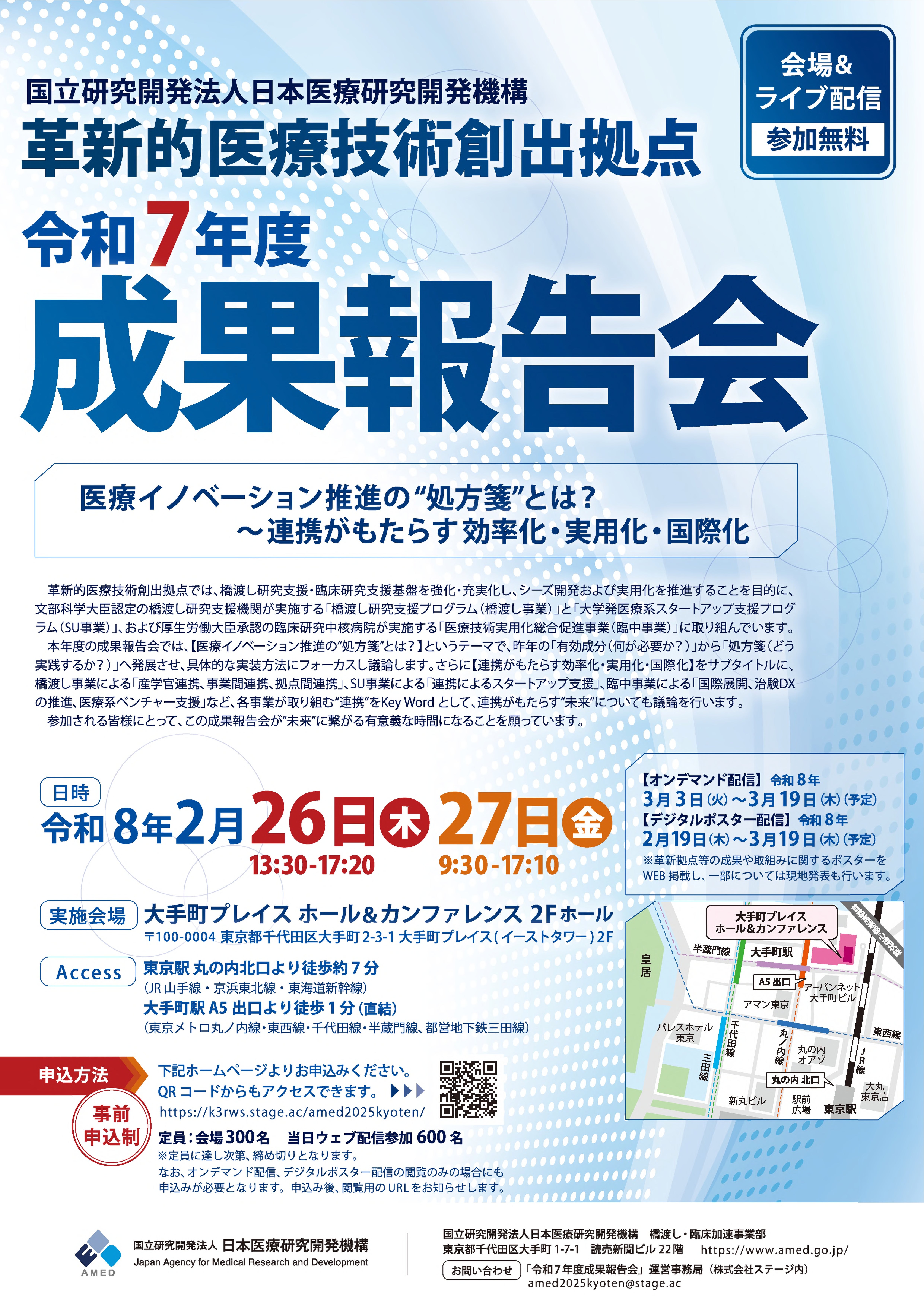この投稿記事は、LINK-J特別会員様向けに発行しているニュースレターvol.27のインタビュー記事を掲載しております。
この投稿記事は、LINK-J特別会員様向けに発行しているニュースレターvol.27のインタビュー記事を掲載しております。
☜PDFダウンロードはこちらから
今回のインタビューは、米国でPI(Principal Investigator:主任研究者)として独立され、現在は日本にも研究室を持ち、日米のアカデミックシステムの違いをよく知るお二人をお招きしました。お一方は、東京大学発バイオベンチャー「ペプチドリーム」と「ミラバイオロジクス」の創業者で、現在、総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)の議員として大学改革の司令塔を務める東京大学教授・菅裕明博士。もうお一方は31歳という若さで大学教授に就任し、「ミニ肝臓」の作成者である武部貴則博士。日本の科学研究活動の国際的地位の低下が懸念される中、競争力を高めるために必要な次世代研究者の育成と、整えるべき研究環境についてお話を伺いました。
研究に対峙できるよう、若手研究者の経済基盤の確立を
武部 菅先生、ご無沙汰しております。久しぶりに対面でお会いでき、少々緊張しています(笑)。
菅 対面でお会いするのは科学技術振興機構の支援プログラム「さきがけ」以来だから、もう10年以上経ちますね。
武部 菅先生にメンターしていただいた「さきがけ」は、僕のキャリアにとって大きなターニングポイントの一つでした。あれ以来、研究者でありながら起業も手掛ける先生の活躍ぶりを拝見していましたので、今日お話できるのを楽しみにしてきました。
――本日は「研究者の育成・能力向上のため、ひいては日本の科学研究の質を高めるため、今、整えるべき研究環境」というテーマでお話を伺いたいのですが、まずお二方がそれぞれどのようなキャリアパスを辿ってきたのか、教えていただけますか。
武部 僕は元々、肝臓疾患の新しい治療法を生み出したいという思いがあり、横浜市立大学医学部の2年生のとき再生医療をテーマに掲げる研究室へ入りました。最初は下積みとして軟骨の再生を5年間研究し、ようやく"花形"と呼ばれる肝臓の研究をやらせてもらうことになったのは、卒業してから。その2年後にiPS細胞から立体構造の「ミニ肝臓」を作成する研究成果を発表し、注目を集めるようになりました。それが2013年のことです。その後、「さきがけ」の後押しがあってスタンフォード大学に小さなチームを作ることができ、そこでの1年間の助走を経て、28歳頃シンシナティ小児病院の研究所でPIとして独立しました。シンシナティ小児病院は研究者だけで2万人を擁する、小児病院としては世界最大規模の病院です。その後日本の大学からもオファーがあり、現在はシンシナティで12人からなる研究チームを率いながら、東京医科歯科大学と大阪大学でもiPS細胞の研究を行い、そのほか横浜市立大学ではまちづくりに関する研究も行っています。また、7社ほどスタートアップ企業の創業にも関わっています。
菅 私は岡山育ちで、高校時代は特に興味のある分野があるわけでもなく、地元・岡山大学の工学部に進学しました。ですが大学4年のときに入った有機化学の研究室が、本当に面白くて。そこから研究に没頭し始め、修士に進み、留学先のスイスで生物有機化学の領域に初めて出会って衝撃を受け、バイオの方向に目を向けることになりました。帰国後、修士を取るとすぐさま渡米して、マサチューセッツ工科大学(MIT)でPh.D.を取りました。その後、マサチューセッツ総合病院でポスドクとして自分の研究の基盤になる技術を勉強し、ニューヨーク州立大学バッファロー校でアシスタント・プロフェッサーになり、教鞭をとりつつ研究を行いました。それからテニュア(終身在職権)を獲得し、同校でアソシエイツ・プロフェッサーに。いくつかの機関からオファーがあった中で、東京大学先端科学技術研究センター(先端研)を選んで帰国し、先端研の助教授、教授を経て、2010年より東京大学大学院理学系研究科の教授に就いています。
現在、私の研究室は総勢約50人。多様な人材が集まる場にするため海外からのポスドクも積極採用しており、内15人が外国人です。ビジネスとの関連では、先端研に在籍中に東大発創薬ベンチャーのペプチドリームを創業。その後ミラバイオロジクスも創業し、現在もう一社の起業に携わっているところです。

武部 なぜ先生は米国で研究を続けず、帰国されたのですか?
菅 研究費の獲得、研究計画書の審査、そして米国での終身在職権「テニュア」の獲得と、米国でやりたかったことは、一通りやり切ったという思いがあったからです。米国の研究者はみなテニュアの獲得をめざしているのですが、私の場合はいざ獲得してみると「後は日本に帰って、日本のために仕事をしよう」という気持ちになっていました(笑)。
――武部先生は最初に米国でPIとして独立され、その後日本で大学教授になったわけですね。研究者として独立する時期としては、かなり早かったのではないですか。
武部 僕の場合、「自分のアイデアを試したい」という気持ちが強く、早く独立したいと思っていました。既存のヒエラルキーの中では自分の挑戦ができないと言いますか、予算と場所と人材が講座からサポートされている以上、当然のことながら挑戦はその講座の成果に帰属してしまうわけです。だから、独立――つまりそれまでとは違う場所で、違う予算を使って研究――したかったのです。「さきがけ」の研究者に選ばれたことをきっかけに、独立の道が早く開けました。
――日米で、次世代研究者育成のスタイルの違いはありますか。
菅 まず大きく異なるのが博士課程の大学院生の扱いです。日本では大学院生は学生という位置付けで、経済援助を親か奨学金に頼らざるを得ませんが、米国の大学院生は仕事の対価として給与が支払われます。主に大学院1年生は学部学生の実験準備や指導監督、採点など授業の手伝いをすることでTA(Teaching Assistant)の給与が大学から支払われます。また2年生以上になると、研究室の研究を遂行することでRA(Research Assistant)の給与が研究費から支払われます。TA、RAは大学や都市環境によって差はあるものの、額にして年間約2万~4万ドル程度。アルバイトせずに生活できる程度の額が支給されるため、研究にしっかり時間を費やせる恵まれた環境と言えます。私が今主宰している東大の研究室ではこの米国式を取り入れ、博士には給与を、修士にもアルバイトをしなくて済む程度の謝金を研究費の中から支払っています。国が進めている大学改革でも博士過程の学生に対する経済支援については検討を進めており、将来的には大学ファンドを原資にした支援が行われることになるでしょう。
武部先生はシンシナティの研究室に12人を擁しているとのお話でしたが、その規模になると人件費も大変ではないですか?
武部 はい、少しダウンサイズしたいくらいです(笑)。ただ米国は研究費の規模が大きいですね。初めて自分の研究室を持ったときは、5年で1.5億ドルという余裕あるスタートアップパッケージを財団から獲得できましたし、現在もNIH(国立衛生研究所)から2件と、企業系、財団系からそれぞれ研究費を獲得し、ラボ運営をしています。
菅 日本のように大学から配分される研究費が一切ない米国では、PIが自らNIHやNSF(国立科学財団)などの連邦機関、企業、財団法人などから研究費を獲得し、その中で実験費用や自らの給与、研究室メンバーの給与を賄っていかなければなりませんからね。審査も非常に厳正です。でもこの仕組みこそが米国の研究レベルをボトムアップさせていると私はみています。外部からの競争的科学研究費を獲得できなければ研究室の存続に関わるため、PIは真剣に研究計画書を作成せざるを得ませんから。

若手育成に寄与し、研究を加速させる 米国のメンタリングシステム
――若手研究者を育成する意識にも違いがあるのでしょうか。
武部 米国には自分より階層が上の人からメンタリングを受けられるシステムがあり、これが研究者のステップアップをスムーズに導いています。例えば大学院の学生ならファカルティから、ファカルティならディレクターからといった具合です。特に大学院生は、隣のラボの教授、あえて違う領域の教授、職種の違うエンジニアなど、自分のラボの指導教授以外からも3人のメンターを自由に選ぶことができ、自分の技術の足りない部分を埋めることができます。多角的な視点からアドバイスが半年ごとに得られるため、顕著に成長します。メンター側はしっかりコミットするよう求められており、自分のラボ以外の学生の相手もしないといけないので、時間や労力を割く必要があるのですが、「君が取り組んでいるプロジェクトの課題は、うちのこの技術で解決できるんじゃないか」といった、コラボレーションが生まれるきっかけにもなります。メンタリングの仕組みは若手育成に寄与するのみならず、技術を掛け合わせ、研究を加速する一つのドライバーになっているのです。あのような研究環境を日本で作れないものかと思います。
菅 私もメンタリングの仕組みは有効だと思っており、文部科学省が「卓越大学院プログラム」を始めたときに委員の立場から提案し、一部のプログラムで導入されるようになりました。ただ、卓越大学院でメンターとして推奨されているのはまったく違う領域の教授のため、本当の意味でのメンタリングになっていないのです。やはり同じ領域で違う研究に取り組んでいる教授のメンタリングが一番効果的なはずなのですが、指導教授側に自分の学生を隣の教授に見てもらう心理的抵抗感があるため、違う領域の教授を推薦するような仕組みにしてしまったんでしょう。
武部 日本ではメンタリングに抵抗を覚える人も多いですし、「隣のラボは関係ない」という空気が少なからずありますからね。
――日本のピラミッド型の講座制が若手研究者の独立のチャンスを遅らせているという議論もありますが、これについてはどのようにお考えでしょうか?
菅 講座制は、教授が雑用を助手に押し付けてばかりだと若手研究者の芽を摘む最悪なシステムになってしまいます。逆に、知識と情報が共有された健全な共同研究が成立していれば、講座制は決して悪いシステムとは言えません。日本人の場合、ピラミッド型の中で指導を受けるメリットもあるのも事実です。というのは、助教クラスでは英語の論文を書く力がまだ100%と言い切れないことも多い。そういうとき、より経験豊富な教授からの直接のメンタリングが必要になるわけです。英語も含めてサポートしないとせっかくの研究成果がジャーナルに掲載されず業績につながらない、といった日本独特の事情を考慮すると一概に悪いとは言い切れないのです。
武部 大きな講座になると准教授、助教などミドル層の厚さが問題になることはあります。ミドル層という同じジョブレイヤーに居ながら、独立をめざす人、講座の中で教授の右腕になりたい人、進路がまだ定まらずメンタリングが必要な人などいろいろなタイプが混在し、そのようないわば"機能的多様性"を無視して一律に扱うと歪みや衝突が起こります。僕自身、日本の大学で講座を持ってみて、マネジメントの難しさを感じているところです。
菅 日本では助手や准教授のポジションが任期付きだったり、昇進が原則的にない制度を導入している大学もあります。このような不安定なポジションを存続させることは、研究の質を向上させる上で問題だと思っています。米国のようにテニュア制を導入し、着任から5、6年程度で審査を受けることが若手の研究に対するモチベーションを高めるはずです。

活路は、大学の壁を取り払うことにあり。
――武部先生から先ほど「コラボレーションが研究を加速する」というお話が出ましたが、先生が2021年12月に設立された一般社団法人「ステラ・サイエンス・ファウンデーション(SS-F)」にはそのような狙いがあるのでしょうか。
武部 その通りです。日本のアカデミアで残念だと思うのは、大学の講座という壁に阻まれ、壁を超えたコミュニティが存在しないこと。そこで信頼できるコミュニティをつくるために設立したのが、SS-Fです。活動の狙いは、優れた研究者を発掘し、創造性の高い研究に打ち込める環境をつくることにより、破壊的な発見・発明の持続的創出を図ることにあります。さまざまな視点や価値観のぶつかり合いが必要なため、世代や分野を超えた多様性あふれるコミュニティの醸成に力を入れています。例えば菅先生のような輝かしい実績のある研究者と、まだ原石のような研究者とをインタラクトさせる。そこがポイントなのです。実はSS-Fがモデルにしているのは、僕の独立時に研究費を助成してくれたニューヨーク・ステムセル・ファウンデーションです。
同財団は自分たちが資金提供した研究者を集めたコミュニティを作っており、有名なところではモデルナ創業者のデリック・ロッシ、MIT教授でゲノム編集技術の開発者のフェン・チャン、MITの生化学者・脳神経学者のエド・ボイデンなども参加しています。毎年2回、彼らと会うのがそれは刺激的で。そのコミュニティから発表された論文が毎年ネイチャーやサイエンスに多数掲載され、そこから生まれるビジネスも数知れません。尖った人、変わった人、面白い人を集めると、物事が勝手にダイナミックに動いていく。それを目の当たりにして、日本にこのやり方を持ち込もうと思ったわけです。これだけ狭い国土で物理的にも近い距離にいるので、大学の講座の壁さえ取り払って日本中から研究者を集めれば、面白いことが起きると信じています。
菅 多様な研究者で議論して、起業をめざすイメージですか?
武部 それもあります。でも起業そのものが目的というよりは、想定していないコラボレーションや、ビジネスの種を生み出すところが大きなポイントだと思っています。
菅 同感です。私が今、取り組んでいるCSTIのグローバル・スタートアップ・キャンパス構想も、閉鎖的な環境の大学をどうやって開かせるかを考えています。ところが、この面白さと重要性がなかなか理解されない。「誰と誰をどこから集めるんですか?」と言われてしまう。
武部 最初から予想できてしまうと、面白くないんですよね。
菅 そう、事務局がお膳立てしてしまっては面白くない。そうではなく共同研究のテーマを設定し公募をして、関心のある研究者を
1箇所に集めれば、絶対面白いことが起きるはずなんです。まだ構想段階なのですが、私の思いとしては、研究者にそれぞれの研究の目的と不足する知見・技術を記したプロポーザルを提出してもらった上で、共同研究を行ってもらいます。既存のラボは継続したままで構わないのですが、大学の壁を取り払った座組みを新たにつくり、共同研究者同士で議論・研究を進めてもらう。対象は日本人のみならず世界に開かれていて、世界中から優秀な研究者を集めたいですし、ビジネスユニットも噛ませて研究成果を社会実装させていきたいとも考えています。このコンセプトが理解されないのが、悩ましいところです。

――菅先生もご自身で財団を立ち上げられたとこのことですが、そちらはどのような財団なのですか?
菅 私が個人的に資金を拠出する形で研究費を助成する財団で、3年前から運営しています。特に宣伝はしてこなかったのですが、80件程度の応募が集まるくらい、知られるようになっています。目的は、将来をリードするような飛躍する科学者を見出し、人材を育て研究支援をすること。「LeaP科学財団」という名称で、LeaPには「Leading Pioneers」と「leap(飛び上がる)」の意味を掛けています。特徴的なのは審査方法で、その方法を試したいがために財団を設立したようなものです。
LeaPの審査方法とは、1次審査は研究計画書を1ページにまとめてもらい、申請者の氏名・所属は非公開で審査を行います。7人の審査員で点数を付け、1位通過の研究はそのまま2次審査へ。2位以降の研究については審査員全員で議論し、7~8件の研究を2次審査に上げます。2次審査では改めて5ページ以内の研究計画書を提出してもらい、審査員全員で議論し、投票で3人の研究者を選びます。助成金は1人あたり1000万円。科研費など公的なプロポーザルでは膨大な量の研究計画書が求められますが、LeaPの提案書では研究計画書のフォーマットもなく、端的にまとめて書いてもらう。この方法の方が、誰が見てもキラリと光る研究が見つけられると思っているんです。
武部 毎年3000万円を菅先生がご自分の資金から。すごいです。
菅 幸いベンチャーで成功したので、そのお金を運用しています。お願いした審査員の方たちはまったくのボランティアなのですが、趣旨を理解し、喜んで協力してくださっています。
武部 応募条件や研究成果の評価は、どうなっているのですか?
菅 すでに公的資金から支援を受けている研究は対象外で、求めているのは手垢のついた研究ではなく新しい研究です。1000万円は研究者が自由に使ってもらって構わず、3年後に研究発表は行ってもらいますが、失敗しても結果が出なくても構いません。LeaPは、現段階では既存のラボに対する研究費助成を行っていますが、将来的には先ほど話したような共同研究を推進するファウンデーションに育てたいと考えています。
武部 LeaPと僕らのSS-Fは根底に似た思想がありそうです。どこかで連携できたら良いですね。

サイエンスをビジネスにつなげ、日本経済の発展につなげる
――菅先生も武部先生も、起業に携わっておられます。お二方の中で、サイエンスを応用したビジネスとはどのような位置付けなのですか。
菅 私は創薬系なので、基礎研究で薬の開発につながる技術ができたときは、常にスタートアップの設立を考えます。なぜなら、研究室で直接薬を開発するという選択肢は資金面から難しいですし、製薬企業と組むという選択肢も研究室の本来の役割である論文発表ができなくなることから、あり得ません。その点、先にスタートアップを設立してビジネスの部分を研究室から分離すれば、研究室はビジネスからのバイアスが掛かることなく自由な基礎研究・学術研究を守ることができます。そしてビジネスの方は、スタートアップが製薬企業などと協業するなりして成長させればいいという考え方です。
武部 僕は患者さんに価値を提供する仕事をしたかったので、自分の研究成果が患者さんへの価値になるのなら、スタートアップを作りたいというスタンスです。尊敬する起業家・久能祐子さんに「インベンションは飛ぶように、実用化をめざすイノベーションは這うようにやりなさい」と言われたことがあるのですが、研究と起業の両方を経験してみると本当にこの言葉が腑に落ちます。インベンションについては、僕は一つの研究分野を地道に追究するというよりは、飛び技でも何でも誰もやっていないようなアプローチで取り組んでみて、新しい道が開けてきました。それに対してビジネスは、時間をかけて忍耐強くロジカルに進めることで自分のビジョンに共感してくれる仲間ができ、先が開けてきました。起業のトリガーは、CEO人材とCFO人材の二者が揃って初めて引けると思っています。まだ菅先生の会社のように軌道に乗ったわけではなく、道半ばではありますが。
菅 ペプチドリームは創業者たちで資金を出し合って立ち上げたところ、すぐに製薬会社からの契約が取れたのでうまく進みましたが、ミラバイオロジクスは昨今の投資の冷え込みから、なかなか厳しくて。私もかなり投資しているのですが、それでもVCを入れざるを得ない状況です。日米のVCの違いについて話しますと、米国のVCはやはり力があります。米国では有名な教授がそれこそ次々と会社を創業していますが、あれはVCの方からCEO、CFO、CTOまで連れてきた上で研究者に起業を呼びかけているためで、そういったVCによるカンパニークリエイションがトレンドになっています。自身が会社設立のために動く必要がないので、研究者にとってあのシステムは望ましい環境ですよね。
武部 起業したい研究者は、米VCにコンタクトすれば人材もすぐ見つかる。スタートアップを作って動かし始めるサイクルが早いですよね。ただ、ときに大失敗もある。僕の領域に近い、あるスタートアップが鳴り物入りで創設されたことがあるのですが、複数のパイプラインがあったのにも関わらず4年で解散してしまい、驚いたことがあります。でも大規模なリストラが人材流動性を担保している側面もあり、失敗も新たなオポチュニティにつながるのが米国らしいところ。実際、僕が作った会社もその企業からリストラされた人材を採用し、戦力にしています。
菅 人材流動性は重要ですよね。日本のVCについて触れると、研究の目利きにせよ、人材調達にせよ、資金調達にせよ、まだまだ力不足が否めません。では米国のVCを日本に呼び込めばいいかというと、彼らは作ったスタートアップの本社を米国に置こうとしますから、ある意味、技術流出と同じで日本にとってはデメリットになってしまいます。日本で研究とビジネスをつなげるエコシステムをどのようにつくり、どう日本の経済発展につなげるかは今後の大きな課題と言えます。
――これまでのお話でCSTI やLeaP、SS-Fの活動を通じて、お二方が日本の研究者育成や科学技術発展のために尽力されていることがよくわかりました。国や産業界に期待することなどがあれば、お願いします。
菅 スタートアップが、卒業したての優秀で柔軟な考え方を持つ人材を採用できない。ここにも問題があると考えています。就職活動が卒業の一年前に行われる現状のままでは、一年前から予算を組む余裕がなく翌年の採用枠を決められないスタートアップは、就職先の候補からそもそも外れてしまいます。一方米国では、卒業して半年間旅行をするなど、各自のタイミングで就職するからスタートアップにも人材が流入しています。日本の社会的構造を改めるため、経団連とも話し合いを進めているところです。

――最後に次世代研究者へのメッセージをお願いします。
武部 ぜひ、ご自身の研究の中で、"ぶれ"と"ずれ"を意識してみてください。僕はその意識を持つことで、面白い研究ができたと思っています。自分が行きたい方向の軸はぶれずに持つのが前提ですが、その上で研究内容は「自分が考えることは誰かも考えている」はずなので、一旦ぶらす。ぶれた方向に向かうと、その先は自分の専門でない可能性もあります。そういうときに"ずれ"という相対的ファクターが大事になってきて、例えば別の専門家とか違う業界の人、ラボの技術員などキャリアが違う人などとの関係性を大事にすることで想像もしないピボットが起き、それが自分の軸の中でものすごく大きなドライバーになる瞬間が訪れる。いわゆるセレンディピティですが、いつかジャンプするときが来ると信じて頑張ってほしいと思います。
もう一つ、米国の研究者は研究費の獲得のため、時流に乗った研究テーマに偏る傾向があります。その点、日本には時流からは外れた独自の研究を続けている研究者が多く、僕はその領域にこそ可能性がある気がしています。
菅 研究者の中には、基礎研究を論文にまとめたところがゴールだと思っている方もいます。しかし基礎研究は応用につながり、それがイノベーションにつながるのが自然の流れですから、論文のその先に何があるか、次を見通せる研究者になってほしいと思います。また次世代研究者を導く立場の我々が、そういう教育をしなければいけないと肝に銘じ、改革を進める所存です。
 菅 裕明 博士
菅 裕明 博士東京大学大学院理学系研究科 教授
1886年岡山大学工学部卒業、1994年マサチューセッツ工科大学化学科卒業(Ph.D.)。ニューヨーク州立大学バッファロー校化学科Assistant Professor・同Associate Professor、東京大学先端科学技術研究センター助教授・同教授を経て、2010年より同大学大学院理学系研究科 教授。バイオベンチャーであるペプチドリーム株式会社やミラバイオロジクス株式会社の設立に参画。2022年より内閣府総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)議員。2023年6月、ウルフ財団化学部門賞を受賞。日本化学会会長。専門分野はケミカルバイオテクノロジー。
 武部 貴則 博士
武部 貴則 博士シンシナティ小児病院オルガノイドセンター副センター長
大阪大学 大学院医学系研究科 教授
東京医科歯科大学 統合研究機構 教授
横浜市立大学先端医科学研究センター コミュニケーション・デザイン・センター長 / 特別教授
2011年横浜市立大学医学部医学科卒業。同大学 臓器再生医学助手。2013年准教授、科学技術振興機構さきがけ領域研究者。スタンフォード大学 幹細胞生物学研究所 客員准教授などを経て、2015年よりシンシナティ小児病院 消化器部門・発生生物学部門 准教授、2017年より同 オルガノイドセンター 副センター長(現職)。東京医科歯科大学 統合研究機構 教授なども兼務。医学博士。主な受賞に、2014年 ベルツ賞、2018年日本学術振興会賞、2019年 永瀬賞、2023年持田記念学術賞、2024年神戸賞。専門分野は再生医学、コミュニケーションデザイン。