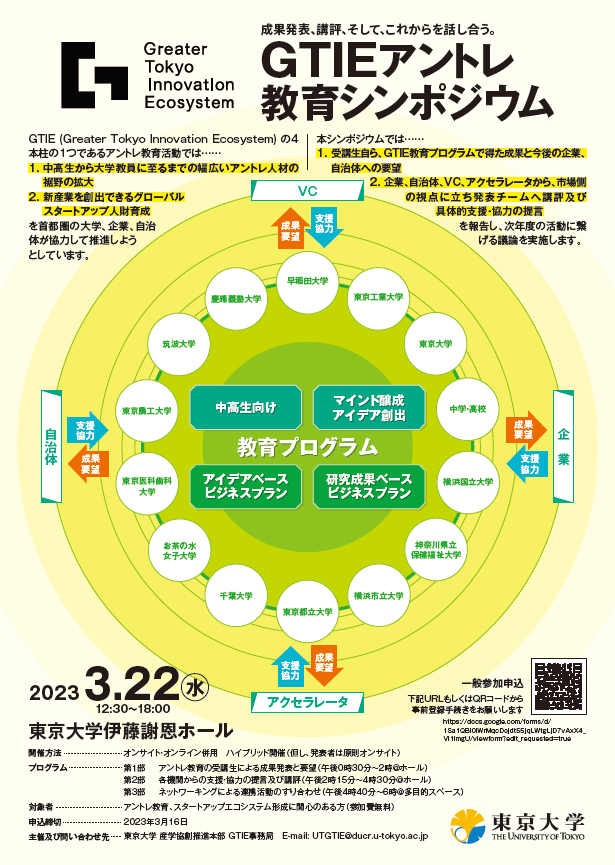2025年2月12日(水)、Greater Tokyo Innovation Ecosystem(GTIE)とLINK-Jは「GTIE(東京圏)、MASP(東北)、Tongali(中部)が支援するライフサイエンス研究者によるDEMODAY」をハイブリッドにて開催しました。
当日は現地参加・オンライン合わせて、197名の方にご参加頂きました。
主催:一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン(LINK-J)
共催:Greater Tokyo Innovation Ecosystem(GTIE)
協力:MASP、Tongali
LINK-JのYouTubeチャンネルでアーカイブ動画を公開しています。(一部編集をおこなっております。)
~世界を目指す大学発スタートアップの創出~
~プログラムに採択された研究者13名によるシーズ紹介~
「自らの技術や研究を、国内だけではなく、最初から世界を目指して展開したい」と考える研究者が増えています。それを受けて、GTIE(東京圏)、MASP(東北)、Tongali(中部)といった各エリアのアカデミアと自治体による、海外を目指す大学発スタートアップを支援するプラットフォームが組成され、各種プログラムが進められています。
LINK-Jでは、これらのプログラムに採択された研究者13名を日本橋に集め、そのシーズをご紹介するDEMO DAYを開催いたします。 これらのプログラムの対象となる研究は、創薬、およびその関連技術、医療機器、AIを活用したシステム、診断、治療など多岐に渡っており、今回のDEMO DAYでも様々なアイデア、最新技術をご紹介いたします。DEMO DAYの最後には、登壇者、参加者によるネットワーキングの時間も設けております。皆様のご参加をお待ちしております。
【各プラットフォームの概要】
Greater Tokyo Innovation Ecosystem(GTIE)
MICHINOKU ACADEMIA STARTUP PLATFORM(MASP)
Tongali
開会挨拶
林 幾雄 (LINK-J事業部長)
講演「GTIEの取り組みについて」
真尾 淑子(東京科学大学)
登壇ピッチセッション【医療機器】
『代謝異常に基づく 早期膵癌・胆道癌診断AIの開発』
馬場 泰輔(名古屋大学)
【講演要旨】
膵癌や胆道癌は、5年生存率がそれぞれ10%、28.7%と固形癌の中で最も厳しい。この現状の打開には、早期発見と早期治療が不可欠だ。一方、癌は非常に多様であり、患者間での遺伝的・分子的な差異が大きいため、全ての患者で一貫して陽性となる腫瘍マーカーを発見することは極めて困難である。そこで我々は、大量のデータを活用し、多様性を考慮した革新的な手法への転換が必要だと考えている。尿中メタボローム解析では、一度の尿検査で1800種類以上の大量の代謝物データが得られるが、従来はバッチ効果などの誤差のため、臨床応用が難しいとされてきた。この課題を克服するために、我々は独自のsingle sample classifierアルゴリズムを開発。これにより、異なるバッチ間でも高精度で膵癌・胆道癌を予測できるAIモデルの構築に成功した。我々は、この尿中メタボローム解析の臨床応用を通じて、癌の早期発見を実現し、治療へとつなげることで、未来をより良いものにすることを目指している。
『スモールデータAIによる希少疾患から主要疾患までを網羅する統合診断支援システムの開発』
鈴木 賢治(東京科学大学)
【講演要旨】
プロジェクトの概要: 深層学習には大量のデータ(1万~10万例)が必要であり、これが医療分野での最大のボトルネックとなっている。我々はこのボトルネックを解決し、100例程度のごく少数のデータ(スモールデータ)で学習可能な独自の深層学習モデルの開発に成功した。本スモールデータ深層学習を用い、大量の症例が収集できずに他の研究機関等が未着手の希少疾患をはじめ、多くの疾患を網羅する診断支援AIシステムを短期・低コストで開発する。現在の医療AIは単一臓器単一疾患限定であるため、例えば複数臓器を撮像する腹部CTからも単一疾患しか検出できず、他の疾患を見落とす。統合診断支援システムの開発は、世界中の様々な疾患を持つ患者を置き去りにしない医療AIの提供につながる。
ミッション: 独自のスモールデータAIで、AI開発から大量データの制限を解き、メジャーな疾患から希少疾患までを網羅する医療AIを全ての医師に低導入コストで提供する。
ビジネスモデル: 統合診断支援システムの国内外での薬事申請・販売を行うスタートアップ企業の創設を検討し、専門医・一般医・研修医に低コストで医療AIを提供する。
活動計画: 連携病院との共同研究を通じ、疾患別医用画像の収集・アノテーション、疾患別AIの開発、読影用高機能GUIの開発を進めると共に、統合診断支援システムの構築を目指す。一方、事業化推進機関と共同して事業戦略・計画を具体化し、2026年度中のスタートアップ企業の創設を目指す。
『顔と声の特徴量を使って心不全入院を防ぎ、健康寿命を延ばす』
岡田 興造(横浜市立大学)
【講演要旨】
心不全は患者数が多いだけでなく、一度発症すると寛解と増悪を繰り返しながら進行する難治性の慢性疾患であり、患者・家族・医療システムへの負荷は計り知れない。一方で、増悪をきしても、早期に治療介入できれば、心不全の進行や入院を抑制することができるため、心不全管理では増悪の早期発見が何よりも重要となる。我々は顔と声の特徴量の変化から心不全の状態を評価できる新たなバイオマーカーの開発を進めている。本バイオマーカーを基軸として、地域全体で心不全患者を管理することができれば、心不全増悪の早期発見を始め、心不全によって引き起こされる様々な医療・社会問題を解決できると考える。
『脂質関連物質に注目した 自閉症診断補助法の開発』
前川 素子(東北大学)
【講演要旨】
2023年のアメリカ疾病予防管理センター(CDC)による報告では、自閉スペクトラム症(ASD)の有病率が2.76%に達すると報告されており、ASDは社会全体で取り組むべき重要な課題となっています。早期診断と適切な支援はASD児の成長に不可欠ですが、現状は臨床で使用可能なバイオマーカーがないことなどが要因となり、診断の遅れが問題となっています。このような課題を解決するため、生物学的知見に基づく新たな診断補助技術の開発が急務です。我々は、脂肪酸結合タンパク質4(FABP4)に着目し、自閉症の診断補助法としての有用性を示す一連の知見を得ました。具体的には、自閉症児における血中FABP4値の低下を発見し、感度94.4%、特異度75.0%でASDを判別可能であることを示しました。また、FABP4遺伝子変異が自閉症に関連することを示すこと、Fabp4遺伝子破壊マウスが自閉症様表現型を示すことを見出し、FABP4機能低下とASD病態の関連性を明らかにしました。これらの研究成果を基に、現在、FABP4を用いた診断補助技術の開発と社会的実装に向けた準備を行なっています。この技術が実用化されれば、早期発見・早期療育に貢献することが期待されます。
『深紫外線LEDを用いた癌治療機器の開発』
國料 俊男(名古屋大学)
【講演要旨】
胆道癌において、手術は根治性が得られる唯一の有効な治療法である。胆道癌の手術では、早期癌であっても大量肝切除になり、病変より大きい正常肝臓が切除される。手術侵襲が大きく、限られた施設でしか治療ができず、低侵襲治療法が必要である。胆道癌に対して内視鏡下治療が可能なデバイスがない。そこで、内視鏡を通して胆管内に挿入可能な細径カテーテルの先端に深紫外線LEDを装着した新しい治療機器を開発した。この機器は、250-350nmの波長でDNAに直接作用して癌細胞を死滅させ、光感受性物質も不要で、アブスコパル効果も期待できる。これまで、マウスの皮下発癌モデルでの抗腫瘍効果が確認できており、ブタを用いた実証実験では側面照射型の試作機で胆管内への照射に成功している。現在、臨床応用にむけ改良を進めている。
市場規模は胆道癌だけでなく、他の癌種への適応拡大が可能であり、今後は胆管癌での臨床実装・保険収載を目指し、その後他の癌種への適応拡大を検討する方針である。
『AI駆動型ACナノポア法による微生物AIセンサの事業化』
山本 貴富喜(東京科学大学)
【講演要旨】
私たちは現在、ウイルスや細菌などの微生物を検出するセンサの販売と、関連サービスを中核としたスタートアップの立ち上げに取り組んでいます。最大の特長は、これまでの手法で得られないような「モバイル・迅速・簡単」によって得られるUXに加え、わずか1度の測定で、どのような微生物がどの程度存在するのか―すなわち種類とその数を明らかにできる点です。私たちがスタートアップとして何を目指し、現段階でどのようなことが可能なのか、そして事業の先にどのような未来を見据えているのかをご説明します。また、これを実現するコア技術(シーズ技術)についても併せてご紹介いたします。
登壇ピッチセッション【医療機器】
『薬剤耐性細菌感染症に対するファージセラピーの事業化』
満仲 翔一(岐阜大学)
『有機溶媒を使わない非晶質医薬品の製剤技術供与事業の検証』
近藤 啓太(名城大学)
【講演要旨】
医薬品は水に溶解しないと体内に吸収されず,薬効を発揮することができないが,近年創出される医薬品候補化合物の7割以上が水に溶けないため,医薬品開発において原薬の溶解性改善技術の重要性が増している.原薬結晶を分子レベルまで小さくして水に溶けやすくする非晶質化技術は,溶解性改善技術として最も利用されているが,有機溶媒の使用が不可欠である.しかし,有機溶媒を使用する場合には,防爆対応の建屋・設備が必要であり,原材料コスト・エネルギー消費量が大きいため,医薬品の製造原価が大きく押し上げる.本技術では,原薬結晶と添加剤球形顆粒を混合処理することで,球形顆粒の衝突・粉砕作用により原薬を非晶質化し,さらに球形顆粒に積層させて非晶質顆粒を製造することができる.そのため,原薬の非晶質化に有機溶媒が必要なく,既存の競合技術(原薬を熱溶融させて非晶質化させる手法)のように高温処理が不要であるため,熱に不安定な原薬にも適用できる.よって,本技術は医薬品の製造原価を大幅に削減することにより,コスト面で開発が断念された医薬品の再開発や医薬品の安定供給に寄与できる.さらに,医薬品製造にかかる環境負荷を削減し,カーボンニュートラルの達成,持続可能性の向上に貢献できる.講演では,本技術を基盤とするスタートアップ設立のための事業化検証について紹介する.
『Protein Crystal Material(PCM)による革新的酵素事業』
土橋 匠(東京科学大学)
【講演要旨】
東京科学大学上野研究室の技術シーズ”細胞内タンパク質結晶化技術”を用いて、新規酵素製品「Protein Crystal Material (PCM)」の製造・販売事業を検討している。PCMは目的とする複数の酵素を内包したタンパク質結晶体であり、熱や乾燥、pHなどへの高い耐性を持ち、結晶体の状態で触媒として使用が可能である。また、内包酵素の組み合わせにより、任意のカスケード反応を構築が可能であり、従来技術では難しかった補酵素再生系を有した触媒利用を実現できる。従来の酵素製造・利用における課題を解決できるソリューションとして、酵素試薬や食品・化学品向けの加工用酵素として展開していく予定である。
『ポリフェノール構造分子を基盤とした 薬物送達システムによる新規バイオ医薬品の開発』
本田 雄士(東京科学大学)
【講演要旨】
タンパク質や核酸などの生体分子は低分子では発揮できない作用機序で薬効を示せる上に遺伝子編集も可能であることから、遺伝子病など難治性疾患の治療薬として期待されている。しかしながら、生体内においてすぐに分解されてしまうことや、標的分子が存在する組織や細胞にほとんどいかないため、活性が制限されている。本技術は、ポリフェノール分子の分子接着性に着目し、種々のモダリティの治療物質をポリフェノール導入高分子と金属イオンで構築された複合体で被覆し、目的の疾病箇所まで効率的に送達する新規薬物送達システム(DDS)を開発するものである。このDDSによって、タンパク質や核酸などの生体内で分解されてしまい活性が制限される治療物質の効果を増強させ、新しいバイオ医薬品を開発する。本講演では、本技術の説明に加えて、どのようなアプローチで薬剤開発を行うのかについて報告する。
『遺伝子を標的とした低分子医薬品を創出する基盤技術』
寺 正行 (東京農工大学)
【講演要旨】
創薬技術が発展する一方、医療費の高騰や、患者の通院負荷の増大は大きな社会課題である。我々は、病気の原因遺伝子上にある特殊構造(G4構造)の位置をAIで予測し、G4構造に結合する低分子医薬品を探す系とノウハウを確立した。低分子医薬品は(注射剤でなく)錠剤にできるため在宅医療を可能にすることに加え、(注射剤と比較し)安価で製造できるため医療格差の是正が期待できる。本事業では当該AI技術を用いて、創薬標的となるG4を同定し、これを標的とする低分子の探索と選抜を支援する基盤研究の社会実装を目指す。
『難治性疾患に挑むAUTACs:選択的オートファジーがもたらす治療革新』
有本 博一 (東北大学)
【講演要旨】
タンパク質の異常な蓄積や機能異常は、様々な難治性疾患の原因となっています。これらの疾患に対する新しいアプローチとして、標的タンパク質分解薬の開発が注目を集めています。私たちは、細胞内の主要な分解システムの一つであるオートファジーを活用した新規分子技術AUTACs (Autophagy-targeting chimeras) の開発に成功しました。AUTACsは、標的タンパク質を選択的にオートファジーによって分解へと導くことができます。特筆すべき点として、機能不全ミトコンドリアの選択的な分解にも成功しており、これは従来の分解誘導薬では達成が困難でした。従来の分解誘導薬が主にユビキチン・プロテアソーム系を利用するのに対し、オートファジーを利用することで、タンパク質凝集体や細胞内小器官なども分解できる可能性があります。また、分解経路の違いにより、これまでの創薬では標的とすることが困難だった疾患関連因子にもアプローチできる可能性があります。本研究では、AUTACsの基盤技術と、治療薬としての可能性について発表します。この技術が、アンメットメディカルニーズの高い難治性疾患に対する新たな治療選択肢となることが期待されます。

『脳機能回復を持続させる治療薬開発』※オンライン登壇
七田 崇(東京科学大学)
【講演要旨】
脳卒中をはじめとした神経疾患は、ダメージを受けた脳神経系の機能に応じた神経症状を生じる。脳神経系のダメージによって失われた脳機能は、脳に備わった修復機転によって代償され、ある程度は回復することが可能である。脳卒中や脳外傷によって失われた脳機能は、リハビリテーションによって発症(受傷)後2~3ヶ月程度まで顕著な回復が期待できるが、その後は回復力が失われていき、残存した神経症状が後遺症として定着する。このように、脳を損傷した場合の機能回復のメカニズムは開始され、終了する。
最近の次世代シークエンス解析技術は、神経細胞を含めた脳細胞に適用できるようになり、脳を損傷した周囲における詳細な分子発現制御のメカニズムを解明することを可能にした。脳卒中は寝たきり・要介護の主要因であり、脳卒中の8割を脳梗塞(脳血管の閉塞や狭窄によって、脳組織が虚血に陥って壊死する)が占めている。我々は脳梗塞モデルマウスと脳梗塞患者の組織を調べることによって、脳梗塞に陥った組織周囲の細胞が、非常に劇的な神経修復の機能を持つことを見出した。この修復機能は、脳機能回復のために神経回路が再構築される過程と同期しており、脳梗塞発症後2ヶ月程度で失われてしまう。そこで、以上のような脳に本来備わった修復メカニズムを持続させ、脳機能回復を促進する治療薬開発への取り組みについて紹介する。
パネルディスカッション
『世界で戦える大学発スタートアップ×ライフサイエンスの育成と 創出に必要なことは?それぞれの立場からみた目線で語る 』 -」
モデレーター:林 幾雄(LINK-J 事業部部長)
パネリスト:藤波 亮(新生キャピタルパートナーズ株式会社 パートナー)
真尾 淑子(東京科学大学)
イベント後のネットワーキング・レセプション会場は非常に盛り上がりました。
皆様、登壇者をはじめとした多くの方とお話をされており、活発なネットワーキングが行われました。
参加頂いた皆様からは「幅広い分野の企業に向けた取り組みが見えて非常に興味深かった。」「発表内容が革新的で素晴らしかった。医療機器から創薬までの分野網羅的な発表で参考になった。」「サポーターのレベルも高く、類似プログラムと比較して、どのシーズのプランもよく考えられていると思った。」と多くの感想が寄せられました。
最後に、登壇の皆様と記念撮影を行いました。
ご参加頂いた皆様有難うございました。