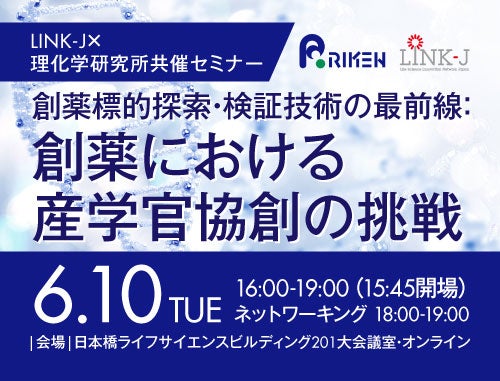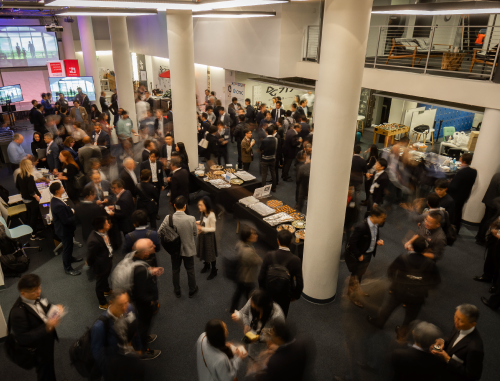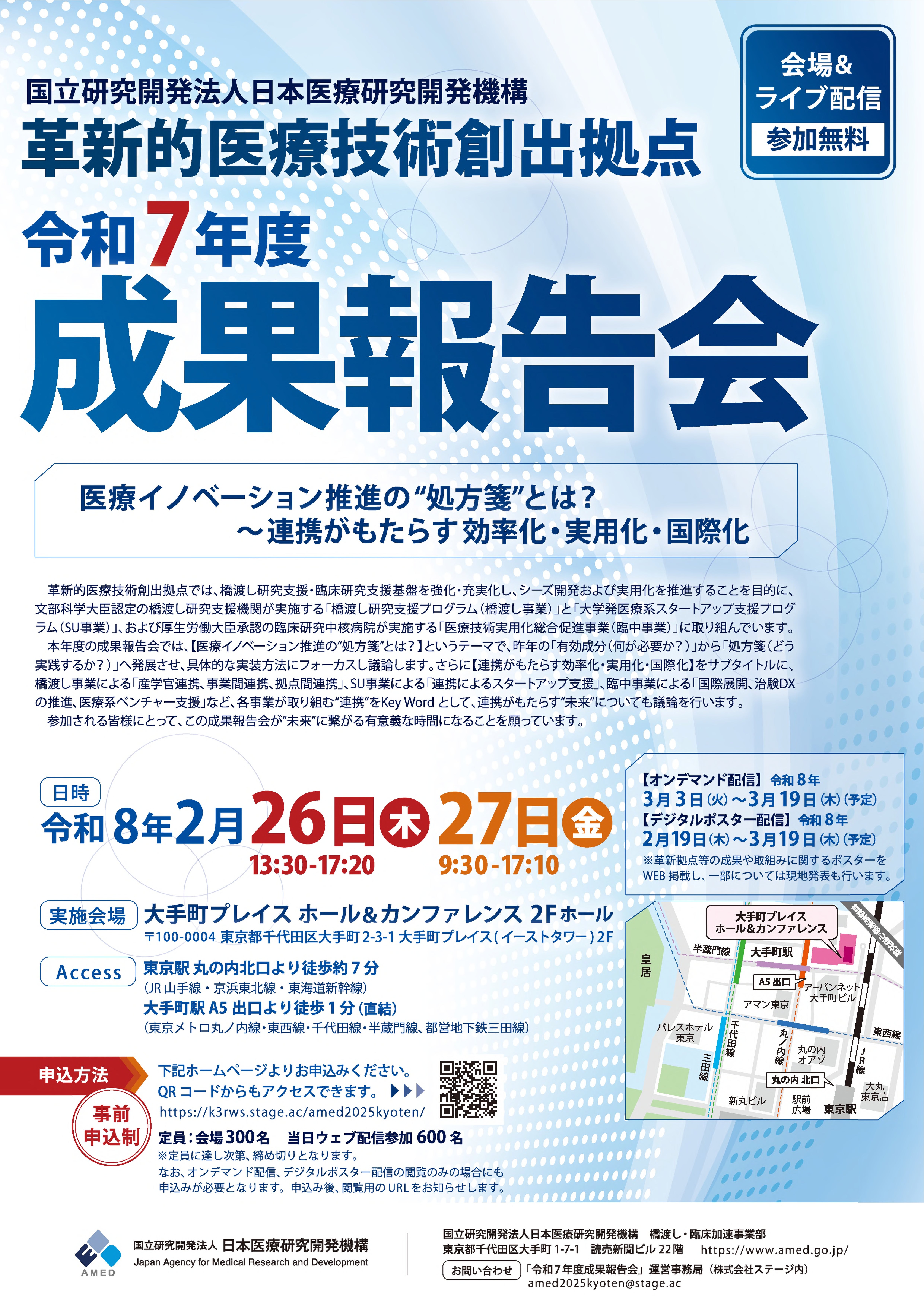おかげさまで満席となりました。当日の飛び入り参加はできかねます。(5/14更新)
BIO International Convention2025期間中に、在ボストン日本国領事館が入居するビルの9階にて、LINK-J Japan Night @Bostonを開催いたします。
今回のプログラムは、ライフサイエンス・エコシステムに関する政府関連機関の活動紹介、エコシステムをテーマとしたLINK-J×BioLabsによるセミナー、ネットワーキングレセプションです。
毎年好評いただき満席となるイベントです、是非お早めにお申し込みください。
※申込締切を【日本時間 5月23日(金)17時】とさせていただきます。満席の場合は締切を待たずに受付終了いたしますのでご了承ください。
※セキュリティの都合上、当日の飛び入り参加は固くお断りいたします。少しでも参加される可能性のある方は必ず事前にお申し込みください。お連れ様であっても飛び入り参加はできかねます。
使用言語
英語
※同時通訳なし
日時: 2025年6月16日(月)16:00-20:30(EDT)
9F, Event Space at the Consulate General of Japan’s office, 100 High St., Boston
※会場は現地のみとなり、オンライン配信はございません
(外部サイトが開きます)
プログラム
セミナーとレセプションを同時開催いたします。
Conference roomとReception roomは隣り合っているため自由にご移動いただけます。
| Reception room | Conference room |
| 3:30pm 開場 (ground floor) | |
| 4:00-5:40 セミナー: 「ライフサイエンス・エコシステムに関する政府関連機関の取組みご紹介」 | |
| 6:00-8:30 ネットワーキングレセプション | 6:15-8:00 LINK-J×BioLabs共催イベント: "Linking ecosystems via LINK-BioBAY TOKYO" (provisional) |
| 8:30 閉会 | |
プログラム詳細
4:00-5:40pm「ライフサイエンス・エコシステムに関する政府関連機関の取組みご紹介」
| 時間 | 内容 |
| 3:30pm | 開場 |
| 4:00-4:05 | 開会 林 幾雄(LINK-J 事業部長) |
| 第一部 | AMEDスタートアップ支援拠点事業 |
| 4:05-4:15 | AMED大学発医療系スタートアップ支援プログラムの紹介(仮) 島﨑 誠 様(エアリッヒパートナーズ合同会社) |
| 4:15-4:25 | 国立がん研究センター Seeds Acceleration Program, NCC SAP 土原 一哉 先生(国立がん研究センター橋渡し研究推進センター・センター長) |
| 4:25-4:35 | QUICK:2000万ドル規模の創薬システム 戸高 浩司 先生(九州大学 生命科学革新実現化拠点 拠点統括/教授) |
| 4:35-4:45 | 慶應義塾スタートアップ推進拠点(Keio Biomedical Accelerator)構築による革新的医療シーズの早期社会実装と、大学発スタートアップ・エコシステムの創成 許斐 健二 先生(慶應義塾大学病院 臨床研究推進センター 副センター長) |
| 4:45-4:55 | 国際展開を目指した医療系スタートアップの育成拠点 町野 毅 先生(筑波大学 つくば臨床医学研究開発機構 橋渡し研究推進センター長) |
| 4:55-5:00 | 筑波大学発スタートアップ(S2)によるピッチ "Polymer-based Nanomedicine For Reperfusion Injury in Stroke" 丸島 愛樹 様(CrestecBio株式会社 代表取締役社長) |
| 5:00-5:10 | AMED創薬ベンチャーエコシステム事業のご紹介 内田 隆 様(日本医療研究開発機構(AMED) 創薬エコシステム推進事業部長) |
| 第二部 | JST・全国ネットワーク構築支援事業 |
| 5:15-5:25 | JST・全国ネットワーク構築支援事業のご紹介 武田 秀俊 様(京都大学成長戦略本部アドバイザー(北米・東海岸担当)) |
| 第三部 | PMDA 「本邦における革新的医薬品等の国際開発の促進に関する取組み」 |
| 5:25-5:35 | 本邦における革新的医薬品等の国際開発の促進に関する取組み 奥平 真一 様(医薬品医療機器総合機構 国際企画部 多国間調整課長) |
| 5:35-5:40 | 閉会 林 幾雄(LINK-J 事業部長) |
6:15-8:00pm "BioLabs x LINK-J Joint Event: Linking ecosystems via LINK-BioBAY TOKYO"
| 時間 | 内容 |
| 6:15-6:20pm | 開会 LINK-J / BioLabs |
| 6:20-6:40 | 基調講演 Dr. Ryo Takeuchi (Director, Genome Editing at Excision BioTherapeutics) |
| 6:40-6:50 | TIB CATAPULT/LINK-BioBAY TOKYOのご紹介 安賀 博子(LINK-J プロデューサー) |
| 6:50-7:30 | ファイアサイドチャット LINK-J / BioLabs / Dr. Ryo Takeuchi |
| 7:30-7:35 | ゲストプレゼンテーション "Introduction to MIT Office of Corporate Relations" Dr. Gayathri Srinivasan (Executive Director, MIT Office of Corporate Relations) |
| 7:35-7:55 | 日本発スタートアップによるピッチ(各社3分) - 株式会社biomy - Crafton Biotechnology 株式会社 - 株式会社iXgene - 京都創薬研究所 - リンクメッド株式会社 - ミルンダ株式会社 ◎事業概要やマッチング希望についてはこちらをご参照ください! |
| 7:55-8:00 | 終了(ネットワーキングレセプションは8:30pmまで開催) |
登壇者略歴・講演内容(順不同・予定)
| 町野 毅 先生(筑波大学 つくば臨床医学研究開発機構 橋渡し研究推進センター長) 筑波大学医学専門学群卒業、筑波大学大学院人間総合科学研究科修了、博士(医学)。循環器専門医。2014年に筑波大学医学医療系助教に着任、2018年より講師、2023年より准教授。2016年からつくば臨床研究開発機構(T-CReDO)に所属し、2018年より医療系アントレプレナーを育成する大学間連携プラットフォーム「Research Studio」を構築・運営し、2024年にAMED大学発医療系スタートアップ支援プログラムに採択され、橋渡し研究支援拠点長として同プログラムを主導している。 講演内容 筑波大学は Research Studio を基盤とする人材育成プログラムに、公的なギャップファンドを提供する伴走支援プログラムを連携させ、国際展開を目指した社会実装を推進します。 国内外の各専門分野のトップリーダー50名以上がメンターとして協力しており、支援人材の Faculty Development も連携・協力機関に提供します。VCや事業会社とも連携体制を構築し、事業化を推進します。 また、UCSDメンター陣と連携した伴走支援体制を新たに構築し、国際的な医療系スタートアップの支援を推進します。 国際展開においては、西海岸での活動実績を活かし、東海岸への展開拡大も検討を進め、米国を中心とした国際展開の拡大を目指します。 | |
 | 奥平 真一 様(医薬品医療機器総合機構 国際企画部 多国間調整課長) 2013年 医薬品医療機器総合機構 新薬審査第五部 2019年 同 再生医療製品等審査部 2023年 同 国際部 国際規制調和調整課 2025年 同 国際企画部 多国間調整課 PMDA国際部門において、ICH、ICMRA等の多国間関係を担当。ワシントンDC事務所設立にも貢献。 講演内容 革新的な医薬品等の開発主体が海外(特に米国)のスタートアップ・ベンチャー企業に移りつつある中、日本においても、こうした開発を迅速に進めていく必要があります。 当該課題に積極的に取り組むため、PMDA は、2024年11月に米国ワシントン D.C.に.事務所を設立しました。 ワシントン D.C.事務所では、FDAを含む米国行政機関と現地での薬事規制協力の強化・規制情報の情報交換を進めます。 また、在米のスタートアップ・ベンチャー企業に対しては、日本の承認審査や市販後安全対策等の規制に関する情報を迅速に提供するとともに、初期の総合的な開発相談及びこれらに関連する業務等を行います。 これらの対応により、日本における革新的な医薬品、医療機器等の開発が促進され、健やかに生きる世界の実現に貢献できるものと考えています。 本発表では、このようなPMDAの革新的医薬品等の国際的な開発促進に向けた取り組みを紹介します。 |
.png) | 土原 一哉 先生(国立がん研究センター橋渡し研究推進センター・センター長) 1993年金沢大学医学部卒業。2000年東京医科歯科大学大学院修了。トロント大学オンタリオがん研究所研究員、国立がんセンター東病院臨床開発センター室長、国立がん研究センター早期・探索臨床研究センターおよび先端医療開発センター分野長・副センター長、橋渡し研究推進センター拠点統括を経て、2024年先端医療開発センター長兼橋渡し研究推進センター長。日本癌学会理事、日本がん治療認定医機構理事。東京大学大学院新領域創成科学研究科客員教授。ゲノム解析技術の臨床実装、大規模臨床ゲノム統合データベースの構築などアカデミア主導創薬基盤の開発・運用に従事。近年は産学公民連携による創薬エコシステム構築にも積極的に関与している。 講演内容 国立がん研究センター Seed Acceleration Program(NCC SAP)では、我が国のスタートアップエコシステムが抱える課題を解決し、日本独自のシステムの創出を目的に、以下の環境整備を進めています。 1. 各分野の専門人材によるメンターネットワークの構築 2. 製造・非臨床開発を支援するCRO/CDMOのネットワーク形成 3. サイエンスの知見を有するCXO人材の育成と確保 4. 米国を含むグローバル市場での資金調達および上市を目指す支援体制の整備 5. アンメットメディカルニーズに基づくカンパニークリエーションの推進 NCC SAPでは、上記1~5の課題に対し、産官学の連携によって解決を図ります。 特に、3. 4. 5.については、以下の3つの取り組みによって支援体制を強化します。 • 日本型カンパニークリエーションモデルの構築 • 企業家レジデント制度の導入 • 海外展開を見据えた支援体制の整備 これらを通じて、基礎研究 → スタートアップ → 実用化 → 再投資という好循環を生み出し、日本の創薬力の強化を目指します。 また、国立がん研究センターががん領域におけるハイボリュームセンターであるという特性を生かし、全国のスタートアップを広く支援できる体制の構築を進めていきます。 |
.jpg) | 許斐 健二 先生(慶應義塾大学病院 臨床研究推進センター 副センター長) 2022年から臨床研究推進センター教授となり、橋渡し研究を統括している。再生医療を中心にアカデミアの橋渡し研究の支援だけでなく、眼科医として医療機器の開発も行っている。アカデミアに戻る以前、PMDAでは再生医療等製品や眼科製品の相談審査業務を、厚生労働省では再生医療等安全性確保法の施行や遺伝子治療等の臨床研究に関する指針の全部改訂を行うとともに、医療機器の保険収載や安定供給に関する業務に携わってきた。米国ハーバード大学関連施設であるスケペンス眼研究所では角膜に関する基礎研究を行い、その後もclinician-scientistとしての研鑽を積むだけでなく、日本の角膜移植のドナー不足解消や医学基準の制定のためにアイバンクの活動にも従事してきた。 講演内容 慶應義塾では、橋渡し拠点である慶應義塾大学病院 臨床研究推進センターが2014年10月以降、400件以上の医療系シーズを支援し、橋渡し研究の観点から社会実装を推進してきた。また、産学連携部門のイノベーション推進本部では、2021年のスタートアップ部門設置以降、医療系の事業会社、VC/CVC、スタートアップ経験を持つ実務家教員チーム、大学VCと協働する伴走支援プログラム、経営人材確保や産業界で活躍する出身者を中心とした支援人材プール構築を含む支援策等を整備してきた。2023年の大学別実績は、企業数で291社/2位、資金調達額で510億円/1位となっている。 2024年のAMED事業で採択された大学発医療系スタートアップ支援プログラムでは、当学における橋渡し研究支援と大学発スタートアップ創出支援の能力を有機的に組み合わせ、さらに発展させた医療系スタートアップ支援拠点を構築し、世界に伍する革新的な医薬品・医療機器・再生医療等製品等の事業化を志す大学発スタートアップの継続的な創出を実現していく。また、必要な支援基盤の構築と運用を行い、当該運用を通じた支援の高質化と効率化、収益モデルの確立に取り組み、事業期間後の自走を目指す。本プログラムにおける当学の現在の取組等について今回紹介する。 |
.4.jpg) | 丸島 愛樹 様(CrestecBio株式会社 代表取締役社長) 当社の技術の高分子ミセルのフリーラジカルスカベンジャーは、特に虚血性脳卒中の再灌流障害に関連する酸化ストレスを効果的に制御することができます。リード化合物であるCTB211は、最適な薬物動態、安全性、ならびに有効性を示しており、脳主幹動脈閉塞患者に対する血栓回収療法後の脳障害を軽減し、神経学的転帰を改善する革新的な高分子医薬を提供できます。 近年、当社はAMED大学発医療系スタートアップ支援プログラム(U2:筑波大学拠点)に採択されました。現在、CMC、GLP-Toxを開始しており、日本および米国での臨床試験に向けた準備を進めています。私たちは、CTB211の臨床開発およびライセンスに向けて、VC、規制対応パートナー、製薬企業の方々との提携に取り組んでいます。 |
.jpg) | 戸高 浩司 先生(九州大学 生命科学革新実現化拠点 拠点統括/教授) 戸高浩司は九州大学医学部卒業後、一般内科、特に循環器内科の臨床研修を受けました。その後、ニューヨークのコロンビア大学で心不全と心機能に関する基礎研究に従事し、1994年には米国心臓協会フェローシップ賞を受賞しました。九州大学に戻り、1997年には心室メカニクスと心不全の研究で医学博士号を取得しました。その後、数年間インターベンション専門医としてカテ室で勤務した後、2002年に厚生労働省医薬品医療機器審査センター(のちの医薬品医療機器総合機構:PMDA)に出向し、審査官を務めました。九州大学に戻り、循環器内科講師に就任しました。2012年、九州大学病院の臨床研究支援組織、ARO次世代医療センターの再編に伴い、同センターの准教授、副センター長に就任し、2019年に教授、2022年にセンター長に昇任しました。2021年からは九州大学 生命科学革新実現化拠点 拠点統括を務め、橋渡し研究へ傾倒しています。 講演内容 QUICK(Quantum University Innovation Cycle from Kyushu)は、創薬を革新する2000万ドル規模のイニシアチブです。26大学(WAT-NeW)、18大学(PARKS)、医療技術共創グラントなどのネットワークから、質の高いシードプロジェクトを調達します。アカデミア発の画期的な研究成果を数多く保有しており、それらを基にした強力な創薬パイプラインを構築しています。QUICKは、シード探索や資金調達から、知的財産管理、臨床試験支援まで、医薬品スタートアップ企業の皆様に包括的なサポートを提供いたします。創薬における「死の谷」と呼ばれる困難な時期を乗り越えるための、最先端設備の利用、GLPコンサルティング、そして100名を超える専門家チームによる献身的な支援体制を整えています。 私たちは、産官学連携によるオープンイノベーションを推進しています。17カ国に広がる国際ネットワークは、臨床研究やグローバル展開を強力に後押しします。さらに、地方自治体からも強力な支援を受けており、起業家の方々には優遇措置もご用意しています。 年間10社の設立と、スタートアップ1社あたり年間最大100万ドル提供を目指します。資金の80%(総額23億円)は、VCを含む民間資金です。400人のCxO候補人材とのマッチングを通じて、スタートアップのリーダーシップ育成を支援します。九州大学と自治体が連携した起業家教育プログラムでは、医療系起業家向けの専門トレーニングを提供します。 最後に、QUICKは、未来の創薬を推進するダイナミックなエコシステムです。製薬会社様には、共同研究やライセンス契約など、様々な形での連携を通して、共に革新的な医薬品を世に送り出し、人々の健康に貢献していきたいと考えています。ぜひ、QUICKと共に、未来の医療を創造していきましょう。 |
.jpg) | 島﨑 誠 様(エアリッヒパートナーズ合同会社) 大阪大学大学院薬学研究科で修士号を取得後、製薬業界及びベンチャーキャピタル業界で30年以上経験。 日本ベーリンガーインゲルハイムで9年間、薬物動態や薬理などの非臨床研究開発、ドイツベーリンガーインゲルハイムで11年間、主に中枢神経系の創薬研究に従事。2015年に三菱UFJキャピタルに転職、キャピタリストとして約20社に投資、アカデミア技術や製薬プロジェクトの新規スタートアップ設立に注力。また、第一三共とのオープンイノベーションプログラムも実施、日本のアカデミアが直面する創薬実用化の課題にも取り組む。 2024年3月から、AMEDの大学発医療系スタートアップ支援プログラムのプログラムオフィサーとして活動。さらに、2024年11月にEhrlich Partnersを設立、医療技術プログラムの実用化と日本の創薬エコシステム確立に貢献するため、医療系ベンチャー支援や海外ファンドとの協業を開始。 講演内容 日本政府はスタートアップ支援を強化しており、2024年10月より大学発医療系スタートアップ支援プログラムを開始することとなりました。今回は、このプログラムの概要を紹介いたします。(仮) |
参加費
無料(事前登録必須)
定員
200名
主催
<主催>
一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン(LINK-J)
<後援>
在ボストン日本国総領事館
<協力>
横浜市
国立研究開発法人日本医療研究開発機構
公益財団法人神戸医療産業都市推進機構
お問い合わせ先
LINK-J事務局 安賀・井本 E-mail:contact@link-j.org