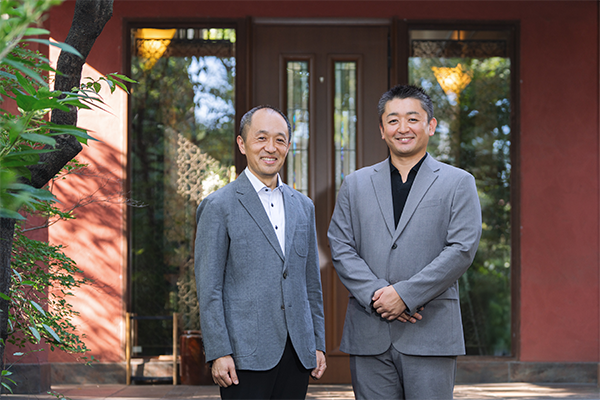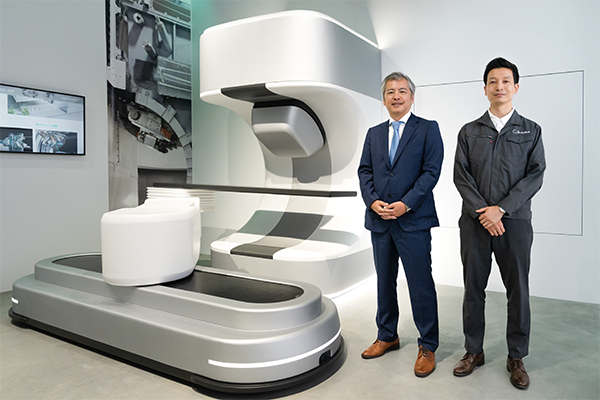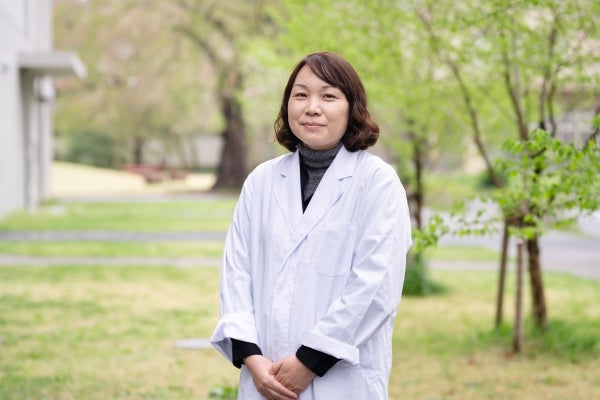株式会社Epigeneron(以下、エピジェネロン)は、藤井穂高博士らが開発した独自の創薬ターゲット探索プラットフォーム技術"遺伝子座特異的クロマチン免疫沈降法(遺伝子座特異的ChIP法)"の事業化を目的に設立された、バイオテック企業です。少人数ながらも、優秀な研究スタッフによって支えられた高い研究力を背景に、製薬会社のラボでも難しい、高度な技術を要求される創薬標的の探索研究に挑戦しています。設立から8年目を迎え、すでに複数のアカデミアおよび製薬会社と共同研究に取り組み、実績を上げてきました。今回の取材では、昨年3月より代表取締役を務める三嶋徹也氏に、同社の設立の経緯とその技術的特徴、今後の事業展望、バイオテック業界が抱える課題などについて、話を聞きました。
経営チームに参画した理由は「チームに魅力を感じた」
――株式会社エピジェネロンの事業について教えてください。
株式会社エピジェネロンは、2015年4月に合同会社として設立されたバイオテック企業です。創業者は、当時は大阪大学微生物病研究所に務めていた藤井穂高博士(現:弘前大学大学院医学研究科教授)と藤田敏次博士(同准教授)です 。当社は、藤井氏らが開発した2つの技術、創薬ターゲットを同定するための技術である「遺伝子座特異的ChIP法」と 、希少な遺伝子配列を検出する技術、「オリゴリボヌクレオチド干渉PCR(ORNi-PCR)法」を活用した創薬事業を目指して設立されました。現在は、特に前者の技術開発を中心に、共同研究事業などを展開しています。
創業当初エピジェネティック制御(塩基配列の化学的修飾によって変化する遺伝子発現の制御メカニズム)に基づいて、悪性腫瘍や神経変性疾患の治療薬の開発に挑戦するという意図を込めて、この社名になりました。社外の方からもエピジェネティック創薬の会社だと認識されがちですが、当社の研究対象領域は、エピジェネティック創薬に限定されず、もっと幅広い遺伝子の発現制御メカニズムを対象としていることも、強調しておきたいと思います。
――三嶋さんが代表取締役に就任されるまでの経緯をお聞かせください。
設立後しばらくは、藤井氏が大学の仕事と代表取締役を兼任していたのですが、設立から2年目に大阪大学を離れて、新たに弘前大学大学院に教授として赴任することになり、兼務が困難になりつつあったこと、加えて同時期に、弊社は初めて外部から投資を受けることになり、成長のために経営体制を強化する必要がありました。そのような状況下で私は、2020年12月に取締役として入社し、翌年3月に代表取締役社長に就任しました。私の経歴にも少しふれますと、大学院卒業後は日本の化学会社に勤務したのち、米国系投資銀行を経てベンチャーキャピタルを複数名で起業して、後にその投資先のバイオテックで代表取締役を務めました。ちょうど、その仕事が一段落した頃に、エピジェネロンと知り合う機会を得て、同社の経営チームに参画しました。
私がこの会社に惹かれた理由は、創業者の藤井氏はもちろん、藤井氏が開発した技術を育成し事業化する力を持った、優秀なチームの存在でした。私も仕事柄、多くのバイオテックを見てきました。バイオテックの成長に重要な要素は、優秀な研究者を含むチームの存在なのです。というのも、たいていのバイオテックは、将来性を秘めた高い技術をもって起業します。しかし、いくら技術が優秀でも、その技術を育成するチームが未完成では、会社としての成長は厳しいのです。その点、藤井氏は事業スタートの時点から優れた研究者を巻き込みながら、優秀な研究チームや事業化チームを結成していました。私はそこに魅力を感じました。
新たな創薬ターゲットを短期間で同定可能な新技術
――"遺伝子座特異的ChIP法"とはどのような技術になりますか。
一般的に疾患と関連する原因遺伝子は、すでに数多く知られていますが、原因遺伝子と創薬を結びつけるのが、非常にむずかしいといわれています。たとえば、標的タンパク質の構造上の問題から、結合して機能を阻害する分子が設計できないというケースも少なくありません。
遺伝子座特異的ChIP法は、特定の遺伝子座領域に結合しているタンパク質やDNA、RNAを網羅的に捕捉し、同定することができる技術です。これにより見出される標的は標的遺伝子の発現を調節する新しい創薬標的で、すなわち従来の技術では創薬不可能だった標的遺伝子を、創薬標的に変えることが可能なのです。
創薬プロセスの出発点である新たな創薬ターゲットの同定には年単位の時間がかかります。遺伝子座特異的ChIP法を使えば、疾患発現のメカニズムにおいて重要な遺伝子座を特定して標的候補の同定まで、1年以内で達成できます。そこから解析を進めれば、従来の技術よりもずっと速やかに創薬ターゲットを同定することができるようになります。
――現在の共同研究契約では、この技術を外部のアカデミアや製薬会社に提供されているのでしょうか?
要求される技術レベルが高度なので、技術を外部にそっくり導出すれば、明日から他社のラボでも実行できるといったものではないのです。そこで現在は、当社のラボだけで探索研究が完結する体制をとっています。具体的には、藤井研究室で開発した研究技術およびノウハウを当社のラボに移転した上で、当社のラボの研究者が探索研究を行い、その結果を共同研究の相手に提供するという形をとっています。
――今後の事業展開の方向性についても教えてください。
当社のコア事業は、主にアセット系事業と、プラットフォーム系事業にわかれます。そのうち、アセット系事業は、独自技術である遺伝子座特異的ChIP法を用いた医薬品開発です。現時点で、すでに複数の医薬品候補のパイプラインがあって、ある程度まで開発が進行した時点で、製薬会社にライセンスアウトしたいと考えています。現在進行中のアカデミアとの共同研究も、アセット事業の一環になります。もっとも、すぐに収益に結びつくような事業ではないので、より長期的な視点に基づく計画となります。
これに対して、現在の当社の収益源であるプラットフォーム系事業では、製薬会社などと提携して、新たな創薬ターゲットの探索・同定を目指すという、共同研究事業を展開しています。今後は、このプラットフォームの幅を広げて、より創薬に近いダウンストリームの部分も強化しながら、複数のプロジェクトに対応できる体制整備を目指していきます。もっとも、ダウンストリーム機能の強化についても、当社1社だけで全ての作業を行うのは難しいので、これもアカデミアや製薬会社などと連携して、相互の技術を活用しながら、新たな体制を構築していく予定です。この2点が、現在の当社の事業モデルです。
――どのような疾患領域での、医薬品候補の開発に挑戦していますか?
当社の技術の特性上、まずは悪性腫瘍と神経変性疾患が、目指すべき二大領域になると考えています。特に最近は、神経変性疾患の研究プロジェクトに注力しています。先ほど、アカデミアとの共同研究が進行中と紹介しましたが、たとえば、新潟大学脳研究所および順天堂大学ゲノム・再生医療センターとは、神経変性疾患に対する新規の創薬標的の創出を目指して、共同研究プロジェクトがいまも進行中です。
――現在の研究体制とスタッフ数を教えてください。
当社の研究拠点は、兵庫県神戸市の人工島・ポートアイランドの中にある、ドイツの製薬会社バイエル社が運営する共同研究拠点"CoLaborator Kobe"内にあります。現在は同ラボで5名の研究者が働いており、それとは別に東京で4名のスタッフが働いています。東京では、日本橋ライフサイエンスビルディング7(日本橋堀留町)内に活動拠点を構えており、ここでは主に事業開発・管理業務などの本社業務を行います。
――なぜ神戸市に研究拠点を構えたのでしょうか。
設立時は、創業者の藤井氏が大阪大学に勤務していたことから、地理的に近いという条件があります。また神戸市は、日本最大級のバイオメディカルクラスター"神戸医療産業都市"をポートアイランド内に設立するなど、長年にわたってライフサイエンス産業およびバイオテックの育成に注力してきました。バイエル社の共同研究拠点にも、第1号として入居しています。これは余談なのですが、研究所は神戸空港と近く、後に藤井先生が赴任した弘前大学と交通の便も良いという、好条件にも恵まれています。
今後も外部とのパートナリング事業を通じて成長を続けたい
――現時点における課題を教えてください。
課題のひとつが、研究者の確保です。当社も研究者を増員して、研究規模を拡大したいのですが、その確保に苦心しています。特に日本の場合は、米国のように製薬会社とバイオテックベンチャーとの間で人的交流・流動性が活発ではなく、バイオテックに転職を希望する研究者の数も、そう多くはありません。その意味では、当社だけでなく、国内のバイオテック業界全体に共通する課題だといえます。特に当社の場合は、技術自体が高度であり、研究者に要求されるスキルも高いため、研究者の確保には難渋しています。
――国内にはバイオテック領域に詳しい人材が不足しているのでしょうか?
人材そのものは、十分にいると考えています。というのも、大学内のポストは限られており、准教授など安定したポストを獲得できる人は、全体の1%に満たないからです。もちろん、ある程度はポスドク(博士研究員)として学内に残れますが、どこかの段階で、アカデミア以外の進路も考えるべき時期が来るはずなのです。問題なのは、国内の多くの大学研究者が、その転身のチャンスに気づかないことですね。
バイオテックのラボは、製薬会社よりもずっと間口が広く、特にポスドク経験者であれば、大いに活躍が期待できる場所なのです。今後は、研究者を対象としたセミナーなどで、転身に成功した研究者に自身の成功を語ってもらうなど、バイオテック業界について、広く知ってもらう必要があると考えています。
――そのほかで、現時点で直面している課題はありますか?
最近はバイオテックに対する投資が冷え込んでおり、資金調達が難しくなっています。特にロシア軍によるウクライナ侵攻の影響は大きく、ベンチャーキャピタル業界も投資の意欲が低下しています。またコロナ禍を受けて、海外との接点が途切れたのも、大きな損失でした。世界的にも、コロナ禍で各国間の交流が途絶えたことで、米国の会社は米国市場に、欧州の会社は欧州市場に閉じこもる傾向が生まれました。アジアの場合、中国・韓国・シンガポールなどの国々がつながりを強める中、日本は孤立を深めています。あれほど犬猿の仲である中国と米国でさえ、実は米国から多くの事業資金を調達しています。
これに対して、日本のバイオテック業界は、いわゆるガラパゴス化が進み、海外投資家からの出資率も低く、資金調達も事業開発も、国内市場が中心です。市場環境も特殊で、外国人投資家に日本の投資市場を説明しても、まず理解は得られないでしょう。同じスタートアップでも、他の産業は海外からの投資を積極的に誘致できているのに対して、国内のバイオテック産業は、まだまだ古典的な状況だといえます。
――ありがとうございました。最後に今後の展望についてお聞かせください。
当社は、自社単独で研究開発をして創薬まで達成するタイプの会社ではありません。アカデミアや製薬会社などとのパートナリング事業を通じて、ともに目的を達成するのが事業方針の前提であり、成長の大原則です。コラボレーションの相手は、製薬会社に限らず、同じバイオテック同士でも、様々な形での連携が可能だと考えています。今後はさらに外部との共同研究事業およびパートナリングの機会を追求していく予定です。また、当社の技術は海外でも十分に通用すると考えています。今後は海外展開にも挑戦し、特にバイオテックの中心地である米国・ボストンにも認知される会社にしていきたいですね。
 三嶋徹也 株式会社Epigeneron 代表取締役社長
三嶋徹也 株式会社Epigeneron 代表取締役社長東京工業大学工学部卒。同大学院修了後は旭硝子、米系投資銀行を経てVCを設立。2007年より投資先のアネロファーマ・サイエンス代表取締役に就任する。M&A、バイオ分野へのベンチャー投資、欧米VCからの資金調達、米国での臨床開発とFDA(米国食品医薬品局)との折衝、製薬会社との提携など幅広い経験を有する。2020年12月に当社取締役就任を経て、2021年3月当社代表取締役に就任する。