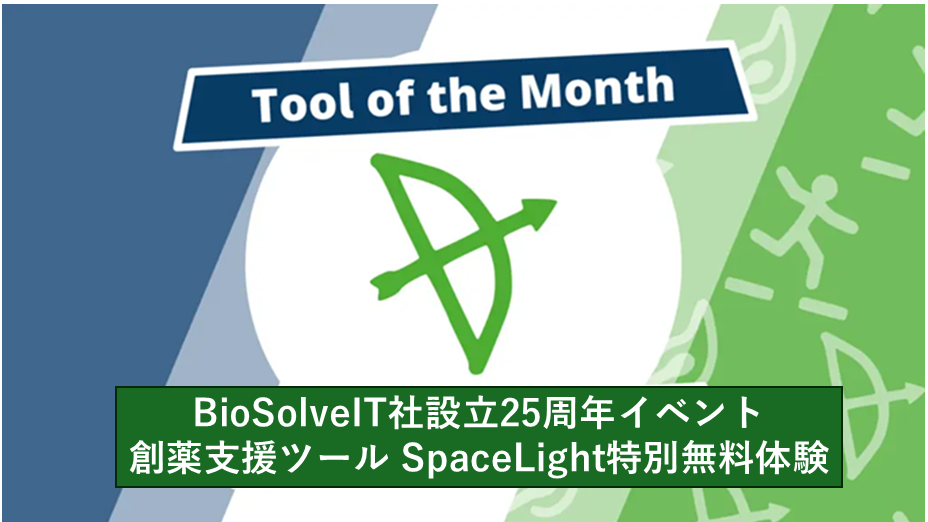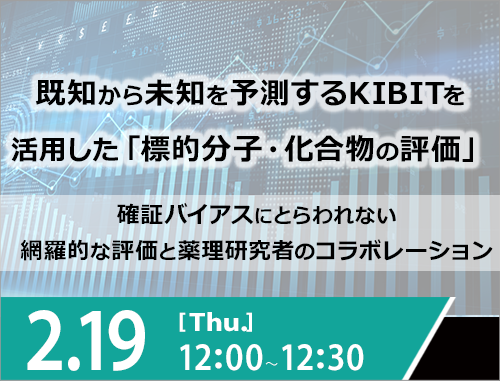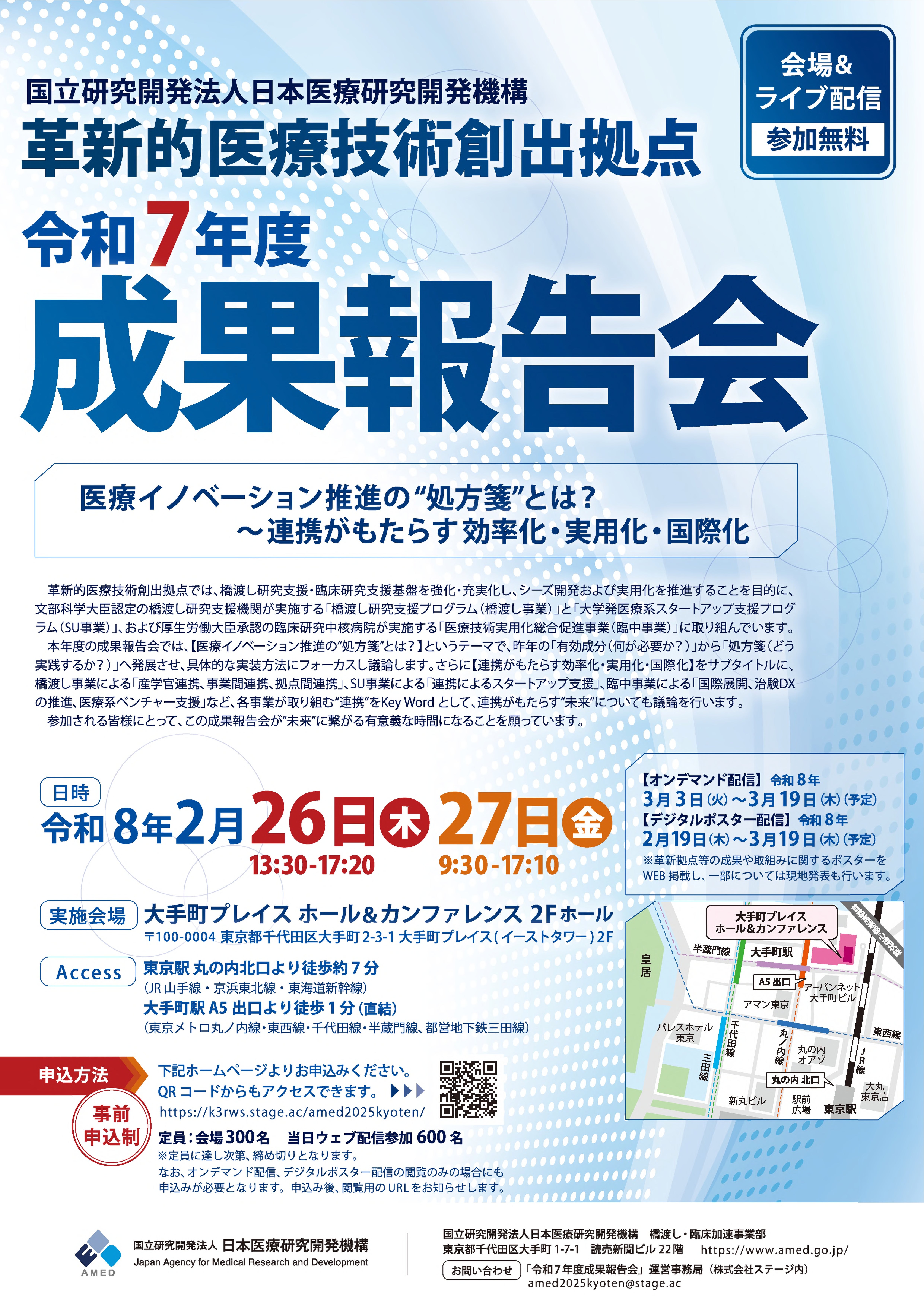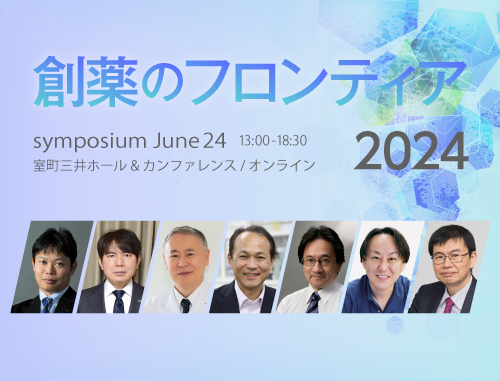LINK-Jシンポジウム「創薬のフロンティア2025」を開催!
角膜再生医療から腸内細菌製剤まで多岐にわたる話題を提供
2025年6月30日(月)13:00-18:30
東京ミッドタウン八重洲カンファレンスホール(オンライン同時配信)
創薬研究の第一人者が一堂に集い、話題の創薬モダリティについて語り合う「創薬のフロンティア」も今年で5回目。
過去4回の開催は、いずれも産業界やアカデミアから素晴らしいゲストの皆様がご参加くださり、最新の創薬をめぐるホットな話題を提供していただきました。
第5回となる今回のシンポジウムも、角膜再生医療から腸内細菌製剤に至るまで、いま注目を集める創薬モダリティの開発に取り組む、産学を代表する関係者の皆様にご登壇いただくことができました。
本稿ではその内容の一端をご紹介します。
当日は、会場・オンラインを合わせて約400名の皆様に参加頂きました。

開会挨拶
岡野栄之(LINK-J理事長/慶應義塾大学再生医療リサーチセンター・センター長/慶應義塾大学教授)
開会に先立ち、岡野先生が開会挨拶に立ちました。今年で5回目を数える本シンポジウムも、最新の創薬モダリティをテーマに、それぞれの領域の第一人者が登壇するという豪華な内容となったこと、シンポジウム終了後は、来場者だけでなく、ライフサイエンス企業との懇親を深める場も用意していることを紹介した上で、岡野先生は「去年のシンポジウムでは、わたし自身も懇親会をきっかけに共同研究を始めることができました。今日もどんな出会いが待っているかわからないので、ぜひご参加下さい」と呼びかけました。
角膜再生医療の実用化にむけて
西田幸二(大阪大学大学院医学系研究科脳神経感覚器外科学主任教授/大阪大学ヒューマン・メタバース疾患研究拠点(WPI-PRIMe)拠点長)
再生医療や遺伝子治療などを用いて、喪失した器官の機能回復を目指す医療が、いま急速に進歩しています。西田先生も、iPS細胞(人工多能性幹細胞)を用いた角膜再生医療に挑戦する研究者のひとりです。すでに臨床研究として4例の患者さんに角膜上皮細胞シートが移植され、全例で角膜上皮再建および視力向上が確認されています。今年からは治験も開始する予定であり、今後の展開が注目されます。さらに西田先生は、仮想空間にヒトの疾患モデルを再現する「デジタルツイン技術」という、大阪大学の新たな試みも紹介。薬効評価や予防医療の検証などに仮想モデルを活用し、そこで得られた知見をリアル医療に還元する「ヒューマンメタバース医療」実現に意欲を示しました。
アカデミア発のイノベーションを社会実装する試み
金子新(京都大学iPS細胞研究所教授/筑波大学医学医療系教授)
金子先生は、人体の防御機構「Tリンパ球」を利用したがん治療技術の開発に挑戦中です。元来、腫瘍細胞はTリンパ球による防御機構を回避する力を持つため、腫瘍細胞を攻撃できるTリンパ球の数は少なく、わずかなTリンパ球もいずれは疲弊して攻撃性を喪失することが知られています。そこで金子先生は、腫瘍細胞を攻撃中のTリンパ球を採取して初期化した上で、再度Tリンパ球に分化誘導することで、腫瘍細胞を異物として認識する能力を維持した状態のまま、Tリンパ球を「若返らせる」技術を開発。実験では、再生Tリンパ球は腫瘍細胞のスフェロイド(三次元凝集モデル)を強力に攻撃することが確認されています。現在は事業化も挑戦しており、今後の展開が期待されます。
カイオム社での多重特異性抗体の展開~独自フォーマットTribody®と二重特異性抗体細胞表面ディスプレイ技術DoppeLibTM~
小池正道(株式会社カイオム・バイオサイエンス代表取締役社長)
カイオム社を代表する技術のひとつが抗体作成技術「Tribody®」です。複数の異なる標的に結合する「多重特異性抗体」のフォーマット技術であり、現在は自社開発および導出候補も含めて、複数のプロジェクトが進行中です。中でもがん治療用抗体(国内P1試験中)は、固形がんに多く発現するタンパク質と、T細胞に発現するタンパク質の双方を標的とすることで、高い治療効果と標的選択性の両立が期待されます。さらに小池氏は、開発中の細胞表面ディスプレイ技術「DoppeLibTM」も紹介。現在は膨大なスクリーニング作業を必要とする二重特異性抗体の開発難度を劇的に下げる可能性を秘めた技術であり、「我々の技術に興味があればぜひご連絡下さい」と呼びかけました。
RNA合成生物学による創薬展望
齊藤博英(東京大学定量生命科学研究所教授/京都大学iPS細胞研究所教授)
細胞内では、mRNAを介したゲノム情報の転写・翻訳という過程を経て、タンパク質の合成が誘導されます。この経路を利用し、合成mRNAを用いて疾患治療に必要なタンパク質の合成を誘導する技術が「mRNA医薬」です。ワクチンから再生医療、がん治療まで多様な可能性を秘めた技術ですが、一方でいまだ様々な実用上の課題も抱えています。中でも齊藤先生は、副作用の原因である「標的細胞以外での非特異的なタンパク質の発現」という現象に着目。これを回避するため、miRNAを用いて遺伝子発現のオン/オフを制御する独自のスイッチ技術を開発しました。齊藤先生は起業もしており、開発と同時に社会実装に挑戦していることから、今後の展開に期待が募る内容となりました。
本邦におけるヒト由来腸内細菌製剤開発の最前線
中原拓(メタジェンセラピューティクス株式会社代表取締役社長CEO)
メタジェン社は、ヒト腸内細菌の医療応用に挑戦する日本発のバイオテックです。糞便移植による腸内細菌を用いた医療は、潰瘍性大腸炎などの消化管疾患だけでなく、たとえば免疫チェックポイント阻害薬との併用で、悪性黒色腫の寛解率が向上するなど、多様な可能性を秘めています。現在はカプセル製剤の開発も進行しており、同社も来年からP1試験を日米で開始する予定です。中原氏は、腸内細菌製剤をめぐる疑問や誤解(便提供者は十分に確保できるのか、患者さんはヒト便由来製剤を受容できるのか、など)を紹介した上で、これらの課題は開発の障壁にはならないと説明。その上で「腸内細菌製剤を世界の患者様に届けるためにも、一切の妥協なく事業を推進していきたい」と述べました。
特別講演 抗体エンジニアリング技術を活用した創薬
井川智之(中外製薬株式会社執行役員研究本部長)
中外製薬は、ロシュグループへの参画を契機に、抗体医薬の技術開拓に積極的に挑戦してきました。その挑戦は確実に実を結び、関節リウマチ治療薬アクテムラや血友病治療薬ヘムライブラなど、同社を代表する抗体薬が幾つも誕生しています。井川氏によると、同社の創薬の特徴は「参入する疾患領域の探索」から始まる他社と異なり、まずは独自の技術を徹底的に磨き上げた上で「この技術が活きる疾患で、いまだ満たされないニーズは何か?」を探索する「技術ドリブン創薬」にあると指摘。さらに、開発のタイムラインに拘らず、逆に「最高品質の候補物ができるまでは治験には移行しない」という姿勢を貫いたことも、革新的な製品を送り出すことができた理由だと述べました。
講演では、同社が開発した創薬技術の数々が紹介されました。自社開発した二重特異性抗体技術をさらにブラッシュアップし、難治性がんにも治療効果が期待できる「次世代T細胞二重特異性抗体」、環境依存的に乖離・再結合を繰り返すという特性を抗体に付与することで、極めて少ない投与量で治療効果が期待できる「リサイクリング抗体」など、その技術は多彩かつ興味深いものでした。たとえ、ひとつの革新的技術が生まれても、さらに「まだ改良の余地はあるはずだ」、「他の疾患にも使えないのか」と追究していくあくなき探究心が、同社の開発力の源であることが、よく伝わるご講演でした。
パネルディスカッション
続いて岡野先生の司会のもと、これまで登壇した6名の登壇者が参加し、パネルディスカッションが開催されました。今回は、来場者やオンライン視聴者から寄せられた質問の中から岡野先生が厳選して提示し、これに登壇者が回答するというスタイルで進行。質問の内容は「デジタルツイン(疾患などをサイバー空間上に再現する技術)の実現を目指す上で何が障害になっているのか」、「バイオ後続品の市場拡大は新規抗体薬の開発に影響をもたらすか」、「ドナーごとの腸内細菌叢の個人差は、腸内細菌製剤の開発リスクにはならないのか」、「製薬企業はアカデミアにどんな役割を求めているのか」など多岐にわたり、これに対して登壇者がそれぞれ独自の見地から回答を示しました。
イベント終了後は、登壇者と来場者が一斉に介する立食懇親会が開催されました。会場には、ライフサイエンス業界で活躍する大小さまざまな企業が、自社の技術や事業などを紹介する案内ブースを出展し、担当者が笑顔で参加者を出迎えました。和やかな雰囲気の中、来場者と登壇者、来場者同士、また来場者と企業の担当者が、飲み物を片手に交流を深めました。
会場内にはLINK-J特別会員企業の事業内容、取り組みを発信する「Meet UPブース」を設け、20社の会員企業の皆様に出展を頂きました。 各ブース多くの参加者・出展者同士、様々な交流が行われており非常に賑わっていました。
ご参加頂いた方からは、「現在注目を浴びている分野のお話を聞けて良かったです。」、「最先端の技術が知れる良い機会でした。」、「話題は非常に興味深く、新しい動向を幅広に知ることができてよかった。」といった声を頂きました。 当日会場までお越し頂いた皆様、またオンラインにて講演を拝聴された皆様には、心より御礼申し上げます。