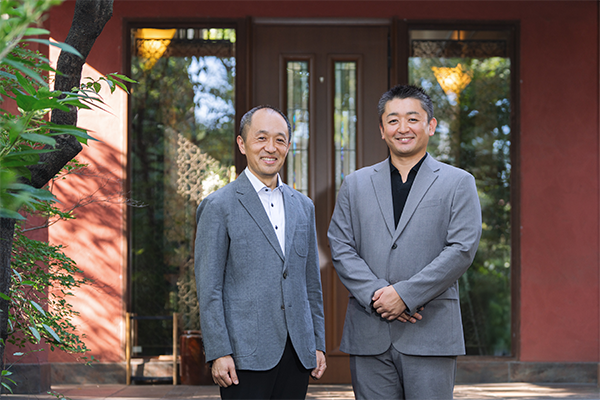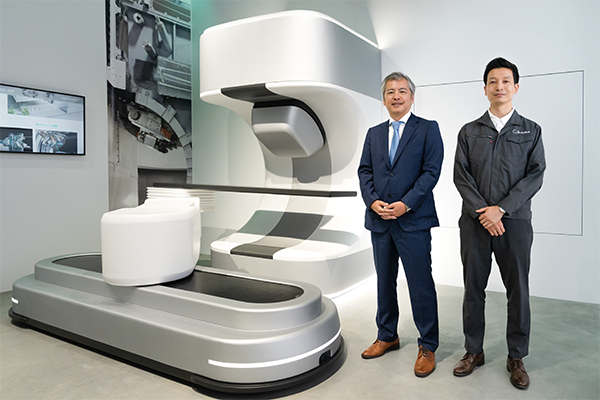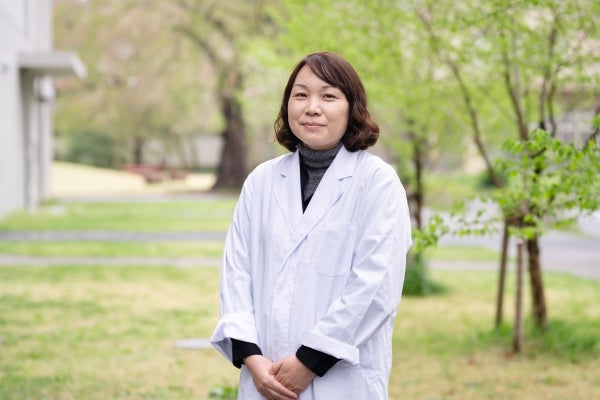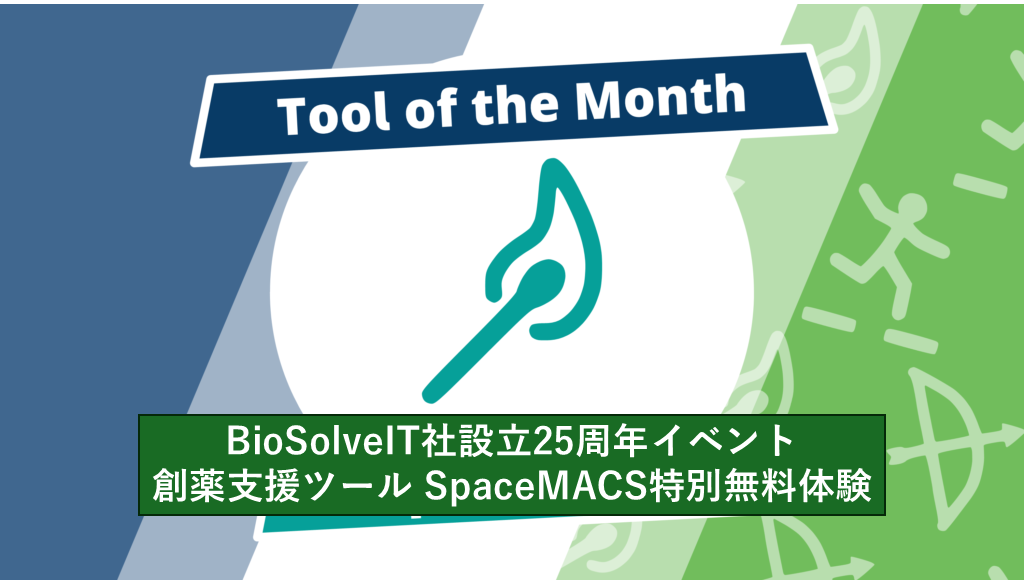株式会社キノファーマは、京都大学との産学連携で医薬品の研究開発に取り組む大学発ベンチャーです。ウイルス性疾患など、医療ニーズの高い疾患領域に対して、低分子薬を研究・開発し、グローバルで早期に実用化することを目指しています。主に子宮頸がんやウイルス性いぼ(疣贅)・尖圭コンジローマの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)感染に対する、抗ウイルス薬を開発しており、2023年には2つのプログラムが臨床試験の次の段階に進む見通しです。これらは腟錠や皮膚外用剤といった局所投与剤として開発しており、有効性・安全性を確保して成功確度を高める戦略です。今回のインタビューでは、代表取締役社長CEOの黒石眞史氏に、同社のこれまでの道のりとプラットフォームの概要、開発戦略、資金調達などについて話を聞きました。
京大発ベンチャーの成果を「世に出さねば」と投資家、そして取締役に
――株式会社キノファーマについて教えてください。
株式会社キノファーマは、創業科学者である萩原正敏先生(京都大学大学院医学研究科教授)の成果をもとに、2005年に創業しました。先端的な医学研究成果から医薬品候補の化合物を創製して、さらに臨床試験を経て、有効な治療薬のない疾患に対して新薬を提供できるよう、日々取り組んでいます。
現在は、東京と京都にそれぞれ本社と研究所を構えています。そのうち、東京本社は、日本橋ライフサイエンスビルディング2内にあります。東京本社では、臨床・事業開発・資金調達などの業務を担当しており、京都研究所では、基礎・非臨床・製剤などの研究をしています。
――黒石さんが代表取締役社長に就任されるまでの経緯をお聞かせください。
当初は、投資家としてウォーターベイン・パートナーズ株式会社の立場で創業の初期から関わってきました。
キノファーマの設立当初、本社機能は研究プラス公的資金マネジメントが中心で、人員のほとんどが研究開発業務をしていました。より開発を進めていくためには、投資家が同社の経営をサポートする流れになり、三菱UFJキャピタル社にもご協力いただきながら、キノファーマを支えてきました。
2006年には、キノファーマの社外取締役に就任しました。ファンドを預かる立場上、最初は兼務でしたが、ファンドの方がある程度足固めできた時点でファンド側の役目を解いてもらい、専任で経営職を務める形になりました。
――御社のプラットフォームについて教えてください。
宿主(ヒト)因子をターゲットとする抗ウイルス薬です。ウイルスは、DNAウイルスとRNAウイルスに大別されますが、極論すれば、殻の中にDNAあるいはRNAという遺伝情報が入っているだけです。それが、宿主である体内の細胞内に入ると、宿主の酵素を使ってタンパク質を合成し、生物のように増殖します。そのうち、特定の酵素を抑えると、ウイルスはタンパク質を合成できず、増殖できなくなります。そこが、我々の開発で最も戦略的かつ新規性の高いポイントだと考えています。DNAウイルスの種類を問わず、阻害能を有する衝撃的な戦略で「これは何とか世に出さなければならない」と思ったのが、この会社に関わるきっかけです。
「子宮頸がんの前がん病態(子宮頸部上皮内腫瘍)」に使用する腟錠を開発中
――実際にどのような適応になるのでしょうか?
子宮頸がんへの抗がん剤ではなく、ヒトパピローマウイルス(HPV)に対する抗ウイルス薬として開発しています。そのような薬剤はまだ実用化されておらず、我々がファーストランナーだと思います。
男女とも、セックスデビューするとほとんどの人が一度はHPVに感染します。自分の免疫でいったん排除しますが、10%くらいの人は排除できずに持続感染になります。持続感染の状態になると、ウイルスの「がん化因子」によって、徐々に細胞・組織が蝕まれていきます。そして「がんになる前」の状態である子宮頸部異形成を経て、長い時間をかけてがんに進行するのです。
一般的な免疫レベルの女性の場合、がんになるまで15~20年かかるとされています。つまり、子宮頸がん検診で異形成と判定された人は、その後も長期に精密検査を受け続けなければなりません。これは大変な精神的苦痛で、その社会的なコストもかかります。
――開発中の薬剤はどのような適応になるのでしょうか?
薬剤について説明する前に、まず開発の背景について説明させて下さい。子宮頸がんの治療法の1つは手術ですが、子宮全摘出術など、女性にとっては非常に辛い手術となります。がんになる前であれば、子宮頸部上皮内腫瘍(CIN、子宮頸部異形成とも呼ばれる)の進行が進む段階で、子宮頸部への円錐切除術という方法があります。そこで現在は、がんになる前の段階での早期発見を目的に、子宮頸がん検診が広く行われています。
検診では、子宮頸部から採取した細胞を調べて、異常が見つかると、精密検査として「コルポスコープ」という拡大鏡で子宮頸部を撮影し、異形成が進んでいる病変を生検して、病理医が異形成の進行度を判定します。進行度は3段階あって、もっとも進行している段階と中間の段階であれば、前述の円錐切除術などの方法で治療介入するのが、現在の医療の対応になります。
私たちが開発中の薬剤は、CINに対する治療薬です。すなわち、子宮頸がん検診において異形成が発見された患者さんに迅速に用いることで、ウイルス活動を抑制し、子宮頸部組織を正常に戻す治療薬です。患者さんにも社会全体にとっても、これが最良の治療法だと考えています。
――臨床開発の進捗状況をお聞かせください。
CINに対する第1/2相臨床試験が終了し、来年には第2b相試験を開始できる準備が整いました。さらに、皮膚のウイルス性のイボ(尋常性疣贅=ゆうぜい=)に対する開発も進行しており、こちらは第2相試験の開始に向けて最終調整をしているところです。ウイルス性のイボは、子宮頸部上皮内腫瘍とは異なり良性なのですが、こちらもアンメットニーズの高い治療領域だと考えています。両疾患を並行して開発できるのが、ベストだと考えています。
我々の薬剤のもう1つの特徴は、局所投与であることです。全身曝露がないため、安全性の観点からも有利であり、かつ組織内濃度が高いので効果的です。実際は腟錠で、就寝前の挿入によって子宮頸部で十分な組織内濃度が得られるため、ウイルス増殖に必要なタンパク質を作らせません。すると、ウイルスは増殖できなくなり、さらに組織は新陳代謝で入れ替わり、最終的にウイルスが排除される仕組みです。さらに今後は、皮膚外用剤・点眼剤と、局所投与剤を連続して開発することで、事業としての成功確度を高める戦略です。
――2005年の創業から17年。ここまでを振り返っていかがですか。
確かに長くかかりましたね。新しいコンセプトをもとに進めてきたので、試行錯誤はありました。初期にそのコンセプトが見えてきて、HPVの抗ウイルス薬としてのポジションが確立するまでは、かなり時間がかかりました。
その後、どのような開発戦略で進めるかを検討し、局所投与剤での開発を決定しました。そうなると、腟錠にしても皮膚外用剤にしても、製剤開発が「第2の肝」になります。製剤の設計・評価、知的財産の確保に外部の力を借りて、一定の時間を費やす必要がありました。京都大学で2016年から医師主導治験を開始してもらいましたが、その間に製剤設計を固めました。
――他に京都大学との産学連携はどのような場面で活かされているのでしょうか?
HPVに対する抗ウイルス薬の開発の難しいところは、動物モデルがないことです。そこで、京都大学の先生方にご尽力いただき、細胞を三次元で培養した上でウイルス感染させた、疑似的な組織モデルで薬理評価をしてもらい、確信を得ました。規制当局にも納得してもらい、前述の医師主導治験を京都大学にて始めていただいたわけです。
――今後の事業展開の方向性をお聞かせください。
HPVは、DNAウイルスの中でも抗ウイルス薬が存在しない、最も大きなセグメントです。我々はベンチャー企業として、すでに抗ウイルス薬が存在する領域で競合するのではなく、治療薬が存在しない領域でトップバッターを狙うという戦略を進めています。これまで話したように、子宮頸部上皮内腫瘍は、アンメットニーズが高い疾患領域です。また、現在の尋常性疣贅の治療は、強い痛みの伴う液体窒素による冷凍凝固法が主流なので、こちらも薬剤へのニーズは高いと考えています。
事業開発では、日本・中国の製薬企業と具体的に提携交渉を進めています。我々のプロジェクトは、まだ臨床開発の初期段階ですが、先方からも高く評価されています。最近では、さらに欧米や他の地域からの導入への関心を受けて交渉を開始しています。
――海外展開についても挑戦しているわけですね。
この薬剤は低分子化合物なので、グローバルで展開でき、どの地域へも流通可能です。欧米を含めたグローバル開発にも、ぜひ挑戦したいですね。ウイメンズへルス領域や皮膚科領域は、世界の各地域で、この領域に強いプレゼンスを持つ製薬企業が活躍しています。臨床開発は順番にグローバルで行い、パートナーリングは、主要地域ごとにステップバイステップ、という事業戦略を考えています。
インフルエンザなどRNAウイルスへの応用も視野に
――御社のプラットフォームを、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスのようなRNAウイルスに対して応用する計画はありますか?
我々は創業期から、DNAウイルスとRNAウイルスの両方をテーマに研究してきました。DNAウイルスに関するプロジェクトが先行したのは、開発資金を獲得できたからです。さらに政府系資金も獲得し、開発を加速させてきました。RNAウイルスについても、まだ研究段階ですが計画はあります。今後さらに資金調達が進めば、我々のコンセプトである「宿主因子ターゲット」のアプローチで、RNAウイルスに対する薬剤も手掛けたいですね。
――LINK-Jに期待する役割についてお聞かせください。
ベンチャーにとって活用しやすい場を作っていただいたと大変感謝しています。日本橋は、ライフサイエンス産業の集積地として毎年発展しており、我々にも地の利があります。皆さんポテンシャルがあり、非常に面白い。リアルな交流ができるのも、インパクトがありますね。
LINK-Jが積極的に活動しているので、海外からも注目され、そこから相互に様々な連携につながることを期待しています。ヨーロッパでも、ライフサイエンスの集積地が注目されていますが、日本橋もそうなりつつあると思っています。我々自身も今後、グローバルな発展に注力したいので、この取り組みを、今後もぜひ加速させていただけるとありがたいですね。
――最後に読者に一言お願いします
現在は、成功確度が高い腟錠と皮膚外用剤で臨床開発を進めていますが、一刻も早く承認に結びつけ、薬剤にしていきたい。子宮頸部上皮内腫瘍で不安を覚えている方々からも、「いつ頃、薬になるのか」とお問い合わせをいただきます。そうした方々に一刻も早く薬を届けられるよう、全力で取り組んで参りますので、引き続きご支援をお願いします。
 黒石眞史 氏 株式会社キノファーマ 代表取締役社長
黒石眞史 氏 株式会社キノファーマ 代表取締役社長ウォーターベイン・パートナーズ元代表取締役。2006年より当社社外取締役、2010年12月代表取締役就任。多くの国内バイオテック企業の創業期投資・立上げ支援の実績を有する。元・JST/STARTプログラム・プロモーター。MBA(経営学修士)。