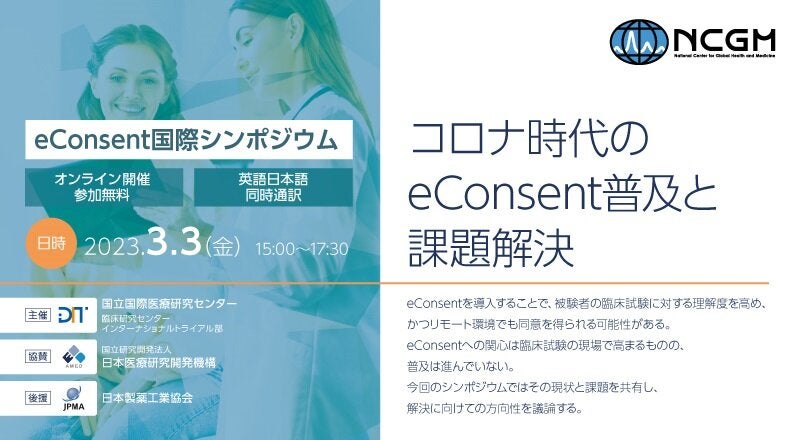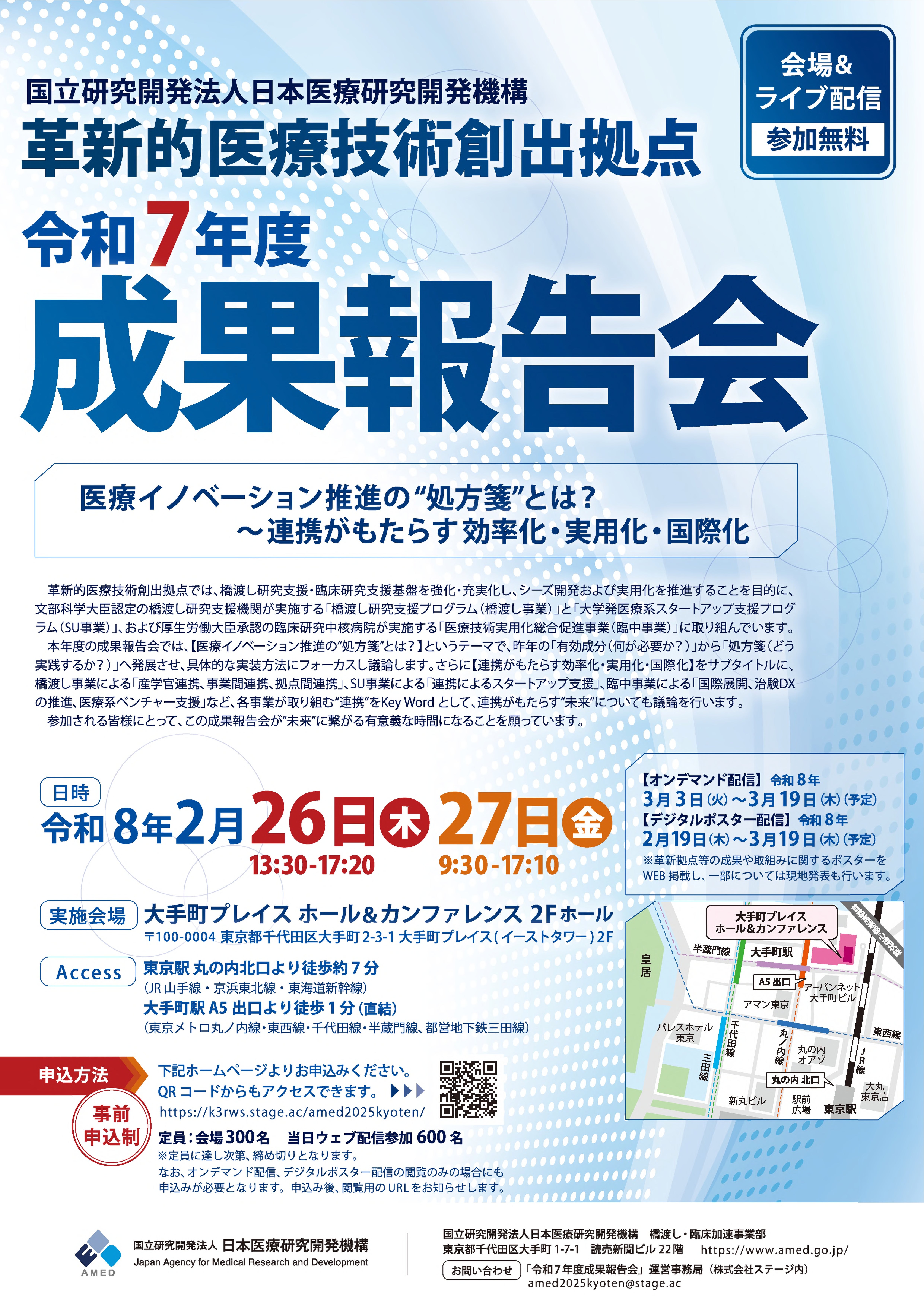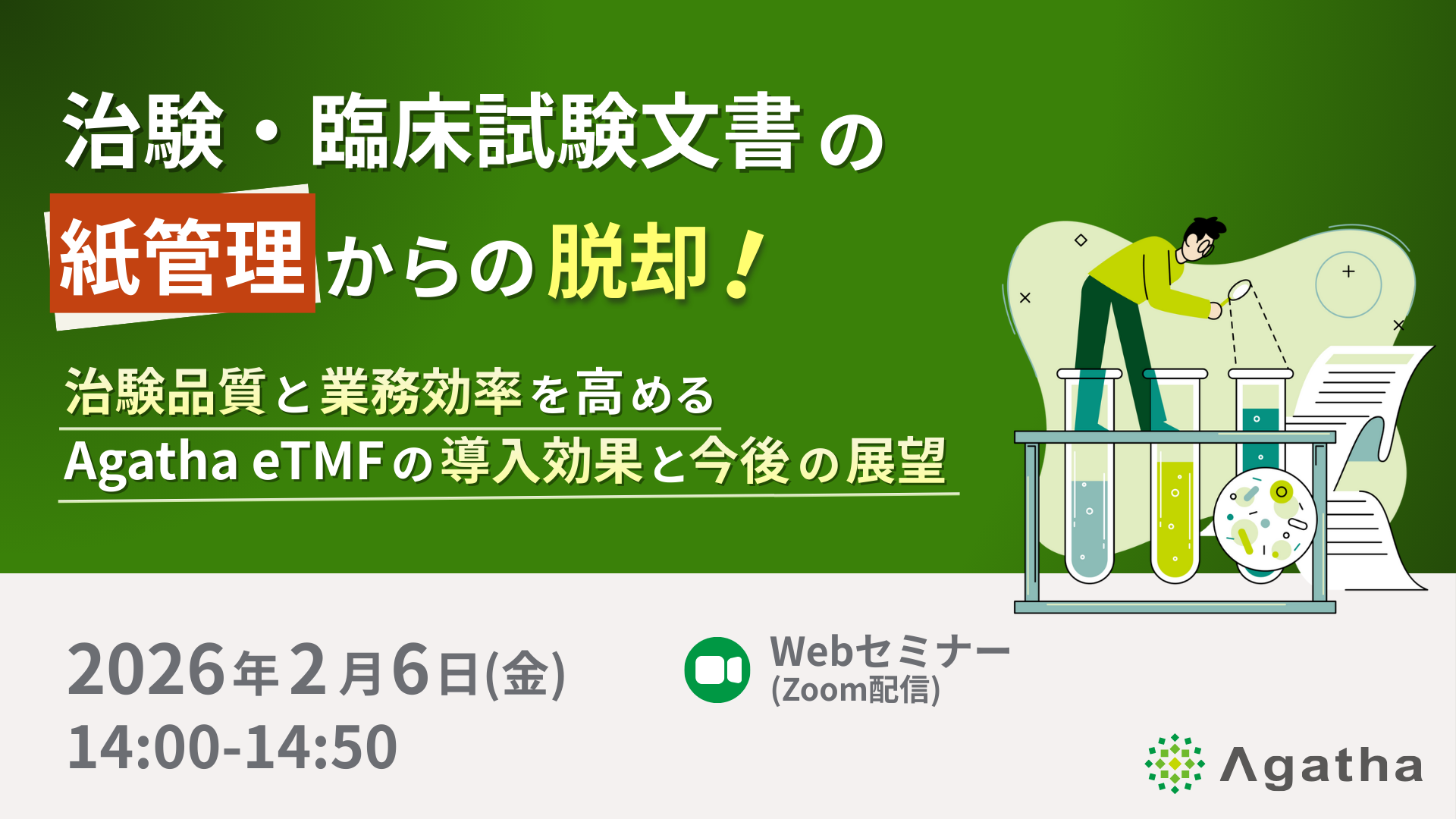近年、DX(Digital Transformation)の進展により、臨床試験をめぐる環境は急速に進化しており、近い将来、DCT(Decentralized Clinical Trial)が実現すると広く考えられている。特に eConsentは、被験者の臨床試験への理解を高めると同時に、原理的にはリモート・インフォームドコンセントを実施可能とする極めて重要なコンポーネントであると考えられている。
eConsentに関するFDAガイダンス(2016)では、eConsentはインフォームドコンセントにおける患者理解を支援する重要なツールとして位置付けており、臨床試験の現場でのeConsentの利用を後押ししている。
一方、Pietrzykoski(2021)は、メタアナリシスの結果から、約半数の患者が同意説明に対するコンセプト(無作為化、プラセボ、安全性など)に対する理解が限定的であることを指摘しており、インフォームドコンセントを適切に行うというヘルシンキ宣言の観点から大きな問題があることを示唆している。
しかしながら、少なくとも日本においては eConsent の利用が進んでいないのが現状である。今回のシンポジウムでは、現状をより正確に把握する必要があると考え、国内と海外におけるeConsent に関する現状と課題を共有し、今後取り組むべき方向性について議論することを目的とする。
お申込み後、配信URLをご登録のメールアドレスにお送りします。
プログラム
開会挨拶
飯山 達雄(国立国際医療研究センター臨床研究センターインターナショナルトライアル部 部長)
Session 1: eConsentにおける共通認識
1) 医薬品開発におけるeConsentの現状と課題
吉本 克彦(日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 電子情報部会)
2) eConsentの基礎知識ーメリットとデメリット
友次 直輝(国立国際医療研究センター臨床研究センターインターナショナルトライアル部
エグゼクティブマネジメント室長)
Session 2: これまでのeConsentとこれからの課題
1) 患者中心の説明同意を目指してわたしたちが取り組めること
高橋 真実(中外製薬株式会社臨床開発本部バイオメトリクス部臨床システム
&インフォマティクスグループ臨床試験関連ITソリューションアーキテクト)
2) Making eConsent a habit in Clinical trial:
Experiences and Challenges in the EU and the US.
Ramya Krishnaa Mokkapati (Data management lead, Global Business Division,
Remedy & Company)
3) eConsent-グローバルの現状とチャレンジ
小野口 浩行(メディデータ・ソリューションズ株式会社
ダイレクトセールスソリューションスペシャリスト)
Session 3: パネルディスカッション
- eConsentはなぜ普及しないのでしょうか。
- eConsentを導入するためには、どのような課題があるのでしょうか。
- これらの課題を解決するために、私たちはどのような行動をとるべきでしょうか。
閉会挨拶
近藤 充弘(日本製薬工業協会医薬品評価委員会 副委員長)
参加費
無料 ※ご参加には事前登録が必要です。
主催
主催:国立国際医療研究センター
臨床研究センターインターナショナルトライアル部 (NCGM-CCS-DIT)
協賛:日本医療研究開発機構 (AMED)
後援:日本製薬工業協会 (JPMA)