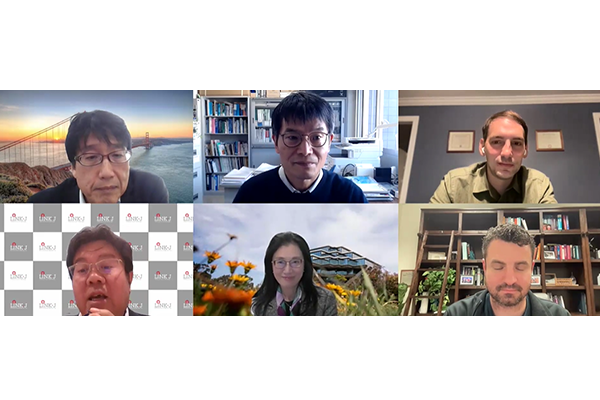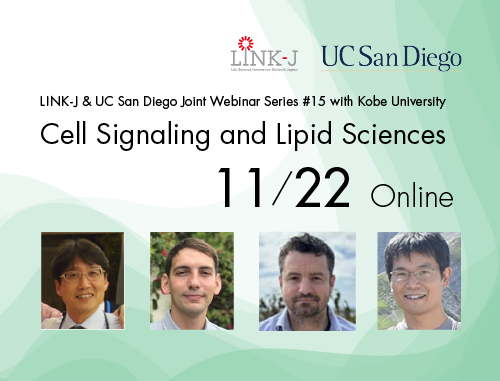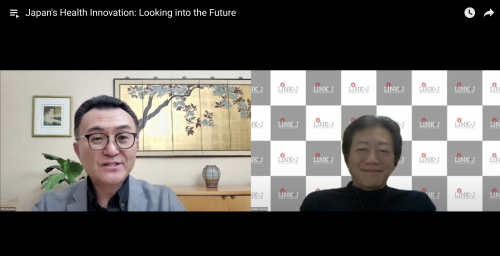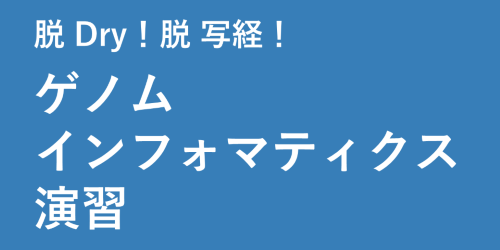この投稿記事は、LINK-J特別会員様向けに発行しているニュースレターvol.17のインタビュー記事の「ロング ver.」を掲載しております。
☜PDFダウンロードはこちらから
大学TLO(技術移転機関)/産学連携推進機構/インキュベーション施設の開設など、いま国内の多くの大学が学内研究の産業連携に挑戦しています。ファンドの設立など資金面の支援もあわせ、ベンチャーの支援・育成制度の充実が進んできました。しかし一方で、特許知財収入の少なさ、国内で調達できる資金の限界などの課題が残っています。これに対して、米国では知財が大学に莫大な利益をもたらし、ベンチャー企業にはVC(ベンチャー・キャピタル)から巨額の資金が提供されています。日本のベンチャー育成は、これからどうあるべきなのか。清泉貴志氏(UCサンディエゴ日本研究センターエグゼクティブ・マネージャー)と萩原正敏氏(京都大学大学院医学研究科教授)のお二人に、詳しいお話を聞きました。
ビジネス経験を通して
起業支援の実態を知るために自ら起業
――それでは最初に、お二人のご経歴についてお聞かせ下さい。
清泉 もともと、私は形成外科医でした。当時の大学病院での主な仕事は、臨床・研究・教育の3つ。ところが、院内でキャリアを重ねていくうちに、運営会議や外来診療管理など、新たにマネジメント関連の仕事も増えてきました。とはいえ、経営管理は全くの素人。医師と兼任では手が回らず、今までの慣例に基づいた運営にとどまっていたのです。そこで思い切って、ビジネススクールで病院の経営管理を学ぶために渡米しました。当時(1990年代)の米国は、バイオベンチャーの勃興期に差し掛かっていました。私もバイオベンチャーでインターンをする機会があったのですが、そこで製品も売上もない段階から投資を受けて研究に取り組む業界のシステムに魅力を感じ、卒業後は現地のバイオベンチャーに就職しました。その後日本企業の米国研究所のトップとしてベンチャーの立ち上げに関わり、現在はエンジェル投資家として活動しつつ、UCサンディエゴの日本研究センターのお手伝いをしています。
萩原 私は三重県の田舎で代々続く開業医の家に生まれ、父の跡を継ぐつもりで地元の大学に進学しました。学部生時代にたまたま誘われて研究室に入り、そこでの発見が脳循環改善薬になる幸運に恵まれました。さらに運のよいことに、大学院での研究も、のちにくも膜下出血術後の脳血管攣縮の治療薬になったのです。その後、教授の転任に伴い名古屋大学に移籍し、ソーク研究所に留学。約8カ月で論文を書きあげると、「セル」誌に掲載されました。帰国後は名古屋大学に戻って解剖学教室の助教授を務めた後、東京医科歯科大学での知財本部事業や起業などを経験し、現在は京都大学形態形成機構学研究室で、RNAに影響する化合物を用いた遺伝性疾患の治療を研究しています。
――お二人とも起業経験者でもありますね。
清泉 私の場合、起業に関心を持ったのは、ビジネススクール時代のインターン経験がきっかけです。卒業後に現地バイオベンチャーに就職したときも、短期間でマネジメントの経験を積み、ビジネスを学ぶため、未経験の事業開発を志願しました。当時のバイオベンチャーはまだ余裕がないところも多く、実務経験が豊富な製薬企業の出身者を多く雇用する傾向にありましたが、この会社はビジネス経験ゼロの私のために社内にポジションを用意してくれました。ここに入るしかないと思いましたね。後に国内製薬企業と組んで米国でスピンオフ起業したときは、経験を活かして日米欧のVCから資金調達し、上場を達成しました。
萩原 私の信条は「隗より始めよ」。何事も自分で経験することが大切だと考えています。東京医科歯科大学で知財事業本部長を務めていた時に、「まずは自分で起業を経験しよう」と考えて、資本の一部を自腹で拠出してキノファーマ社を設立しました。開発に挑戦した抗ウイルス薬は、今では韓国で国際共同治験が進行中です。また、現在行っているRNAに関する研究についても、もうすぐ治験に進める段階まで来ています。私にとっての起業の目的は「いまだ治療薬のない難病のための治療薬の開発」。たとえば全世界に100人しか患者がいない難病のような、大企業ではなかなか手が出しにくい疾患の治療薬の開発に、今後も挑戦していきたいと考えています。

優れた技術は特許出願前に見つける
驚くべき米国の技術移転事情
――現在、国内の多くの大学が学内にインキュベーション施設を設置するなど、起業支援を進めています。しかし、米国と比べると、まだまだ実績が上がっていません。
清泉 米国の方々も、最初から正解を知っていたわけではありません。30年前は、米国のベンチャー企業も大変な思いをしていました。それがインキュベーション施設や大学TLOの変革によって解決されたのです。自分たちの研究について特許出願の必要性が生じた時に、高額な費用がかかる外部の弁護士事務所に代わって特許事務を引き受ける部署として、大学側が学内に設置したのがTLOです。従来は特許を事業会社にライセンスするという業務だけだったのですが、徐々に大学の技術をもとにベンチャーを起業する際の支援業務を拡大し、今では大学発のスタートアップにとって重要な機能を果たしています。
――日本の大学は知財収入が少ないという話もあります。大学TLOとの連携がうまくいっていないということでしょうか。
清泉 米国でも、大学が技術移転を希望する特許情報がインターネット上に公開されていますが、実はその大半はビジネス面からはあまり魅力のないものです。では、魅力的な特許はどこに存在するのか。米国では、事業会社の担当者が大学を定期的に訪問し、将来有望な研究がないかTLO担当者に聞いて回ります。そして有望な研究者を紹介してもらうと、特許出願前から研究者と協力関係を構築しながら、出願と同時に特許権利をライセンス取得します。場合によっては、弁護士を紹介して、一緒に出願書を書くこともあります。日本の大学TLOは、まだそこまでの関係構築ができていないと感じます。
萩原 大学の産学連携担当者のうち、起業の経験者はまだ少ないのが現状です。製薬企業での実務経験は豊富でも、ベンチャーの方法論とは合致しないことも多い。米国を模倣しようとする動きもありますが、日本と米国では文化も社会構造も異なります。こうしたミスマッチが重なった結果、関係者の懸命な努力にもかかわらず、十分な成果が挙がっているとはいえない状況にあります。

――日本と米国を比較して、何が不足しているといえますか。
清泉 日本の場合、ベンチャーに対する投資の歴史と経験が不足しています。起業に対する投資は、成功例より失敗例の方が多いのが実情です。日本は米国を真似て、大学内の支援組織などのいわゆる外側の部分は固めましたが、投資経験が少ないために、失敗の経験と投資のリスクを学べていません。だから、起業も技術移転もうまくいかない。「起業に対する投資は損をするリスクもある」ということが真に理解されれば、エコシステムも回り始めると期待しています。
萩原 特許の問題もあります。国内製薬企業とベンチャーとでは、要求される特許のスタイルが異なることが多い。ベンチャーの市場は日本に限らないため、海外も想定する必要があるのです。そのような特許出願については、国内の特許事務所は不慣れな部分があります。私も出願時には、弁理士とは密に相談して、米国や欧州での特許成立も視野にいれたスタイルで出願しています。また、大学の知財本部長時代に米国の特許事情を調査した際には、特許訴訟における和解金の額まで調べました。そこまでの知識があって初めて、ライセンス業務は成功すると考えています。
私は常々「人を育てなければダメだ」と考えています。たとえば、東京医科歯科大学で知財本部長に就任した時には、大学院生を雇用して特許事情を調査しました。積み上げると高さ1メートルにもなる膨大な資料を米国から取り寄せ、手分けして読み込み、まとめたレポートを書籍として出版。その内容は、再生医療の特許の帰属先からマイクロアレイ技術をめぐる特許訴訟の終結予想まで様々でしたが、このとき雇用した大学院生は現在、様々な場所で活躍しています。その後も人材育成のため、同様の取り組みを続けました。
清泉 そもそも、大学における研究成果が実際の治療に結びつくまでには、長い歳月が必要です。米国の大学も、例えば30年前に誕生してきた様々な技術が、ようやく利益を生みだす段階まできた。そしていま、大学に膨大な特許収入をもたらしているというのが実情です。こればかりは、すぐには真似できません。
――インキュベーション施設が果たした役割についてはどうですか。
清泉 JLABSのようにまったくの偶然からインキュベーション施設が誕生した例もあります。J&Jがサンディエゴに巨大な研究所を建設したにもかかわらず、リーマンショックで人員整理をせざるを得なくなり、ラボ内にかなりの空きスペースが生まれてしまった。そこでベンチャー企業を対象に入居者を募集したところ、最新の機器が揃う充実した環境が功を奏し、大成功を生み出しています。
萩原 私は米国のインキュベーション施設が話題になった時に視察をしました。しかし、同施設が大学構内から離れた場所にあること、そのためにアイソトープや動物実験などリスクのある実験ができないという点に気づきました。帰国後、京都大学からインキュベーション施設の構想を任されたときは、そのときの経験を活かして、動物実験もできる施設として設計しました。それが「イノベーションハブ京都」です。
――京都大学は、学内だけでなく、カリフォルニア大学サンディエゴ校にも研究施設を保有していますね。
萩原 「イノベーションハブ京都」の設立後に、カリフォルニア大学サンディエゴ校のトーマス・キップス氏の依頼を受け、同校のインキュベーション施設設立を支援しました。そのときに「新施設には、京都大学も入居したい」と持ち掛けたのです。いまや、創薬は世界規模で考えるものであり、日本の市場だけで考えていても仕方がない。米国にオンサイトラボを設置することで、日本の優れた技術・シーズを自分たちがイニシアチブを握る形で米国に進出させ、米国の力を借りながら創薬に結びつけたいと考えています。

創業者でさえ解任される可能性も
米国の厳しいVC投資事情
――米国のVCは資金だけでなく人材の供給も行うと聞きますが、実態はどうなのでしょうか。
清泉 米国のVCは、必要に応じて投資先のベンチャー企業に人材の紹介・供給を行います。ただ、その考え方は非常にシビアです。彼らの目的は、投資以上の利益を得て、自分たちの出資者に1ドルでも多くの利益を還元することです。それができないVCは、業界では生きていけない。また、キャッシュアウトまでの期間も大抵は10年以内と視点が短い。だから評価次第では、創業者であろうと最高経営責任者であろうと、取締役会を通じて容赦なく解任・入れ替えを要求してきます。米国でVCから調達できる資金は日本とは桁違いであり、メリットは大きいのですが、こうした事情も知っておく必要があります。
萩原 科学者に要求される資質と経営者に要求される資質は違いますから、考え方は理解できます。だからこそ、私もキノファーマ社では、アーリーステージ終了と同時に経営から撤退しました。とはいえ、創業メンバーでさえ容赦なく切る米国VCの方法論は、日本人の価値観からいえばちょっと受け入れがたい面があるのも事実です。しかし、「郷に入っては郷に従え」という言葉もあるように、私たちも米国に進出する際には、米国のルールのもとで創薬に挑戦する心づもりです。私たちの起業の目的はあくまでも、新たな治療薬をひとつでも多くの患者さんのもとに届けること。そのために必要なのは、次の治療薬の開発のための開発資金確保と、自分たちが開発した薬剤の上市です。この2点が達成できるのであれば、なるべく割り切って考えるようにしています。
――米国でのVCからの多額の資金の調達と、会社経営に対するVCの介入は、トレード・オフにあると考えるべきですか。
清泉 その通りです。私が渡米した30年前は、VCも起業家も共に頑張ろうという気風がありました。しかし現在は、VCの数自体が増加し、VC市場に流入する資金も増え続けています。ベンチャー経験がないVCも多く、ビジネススクールで経営学修士を取得した若者が、少し金融業界をかじってからVCの世界に来ることもあります。彼らは金融知識が豊富でも、技術的評価はアドバイザー任せ。その結果として、経営陣とVCの間に確執が生じてしまうこともあります。
萩原 私も米国の実情を見てきましたし、彼らの方法論は知っておくべきだと思います。でも、日本でもそのやり方をそっくり真似するのではなく、日本人としての強みは何かということを冷静に見極める必要があるとも考えています。たとえばキノファーマ社は、私自身は経営から退いたものの、設立から17年目の現在も、創業時の代表取締役が役員として活躍しています。創業時のメンバーが会社とともに成長し、企業のステージが上がる。このようなやり方が、日本のベンチャーのあり方として理想的ではないかと考えています。

ヒトとヒトをつなぐ役割に期待
日本人の「強み」を活かした支援を
――最後に、LINK-Jに対する期待をお聞かせ下さい。
清泉 いまはコロナ禍で人同士の交流が難しい情勢ですが、LINK-Jはウェビナーを積極的に開催しており、規模感も大きく、ライフサイエンス関係者の触媒役を果たしていると思います。いま指摘されている日本のインキュベーション施設の課題は、同じ建物で働いているのに利用者間の交流が少ないこと。この部分でも、LINK-Jが仲介して積極的な交流を生み出す役割を担ってくれるのではないかと期待しています。
萩原 やはり、日本の強みを生かした支援策をお願いしたい。また、三井グループは商社機能も持っているので、その力を活かした世界中の情報に基づく戦略立案に期待したいですね。最近は国立大学の予算削減の影響が懸念されていますが、こうした動きも産業界から変えてほしい。大学と産業をつなぎ、知的集約型産業をどう発展させるか。グローバルな視点での活躍に期待しています。
 清泉 貴志 氏 LINK-Jサポーター / Kiyoizumi Advisory LLC マネージングディレクター / カリフォルニア大学サンディエゴ校日本研究センター・JFITのExecutive Manager / エンジェル投資家
清泉 貴志 氏 LINK-Jサポーター / Kiyoizumi Advisory LLC マネージングディレクター / カリフォルニア大学サンディエゴ校日本研究センター・JFITのExecutive Manager / エンジェル投資家慶應義塾大学医学部卒業。同大学形成外科学教室専任講師、ハーバード大学医学部外科フェローを経て、マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院で経営学修士を修了。その後ボストンの医薬品ベンチャーで事業開発・戦略企画担当を歴任。2000年には田辺三菱ファルマ米国法人社長に就任。その翌年にメディシノバ社CEOに就任する。現在はエンジェル投資家および投資先企業のボードメンバーとして活動。UCサンディエゴ日本研究センターのエグゼクティブ・マネージャーも務める。
 萩原 正敏 氏 京都大学大学院生体構造医学講座・形態形成機構学研究室 教授
萩原 正敏 氏 京都大学大学院生体構造医学講座・形態形成機構学研究室 教授三重大学医学部卒業。卒業後は名古屋大学医学部薬理学講座助手に就任。1991年にソーク研究所に留学。翌年より名古屋大学医学部会合学第三講座で助手・講師・助教授を務める。1997年に東京医科歯科大学難治疾患研究所教授に就任。2010年より京都大学大学院生体構造医学講座・形態形成機構学研究室の教授を務める。現在の研究テーマは、遺伝子異常による先天性疾患に対する、低分子化合物技術による有効な治療薬候補の探索。