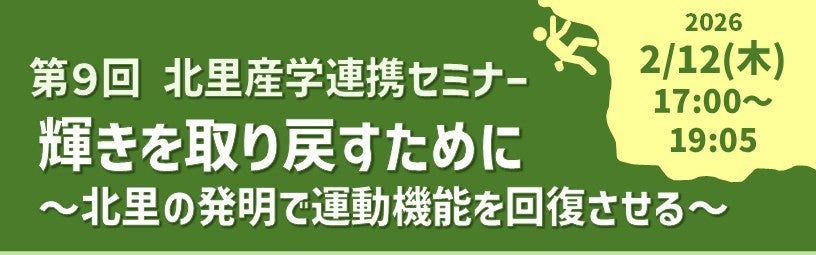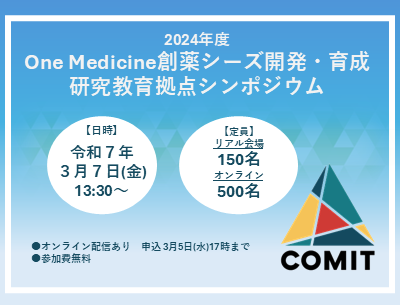名古屋大学医学部附属病院「先端医療・臨床研究支援センター」の水野正明センター長は、その立ち上げから深く関わるとともに、最近まで総長補佐として名古屋大学における産学連携を牽引されてきました。運営諮問委員としてLINK-Jの活動にもアドバイスをいただいている水野先生に、アカデミア発創薬の歩みやアカデミアがめざすべきイノベーションについて、伺いました。
事業化に至らなかった日本初の遺伝子治療の試み
――水野先生のご専門や、これまで名古屋大学で果たされてきた役割についてお聞かせください。
「医療」の分野における専門は脳神経外科で、現在も週4日は臨床医として診療に携わっています。一方、「医学」の分野では1980年代から遺伝子治療学の研究に携わり、いまは先端医療開発、特に細胞再生医療、遺伝子医療を専門にしています。
遺伝子治療について、私は非ウィルスベクターの独自のリポソームを開発し、この技術を用いて1992年には悪性脳腫瘍の遺伝子治療の臨床研究を開始する直前まで行きました。ところが、私たちのプロジェクトはそこで足踏みせざるを得なくなりました。当時米国では遺伝子治療のガイドライン作成が始まっており、日本でも国際的な流れの中で、遺伝子治療のガイドラインやベクターや製剤の品質基準などの整備をする方針が打ち出されたのです。そこで、国の制度の整備と並行して、名古屋大学では、アカデミア内のGMP準拠の製造施設としては国内初となる「遺伝子治療製剤調製室」を設置するなどの対応を行うこととなりました。こうした対応を経て、臨床研究にゴーサインが出たのが1999年のこと。特許取得から実に10年が経過していました。翌年から臨床研究を開始し、悪性脳腫瘍で一定の成果を得たものの、患者数が少なく事業性が低いなどの理由で製薬会社の協力は得られませんでした。なんとか皮膚がんや腎がんなど患者数の多い分野に適応拡大を図ろうとしましたが、特許切れを迎えてしまい、残念ながら事業化には至りませんでした。
しかし、こうした経験が買われて、先端医療・臨床研究支援センターの立ち上げを拝命することとなりました。2010年から運営し、昨年からはセンター長を務めています。また、昨年までの9年間は産学官連携推進担当の総長補佐として、ライフサイエンス分野に限らず、産学連携という橋渡しの出口に近い部分のマネジメントを大学全体として推進しました。この間に、大学の知的財産を10倍にするミッションも達成。また、産学連携の組織を「学術研究・産学官連携推進本部」に改め、基礎研究から産学官連携に至るまで一貫した体制で推進することを明確にし、ベンチャー支援の新たな仕組み作りなども進めました。
大学発のイノベーションを加速するために
――先生が現在センター長を務める先端医療・臨床研究支援センターについて伺います。アカデミア発の医療イノベーションを加速させるため、どのような活動を進めているのでしょうか。
大学の基礎研究の成果が次世代の革新的な治療診断技術の開発に結びつかないという危機感から、2000年代に入って様々な国主導のプロジェクトが始まりました。文部科学省は基礎研究と実用化研究を橋渡しする「トランスレーショナル・リサーチ」の拠点整備を目指した「橋渡し研究支援事業」を、厚生労働省は治験の実施体制の整備や臨床研究中核病院の指定などを進めています。
名古屋大学の強みは、私も関わった遺伝子治療や、口腔外科が中心となって進めていた再生医療などです。早くから「遺伝子・再生医療センター」を整備し、ISO9001や13485のもとで、遺伝子治療製剤、細胞医療用マテリアル、再生医療用マテリアルを調製する「バイオマテリアル調製ユニット」を稼働させるなど、この分野では他大学に先行していました。2010年には遺伝子・再生医療センターと臨床研究支援センターを統合して、「先端医療・臨床研究支援センター」を新設し、シーズの育成から実用化までをサポートする体制を整備。その結果、2012年に文部科学省から「橋渡し研究支援事業」の拠点指定を受けました。ちょうど同じ年に厚生労働省の「臨床研究中核病院整備事業」の臨床研究中核病院にも選ばれ、ダブルタイトルを獲得できたことは、センターを有効に機能させる上でも追い風になりました。
センターのミッションステートメントには、「トランスレーショナルサイエンスとレギュラトリーサイエンスの協調を通じて次世代の医療を開発します」という文言を掲げました。私たちはアカデミアであり、学理の追究を忘れない、サイエンスを基盤とするということを強調するために、「リサーチ」ではなく「サイエンス」という言葉にこだわりました。
こうして私たちは医学系の研究、開発を行い、最終的には医薬品、医療機器、再生医療製品の製品化をめざすことになったわけですが、実は名古屋大学の教員数は東京大学の1/3、京都大学や大阪大学の半分。薬学部もない。そんな不利な状況下で、他大学に負けない結果を出すためには、足りないマンパワーを他で補うしかありません。そこで中部地域に立地する大学や医療機関との連携強化を目的とした、「中部先端医療開発円環コンソーシアム」(Chubu Regional Consortium for Advanced Medicine)、略称C-CAMを組織しました。
C-CAMでは臨床試験を共同で行ったり、施設提供・人材育成・企業とのマッチング・知財管理などの面で名古屋大学が他機関を可能な限りサポートしています。参加施設は中部地域の11大学と国立長寿医療研究センターなど3つの医療機関にまで増えました。将来的には患者団体にも参加してもらいたい、研究開発に携わるプレイヤーばかりでなく、新たな医療の便益を受け、評価する立場の患者さんも一堂に会することのできる組織にしたいという考えからNPO法人の形をとっています。
私たちがC-CAMを組織して3年ほど経った頃、橋渡し研究支援事業や臨床研究中核病院整備事業で、拠点病院の役割の一つに「拠点外病院の支援」が加わったため、現在は全国各地にコンソーシアムができつつありますが、中部地域はさきがけだったと言えるでしょう。

大学が製品化で成果を上げている。この進化こそがイノベーティブ
――先端医療・臨床研究支援センターやC-CAMは、これまでにどのような成果を上げているのでしょう?
医薬品開発は、開発期間が10年から20年、実用化に至るのは3万2000分の1とも言われますが、それを上回るペースで成果は上がっています。C-CAMは非常にうまく機能し、各大学のシーズを集めた結果、「シーズA(関連特許出願をめざす基礎研究課題)」、「シーズB(非臨床POC取得及び治験届提出をめざす課題)」、「シーズC(健常人または患者を対象とした第1相相当の研究課題)」のいずれかのトラックにのっている研究は100を数えます。吃音診断機器、再生医療用に不可欠な細胞分離器、分子標的薬とがん細胞の耐性獲得を阻害するサポート薬の併用療法など、実用化のゴールにたどり着いた事例もいくつか出てきました。
名古屋大学発のシーズで期待しているのは、昨年から臨床研究に入っている新たな白血病治療薬です。先日、日本で医療保険適用が決定されたCAR-T技術を用いた白血病治療薬「キムリア」が3,350万円もするのに対して、名古屋大学で開発中のCAR-Tは高効率の非ウィルスベクターを用いることで薬価が何分の1かまで低く抑えられる見込みです。再生治療、遺伝子治療の薬価は高額になるため、保険財政を圧迫するとの危惧も聞かれますので、少しでも安価で提供できる技術を開発する意義は大きいといえます。
実はアカデミアの「橋渡し研究」は日本独自の考え方。医薬品や医療機器の研究開発は企業だけが担ってきましたが、その機能を大学に持たせようというもの。15年くらい前までは、「大学に医薬品や医療機器の開発・製品化は無理だろう」と言われていたのが、ここまで成果を上げるに至ったこと自体が大きなイノベーションだと思います。
事業採算性の低い希少疾患治療。その研究開発は、アカデミアの責任で
――一方、アカデミアのシーズの実用化にあたっては、どのようなことが課題だと思われますか?
国立大学法人は収益事業ができないため、最終的にはプロジェクトを企業に引き継がなければいけないという点がネックです。企業は事業収益を上げる必要がありますから、採算性がなければ手を出さない。つまり、希少疾患でマーケットが小さい事業には関心がありません。一方アカデミアは、患者さんの治療に役立つなら事業性を問わずに研究開発を行います。そこに企業とアカデミアの境界線があります。
最近米国で承認された脊髄性筋萎縮症の遺伝子治療薬の価格は212万ドル(2億3000万円)もする。日本にこれが入ってきたとき国民皆保険が耐えられるのかということが話題になっています。一方、名古屋大学には遺伝子・細胞治療のためのバイオマテリアル調製施設があり、ISOを取得しています。すべての製造がGMP準拠という意味ではありませんが、一定レベルの品質の担保が可能です。アカデミアにはこうした技術を安価に提供できるノウハウがあるわけです。希少疾患の治療などについては、たとえば臨床研究中核病院や橋渡し研究支援拠点が、患者さんと話し合って、保険診療外で医師の責任の下で新しい医療を提供するといったことを考えてもいいのではないでしょうか。
大学発ベンチャー増加のカギを握るのは、VCの発展
――企業に事業を受け渡す代わりに、大学発ベンチャーを興す方法はとれないのでしょうか?
日本では、まだ大学発ベンチャーが育つ土壌が十分に整っていません。特に創薬や医療機器は資金や時間もかかります。製造段階で、他企業の特許に引っ掛かってしまうリスクも高い。強い知財を有したブロックバスター級の製品に育つ見込みがない限り、起業への挑戦は難しいでしょう。欧米の場合はVCが発達していて豊富な資金を提供するので、ベンチャーを興せるのです。VCは目利きの立場ですから、10のうち1つでも当たり、総和でうまくいけばいいという考え方。日本でも今後VCが発達すれば、大学発ベンチャーも活性化するでしょう。今後はその方向で進めていくことも重要とは思います。
しかし、名古屋大学発のベンチャーも頑張っています。私が総長補佐の立場で産学連携を進めているときには、「名古屋大学発ベンチャー称号認定制度」を作りました。大学のお墨付きにすることで、起業家個人に信用を与えるのが狙いです。認証をとったプロジェクトは現在31あり、その内12が医療系ですが、製薬関連はなく診断機器や医療機器の一部分に関するものがほとんどです。
実は、私自身も地域医療と地域包括ケアを円滑に進めるための「多職種情報共有クラウド型プラットフォーム」を開発するベンチャーを立ち上げています。脳卒中医療は患者さんの一生涯を支えることが肝ですから、地域における連携のためにいわゆる電子連絡帳を開発したのです。愛知県内54市町村のうち48の自治体で運用されています。いまのところは自治体単位の運用が多いのですが、ネットワーク化を進めることで700万人分のデータが集積できます。大学がネットワークやデバイスの開発部隊となり、事業運営のためのベンチャー企業を立ち上げました。もう一つ患者と患者家族が関わるNPO法人も立ち上げ、この三極をつないだビジネスモデルで運営しています。売上も順調です。このような形で、初期投資が負担にならない事業ならベンチャーは立ち上げられます。ちなみに、私は利益相反を避けるため、ベンチャー企業では代表権のない会長職に就いています。

――いまも脳卒中などの診療の現場に携わっている水野先生ならではのベンチャーですね。先ほどのC-CAMのお話にもありましたが、C-CAMやベンチャーの三極に患者さんに参加してもらうのは、どのような目的なのでしょう?
以前は、医者がトップにいて看護師や技師は医者の指示に従うという垂直連携の医療の構造がありました。しかし、MR、CTなどの医療技術の高度化や医療業務の細分化とともに、医師ひとりでは十分な医療を提供するということはできなくなりました。今では医師が中心にいるとしても、関連職種が「チーム医療」という同じプラットフォームいるという水平連携の構造になっています。そのチーム医療のプラットフォームに当事者である患者さんも入るのは、当然のこと。お互いにリスペクトしながら、対等な立場で話し合うスタンスを大事にしたいと思っています。
私は、超急性期の脳外科医として多くの命を救ってきました。患者さんは退院してリハビリなどのために次の病院に移っていく。ところがある時、ずいぶん昔に手術した患者さんから「先生に命を救ってもらったけど、半身不随で20年苦しんで生きてきた。わかりますか」と言われました。この一言が今でも忘れられない。手術をして終わりではなく、その患者さんがお亡くなりになるまでちゃんとフォローしていける仕組みづくりが必要だと気づかされ、在宅医療や地域包括ケアに関わっています。現場を離れ、患者さんから離れると、医療に対する自分の感覚がまちがった方向に行ってしまいそうなので、常に現場に軸足を置くためにも外来診療を続けていますし、そのほかの場面でも患者さんとの接点を大切にしています。
産学連携から産学共創へ、社会貢献のドネーションの文化が必要
――先生がお考えになる産学連携の理想形とは、どのような形なのでしょう?
大学の診療活動にせよ臨床研究にせよ、何をめざしているかというと、最終的には人の幸せや社会の幸せということです。私たちはそれを得るために健康分野からアプローチしているのです。私は、人の幸せを大学が見出そうと思ったときに、産学連携はどうあるべきかという観点で常に考えています。大阪大学に「産学共創」本部という組織がありますが、私も、産学の連携のステージから共に創るステージに変わっていくべきだと考えています。
現状行われている産学連携は共同研究が中心で、企業がその事業戦略に沿ってアカデミアと組むという企業主導で進められています。私はそれを「企業戦略追従型」だと言ったりもするのですが、企業の戦略に役立つかどうかで連携が作られている。企業によるアカデミアのシーズのソーシングともいえる状況です。一方、欧米にはドネーションの文化があって、ビジネスで財を成したらその一部を社会貢献として大学などに寄附をする。このような寄附が、大学の研究を支えているのです。
いま私たちが考えている産学連携の姿は、日本でも共創の観点から、事業で得た資金を紐付きでない形で大学に入れてもらうようにできないかということです。大学はその資金によって自立するとともに、社会課題解決のための新たなプロジェクトを展開するというサイクルを回せるようになります。企業戦略ではなく社会のニーズに基づき、世の中に役立つものを共に創る。産学連携から産学共創になって、こうした社会貢献の資金の流れができることで、人の幸せ、社会の幸せにつながるのではないでかと考えています。
そのための第一歩として、名古屋大学では産学連携で出た成果に対するリターンを、企業にしっかり求めています。「IPOするときは上場前株の〇割を」とか、「売上の〇%を」といった具合に、厳しく交渉し、社会貢献の資金ルートを増やしていこうとしています。
医療は"人としての幸せ"のためにあることを忘れずに
――最後にLINK-Jへの期待やご要望をお聞かせください。
C-CAMは中部圏の共同事業体として、ニーズオリエンテッドな医療技術開発を志向し、うまく機能してきました。これを次のステージに高めるには、中部圏という垣根を取り払い、日本全国あるいはグローバルに展開していくことが求められます。世界に開かれた医療や健康分野への貢献のためには、拠点が必要となる。そのためにも、日本橋周辺の開発は重要で、医薬品、医療機器も含めたライフサイエンスの場を提供するのが大切です。場が本当に活性化すると、患者さんも含め、医療に関わるより多職種の人材が集まります。そういう展開が生まれてくるとよいなと、LINK-Jにはそのつなぎ役を期待しています。
もう一つ、LINK-Jに関わる皆さんに忘れてほしくないのは、「医療」で何をめざすべきかという議論です。これまでの西洋医学は、臓器から組織、組織から細胞、細胞からタンパク、タンパクから遺伝子へとテクノロジーのイノベーションを続けてきました。これは「医学」の進歩としてはすばらしい成果です。一方で「医療」がめざすのは患者さんの臓器の幸せではなく、あくまで患者さんの幸せ、人の幸せ、社会の幸せです。医学の進歩=医療の進歩と勘違いしてはいけないのです。患者さんは一人ひとり違うのだから、めざすべきゴールは個別医療。今ようやく個別「化」医療までは進んでいますが、その先の個別医療をめざさないと、その人の幸せにつながらないと考えています。LINK-Jの中では、個別医療を志向している議論も見られるので、その点も大いに期待しています。
――LINK-Jの役割は、まさに人と人、人と企業、企業と企業をつないでくことです。先生のご期待に沿えるよう、努力してまいります。
LINK-Jには、スティーブ・ジョブスのいう"Creativity is just connecting things――ものをつなげたら創造性が生まれる"の世界を、ライフサイエンス分野で作り上げてほしいですね。私もできることは、協力させていただきます。
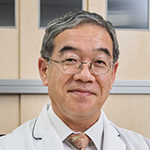 水野 正明 氏 名古屋大学医学部附属病院教授 先端医療・臨床研究支援センター長
水野 正明 氏 名古屋大学医学部附属病院教授 先端医療・臨床研究支援センター長1959生まれ。1992年名古屋大学大学院医学研究科修了。社会保険中京病院、国立長寿医療研究センターを経て、1996年名古屋大学医学部脳神経外科助手、1999年同大学院医学系研究科遺伝子治療学助教授、2010年同医学部附属病院脳卒中医療管理センター長。同年先端医療・臨床研究支援センター副センター長。総長補佐(産学官連携担当)も務める。2018年より現職。