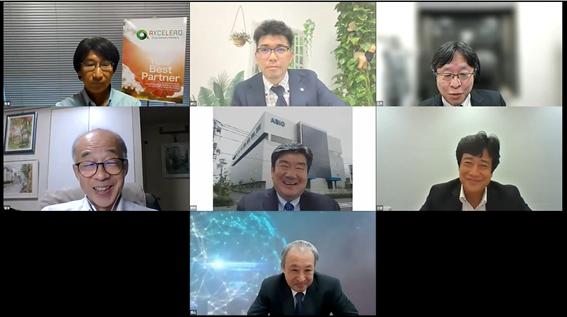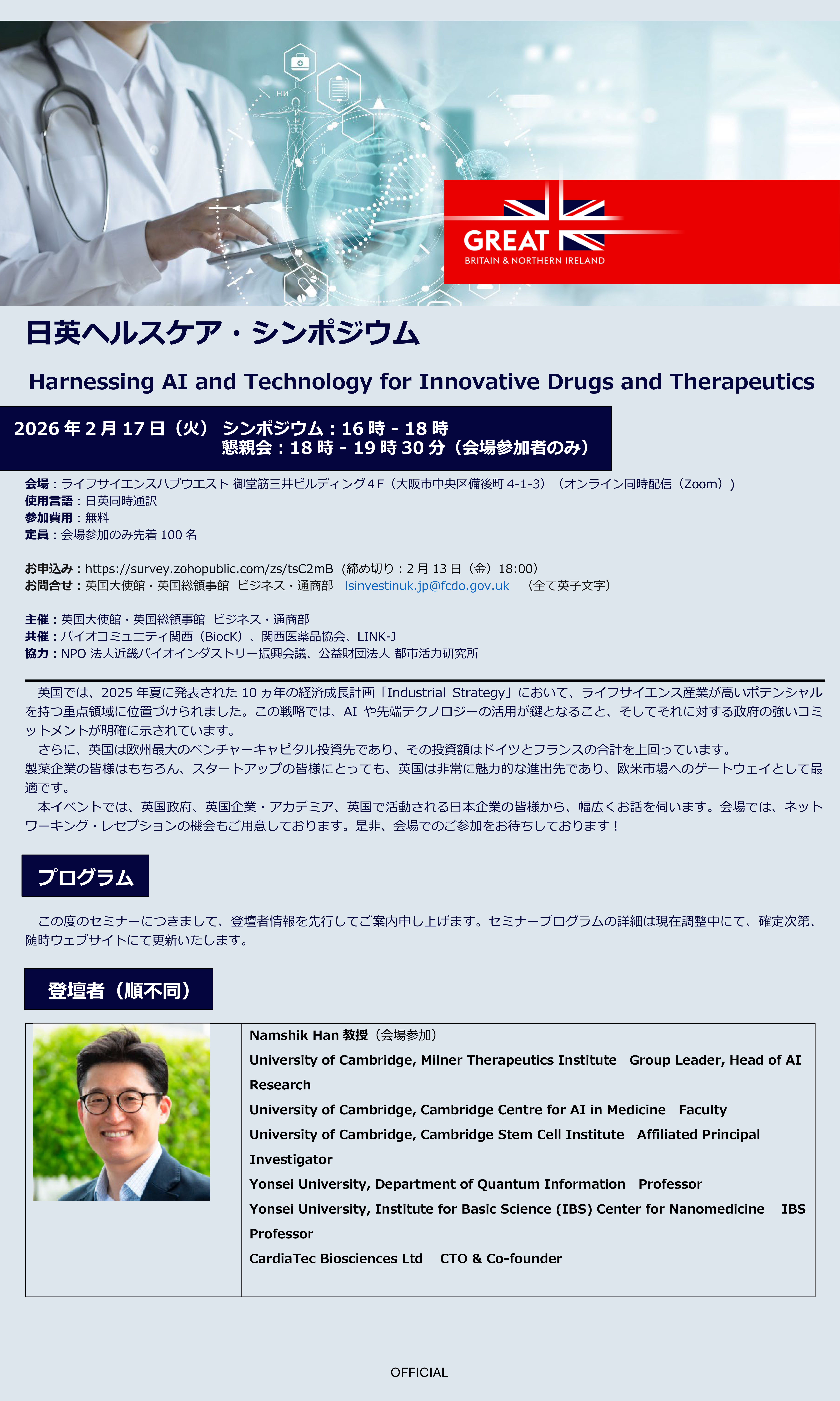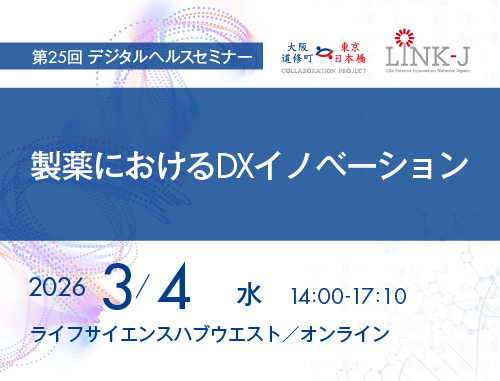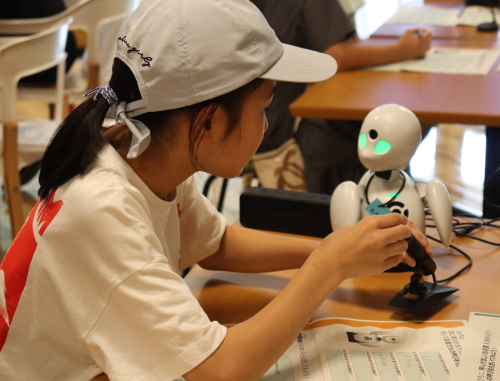2024年5月28日(火)、 LINK-J は「中之島Qross×殿町キングスカイフロント 連携セミナー~東西の再生医療拠点が描く未来~」をライフサイエンスハブウエスト、オンラインにて開催しました。

登壇者
坂田 恒昭 氏(大阪大学共創機構 特任教授; バイオコミュニティ関西 副委員長兼統括コーディネーター)
幸寺 玲奈 氏(経済産業省 生物化学産業課 課長補佐 )※オンライン登壇
山崎 達美 氏(公益財団法人実中研 理事)
嶋村 敏孝 氏(川崎市 臨海部国際戦略本部 成長戦略推進部 キングスカイフロントマネジメントセンター 所長)
西野 晃弘 氏(大阪府商工労働部成長産業振興室ライフサイエンス産業課長)
川井 幸輔 氏(岩谷産業株式会社 産業ガス本部 エアガス部 再生医療プロジェクト 部長)
草薙 尊之 氏(クオリプス株式会社 代表取締役社長)
末水 洋志 氏(公益財団法人実中研 研究部門長)
鈴木 雅実 氏(公益財団法人実中研 トランスレーショナルリサーチ部門長)
粉川 良平 氏(株式会社島津製作所 殿町事業所 所長付け)
厚見 宙志 氏(公益財団法人川崎市産業振興財団 (KIIP)インキュベーション事業推進室サイトディレクター)
澤 芳樹 氏(一般財団法人未来医療推進機構 理事長)※オンライン登壇
野村 龍太 氏(キングスカイフロントネットワーク協議会会長; 公益財団法人実中研 理事長)
林 幾雄 (LINK-J 事業部部長)
ご挨拶
坂田 恒昭 氏(大阪大学共創機構 特任教授; バイオコミュニティ関西 副委員長兼統括コーディネーター)
幸寺 玲奈 氏(経済産業省 生物化学産業課 課長補佐 )※オンライン登壇
講演
基調講演 「東西バイオクラスター連携の意義とエコシステムの構築について」
山崎 達美 氏(公益財団法人実中研 理事)
新規の技術開発と競争力の不足により、日本のバイオ産業は立ちゆかないのではないかと心配されています。このことはかなり定説のように述べられていますが、限られた資源の中で、いくつかの分野ではかなり善戦しているのも事実であり、次世代を担う有望な産業基盤も構築されつつあります。その中で、個別のバイオコミュニティの形もできはじめていますが、継続的な新産業創出にはまだ道程は遠いと考えています。これを解決するための一つの考えとして、継続的な技術、人材、資金の確保に加え、支援システムの相互利用を加速し、従来のクラスター連携や共同作業を超えた多層的なエコシステムの構築と相互利用について、さらにその中に既存産業の参加が重要と述べました。

① 行政の視点から
殿町(KS):殿町国際戦略拠点「キングスカイフロント」の取組
嶋村 敏孝 氏(川崎市 臨海部国際戦略本部 成長戦略推進部 キングスカイフロントマネジメントセンター 所長)
川崎市やキングスカイフロントの取り組みについて網羅的にご説明いただきました。

中之島(NQ):大阪府のライフサイエンス産業振興について
西野 晃弘 氏(大阪府商工労働部成長産業振興室ライフサイエンス産業課長)
大阪府では、ライフサイエンス産業の発展を図るため、世界をリードする大学や研究機関、ライフサイエンス関連企業が多数集積する強みを活かし、創薬・ライフサイエンスをコンセプトとする「彩都」、健康と医療をコンセプトとする「健都」において拠点形成を進めてきました。さらに、本年6月には再生医療をはじめとする未来医療の産業化の推進拠点となる「Nakanoshima Qross」が大阪・中之島に開業いたします。各拠点のコンセプトや特長・強みを活かしながら、イノベーションを創出する取り組みを推進するとともに、2025年の大阪・関西万博の開催を機と捉え、再生医療の社会的意義や可能性を国内外へ発信し、大阪のライフサイエンス産業の活性化を加速させてまいります。

② 立地企業・スタートアップの視点から
岩谷産業のコールドチェーン構築と中之島クロスの取り組み
川井 幸輔 氏(岩谷産業株式会社 産業ガス本部 エアガス部 再生医療プロジェクト 部長)
岩谷産業のコールドチェーン構築や商品サービス、新たな取り組みへのチャレンジ、中之島クロスとの連携や取り組みについて分かりやすくご説明いただきました

クオリプス社の概要
草薙 尊之 氏(クオリプス株式会社 代表取締役社長)
クオリプス社の研究内容、製品概要等の説明、中之島クロスへの期待等を述べました。

飛び立て、世界へ! 君にもできるヒト肝細胞培養実験
末水 洋志 氏(公益財団法人実中研 研究部門長)
医薬候補化合物の代謝研究や安全性評価に実験動物の果たしてきた役割は大きく、その一方で薬物代謝の動物種差を回避できずヒト生体試料を利用しなければならない場面も多々存在します。そこで我々は肝臓の大部分をヒト肝細胞で置換したヒト肝キメラマウスを開発しました。従来の実験動物よりもはるかにヒトに近い薬物代謝特性を示し、動物種差の克服に有用な in vivo モデルとなっています。
個体間差が最少となるよう品質管理された実験動物とは対称的にヒト生体試料、特に肝細胞の特性には大きな個体間差があることが知られます。ヒト肝キメラマウスから取り出したヒト肝細胞ではこの様な個体間差が大幅に縮小することを見いだし、新たなin vitro ツールとして本格的な生産を開始した。穫りたてのヒト肝細胞を新鮮なまま届けたいとの想いを叶えるため最適な輸送法を確立し、「いつでも、どこでも、だれにでも」使えるヒト肝細胞 HepaSH cells を世界に向けて発信しています。

医薬品候補(らしさ)を目指した初期テーマにおけるin vivo実験での協働
鈴木 雅実 氏(公益財団法人実中研 トランスレーショナルリサーチ部門長)
医薬品開発におけるin vitroモデルは、同一細胞で安定かつ多数の実験を比較的少量の化合物で短時間に実施できることからリード化合物の取得、化合物の各種修飾過程でのスクリーニングなど研究の初期から活用されます。一方、in vivoモデルは、評価に時間を要すること、化合物の量を必要とすることなどから、開発候補物質をある程度絞った段階で実施され、臨床予測性が高いモデルでの評価が要求されます。in vivoモデルの要件は、医薬品開発領域の変化とともに、循環系、代謝性疾患などヒトと動物の共通性の高い疾患・生理的反応、普遍性の高い生物反応から、免疫系(腫瘍免疫を含む)、神経系疾患、腫瘍性疾患などヒトと動物の共通性の低い疾患・生理的反応、種特異性の高い生物反応を反映したモデルへと移行しています。腫瘍領域を例とすると、細胞障害性抗がん剤から分子標的抗がん剤への移行に伴い、腫瘍細胞の恒常的な増殖を維持したモデルから、腫瘍の多様性・複雑性を反映し、臨床に近い状態で標的分子を発現するモデルへと変化しています。この課題への取り組みとして、patient-derived xenograft (PDX)、腫瘍の発生臓器・組織への移植(同所移植)、ヒト免疫系を移入したヒト化マウスを組み合わせたモデル系を構築し、外部研究機関と協働しています。

殿町を魅せ、研究者を繋ぐ
粉川 良平 氏(株式会社島津製作所 殿町事業所 所長付け)
株式会社島津製作所は、川崎市殿町キングスカイフロントの新拠点を2023年1月に開所しました。
その新拠点、Shimadzu Tokyo Innovation Plaza のコンセプトは「魅せて繋げる」。
多くの来訪者の方々に、当社装置や技術だけでなく、拠点全体・人財・そしてキングスカイフロントの研究コミュニティをご紹介できるような数々の工夫を取り入れています。
当日はそれら魅力の一端をご紹介し、中之島Qrossとの連携の一助となれればと述べました。

スタートアップインキュベーションの視点から
川崎市キングスカイフロントにおけるスタートアップエコシステムの構築の取り組み
厚見 宙志 氏(公益財団法人川崎市産業振興財団 (KIIP)インキュベーション事業推進室サイトディレクター)
キングスカイフロントの取り組みのご紹介とiCONM with BioLabsの事業概要とコミュニティ形成についてご講演いただきました。

三井リンクラボ中之島が目指す未来
林 幾雄 (LINK-J 事業部部長)
6月にオープンする三井リンクラボ中之島の施設のご紹介と三井不動産とLINK-Jの関西での取り組みについて講演しました。

中核機関の視点から
NQ:Nakanoshima Qross が実現する健康未来都市
澤 芳樹 氏(一般財団法人未来医療推進機構 理事長)
ドバイからオンラインでご登壇いただきました。これまでの関西での取り組みだけでなく6月に開業するNakanoshima Qrossの今後の展望や関連のプログラム等をご紹介いただきました。

川崎キングスカイフロントの歴史と強み
野村 龍太 様(キングスカイフロントネットワーク協議会会長; 公益財団法人実中研 理事長)
川崎殿町キングスカイフロントは2011年に第一号で公益財団法人実験動物中央研究所(現実中研)が進出以来、13年で70機関を超える国内では名の知れた研究拠点になってきました。羽田空港の多摩川を挟んだ対岸にあるいすゞ自動車のトラック・バス工場の跡地を川崎市がライフサイエンス・再生医療の拠点にしようと考え2008年開発が開始、その後民主党への政権交代など紆余曲折の末、民間と川崎市と神奈川県という行政が仲間のような対等な関係で手作りでまちを作り上げた心の籠ったサイエンスの拠点です。全ての逆境を逆手に考え、逆転の発想をベースにまちづくりを行い、その苦労により進出機関が強い絆で結ばれた日本一、世界一仲の良いサイエンスの拠点になった歴史を説明しました。その後キングスカイフロントの特徴と強みを説明し、今後の関西の大学・研究機関・企業・ベンチャーとの取り組みの可能性を示唆いただきました。

全体討議・質疑応答(パネルディスカッション)
坂田 恒昭氏にモデレーターとして入っていただき、質疑応答を含めた全体討論を行いました。グローバルな視点も踏まえた今後の日本のエコシステムについて熱く議論が交わされました。

開催後は、リアル会場限定で会場参加者の皆様と登壇者のネットワーキングがおこなわれました。


参加者からは「中之島クロスと殿町の今後の連携に大変期待させていただける内容でした」「東西拠点の状況が良く理解できた。」「出席者の先生方の熱気あふれる議論に感激しました。」といったご意見やご感想を頂きました。
オンライン、会場を含めて約380人の方にご参加いただきました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。